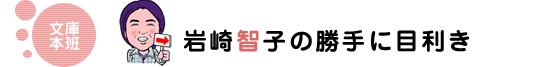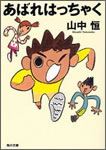WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年6月の勝手に目利き
今月の新刊採点 勝手に目利き
![]()
『そろそろ旅に』 松井今朝子/ 講談社
神田八丁堀に住む弥次郎兵衛(通称やじさん)と、食客の喜多八(通称きたさん)の二人が、厄落としに伊勢詣でを思い立つ。二人が、東海道を江戸から大坂へ、数々の失敗を繰り返しながら旅する様子を描いた滑稽本が、皆さんご存知の『東海道中膝栗毛』。さてその著者、十返舎一九はといえば、やっぱり数々の失敗を繰り返しながら、「人生」という名の旅をした人物だった。
そんな彼の旅を描いたのが、直木賞作家、松井今朝子の『そろそろ旅に』。
歴史小説と聞いて二の足を踏むかもしれないが、そんなに自分たちとかけ離れた事が書いてあるわけじゃない。材木問屋の養子→浄瑠璃作家→黄表紙本の作者と、いくつか職を変えながら、段々自分の目指すものに近づいていった一九。転職を繰り返しても、なかなか自分の適職が見つからない。そんな経験をした人には、「自分らしさ」を見つけるまでの、彼の苦しい気持ちがわかるだろう。でも、苦労は決して無駄じゃない。挫折や失敗を知っている人の方が、より豊かな人生を送れるから。
さて、行き詰まりを感じている貴方、『そろそろ旅に』出てみませんか?
『あばれはっちゃく』 山中恒/角川書店
三十代、四十代の方々には懐かしい、名作ドラマ「あばれはっちゃく」の原作です。
「暮しの環境」や「お金の価値単位」はさすがに違いますが、作品全体としては、古い雰囲気をあまり感じさせませんでした。
本作で読んで思ったのですが、昔はひとりひとりが、もっと自分に責任を持って生きていたような気がします。元日からケガをした父のために、桜間家に来た消防署員に対して姉のてるほが「元日だというのに、もうしわけございません」とあやまるのはそういったことの表れではないでしょうか。今だったら「自分が困っているんだから、正月であろうと、税金で働いている消防署員が働くのは当たり前」と考える人が多くなってはいないでしょうか。懐かしくて読んだ本で、思いもかけず、人間としての在り方を教えられました。
ひとつだけ残念だったのは、ドラマでは定番の長太郎やお父さんの決まり文句が、原作ではなかったこと。面白さがそれで損なわれるわけではないですけど、ちょっと残念でした。