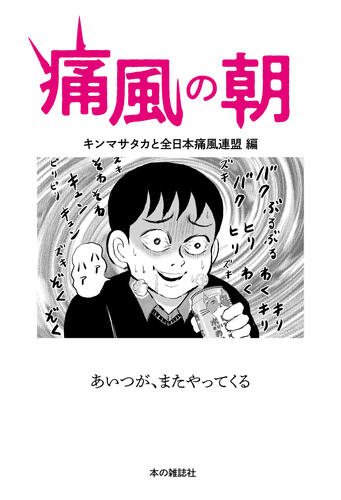はじめに
「とんかつ屋ってどこの町にもあるよね」
そう言ったのは本の雑誌社の杉江さんだった。
その日の杉江さんは小さなとんかつ屋にご執心だった。町のとんかつ屋の存在に気づいたのは自分が最初であるかのように、「年季の入った暖簾がかかっていて」「老夫婦がやっていてさ」「どうやって儲けてるんだろうね」と興奮気味に語り続ける。
杉江さんの言う「町のとんかつ屋」はこんなイメージだ。
いつからあるのかわからない。店主が無口。儲かっているようには見えない。だがポツポツと客が入っていて、手堅い商売を続けていると想像できる。
老齢の店主がやっている店は、もしかしたら持ち家で、賃料がかからないのかもしれない。儲けを重視していないから、どこか浮世離れした雰囲気も漂う。一言も口を聞かない寡黙な店主はもしかしたら狐が化けている可能性だってある。
私たちが町のとんかつ屋を語るとき、「特別うまいわけでもないんだよな......」という言外のニュアンスがあることは否定しない。アラフィフになるまでは、「油で揚げてしまえばたいていのものは食える」と思っていた。衣をつけたフライはだいたい同じ味に帰結するから、ある程度の満足が得られることもわかっている。多くを求めないから、期待を裏切られることもない。
となると、私たちは町のとんかつ屋が出すそれを、スーパーのプライベートブランド商品のように、少し下に見ているのかもしれない。「うまいけどお客さんが来た時に出すのはちょっと違う」というか。
だが、町のとんかつ屋は確かに生き残っている。理由はおそらく「揚げ物の王者」を扱っているからだろう。「とんかつってうまいよね」と言えば誰とでも話が弾む。主に男性だが。
ふと昔のことを思い出す。学生の頃はごはん·きゃべつ·味噌汁おかわり自由のとんかつ店に行くと、きゃべつと味噌汁でごはんを1膳ずつ食べるのが当たり前だった。とんかつとは男子学生の無限給餌装置であったから、今でもとんかつを語る男性の目はみんなやさしい。
誰の心にもとんかつの原風景があるとするなら、自宅近くにあるとんかつ屋は、過去の思い出の暖簾わけみたいなものだ。マダムの伊勢丹並みに信用を持つとんかつブランドだから、町のとんかつ屋はチェーン店に駆逐されず生き残ってきたのだろうか。
一方で、近年では上等なとんかつ屋が人気を得ている。SPFという豚を使っていることが店のどこかに自慢げに掲示され、そういう店に限って席に座って手をおしぼりで拭いていると、メニューよりも先に「塩で食べてください」という文字が目に飛び込んでくる。手の届くところにソースがおいてあるのに。
そうなるとわけのわからない小細工が始まる。「とんかつは塩だけど、こっちはいいだろう」とソースまみれのキャベツ畑を作り出し、やがて野菜で腹が膨らんでしまう。
そういえば、私の自宅近くにも高級とんかつ屋ができたが、気がついたら消えていた。とんかつ業界は意外と競争が激しいのかもしれない。となると町のとんかつ屋は大丈夫だろうか。私は心配になった。
どこにでもあった町のとんかつ屋は、私の知らないところでどんどん消滅しているのではないか......。
そう思って街に出たらなんてことはない。我が家の徒歩圏内に20年以上営業している店が5軒もあって、どこも昼時は繁盛していた。初夏の太陽の下で見る町のとんかつ屋にはたくましさがあった。
その日から、私は何気なく通り過ぎていた町のとんかつ屋が目につくようになったのだ。どうやら町のとんかつ屋(町とんと呼ぶ)には、強烈な吸引力があるらしい。気が付けば知らない町でもとんかつ屋を探すようになっていた。そして少しでも誰かの記憶に残したいと思った。
どの店にも歴史はある。なぜこの街でとんかつ屋を始めようと思ったのかも気になる。それは店主の歴史を紐解くことにもなる。つまりこれは「とんかつ屋の生活史」なのだ。
連載を始めるにあたって、これから訪れる「町とんかつ」の定義を最初に掲げる。
·チェーン店ではない
·ランチのロースが(できれば)1000円以下
大きく言えばこの二つ。
·店構えに年季を感じる
·駅前の一等地にはない
·店主がベテラン
などいくらでも追記したくなる条件はあるが、「大衆店かつ個人店」ということでいいだろう。
というわけで、私はこれからとんかつを探す旅に出る。この連載があなたの町にあるとんかつ屋に想いを馳せるきっかけになれば、それはとても幸せなことです。