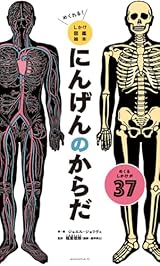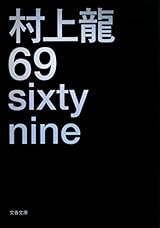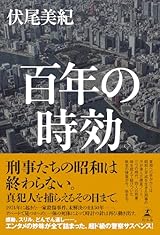くもり時々雨。10時半には会社を出ないとならないため、9時に出社し、6社合同(晶文社、青土社、創元社、白水社、みすず書房、本の雑誌社)読書週間フェアのPOPの色を調整する。
それを終えたら『マンションポエム東京論』の電子書籍用epubデータをモバイルブックjpにアップロード。
アップロードは簡単なんだけれど、このサイトはログインパスワードが13桁以上で大文字小文字アルファベットに数字と記号を入れろ、さらにしょっちゅうパスワードの期限が切れたと変更が求められ、気づけばいつもパスワードの再発行手続きをしているのだった。「昨日浦和レッズでゴールを決めたのは誰?」みたいなパスワードにしてほしい。
10時過ぎに、トーハン、日販の新刊搬入サイトにログインし、「本の雑誌」10月号の部数を確認する。こちらは当初面倒に感じたものの、慣れてしまえば電話で確認するより気を遣わず、楽ちんなのだった。
10時30分に部数確認を終え、配本表を中央精版印刷に送り(これも先月から中央精版印刷が指定するフォーマットデータになった)、会社を飛び出す。
神保町より半蔵門線に乗り込み、二駅先の三越前で下車。11時に誠品生活にあるハッピーレモンで、イラストレーターの信濃八太郎さんと待ち合わせしているのだった。開店と同時にお店に入ると、レジに立っていた女性が困惑顔で、「私は今日が初めてでお店の人がまだ来ていないので来るまでお待ちいただけますか」と言われ、それならそれで構わず席に着く。10分ほどしてお店の人が出社し、オーダを受け付けてもらう。信濃さんとハニーレモンジャスミンティーを飲みながら、単行本の進捗状況を確認する。
一時間ほどの打ち合わせを終えると、今度は銀座線に揺られ、銀座の教文館さんへ。北上次郎『新刊めったくたガイド大大全』の追加注文分を直納。8800円もする本をお買いあげいただいたみなさんに感謝。そして売り切らずに追加注文していただいた教文館さんにも大感謝。
その教文館さんでは階段で2階に上がったところのフェアコーナーで、文春文庫の秋100フェアが開催されているのだった。これは版元が選んだ文庫以外にもいっぱい面白い文春文庫がある!と担当のKさんが奮起し、同僚や他の版元営業に声をかけ、推薦された文春文庫も並べられている。
私もお声かけいただき、以下の5点を推薦したのだった。
和田誠『銀座界隈ドキドキの日々』
海老沢泰久『美味礼讃』
高野秀行『辺境メシ』
大竹英洋『そして、僕は旅に出た。』
東海林さだお『大盛り!さだおの丸かじり 酒とつまみと丼と』
売れますように。
本日は昼メシは食べず水を飲み、小雨降る中、会社に戻り、デスクワークに勤しむ。
途中、京都新聞のIさんが、「『断捨離血風録』の書評が出てました!」と8月31日付の新聞を持ってきてくださる。代わりにこれから出る京都が舞台の小説を教えてあげる。
帰路、東浦和に着くと雨が本降りとなっており、びしょ濡れになりながら自転車を漕いで帰宅。