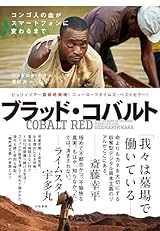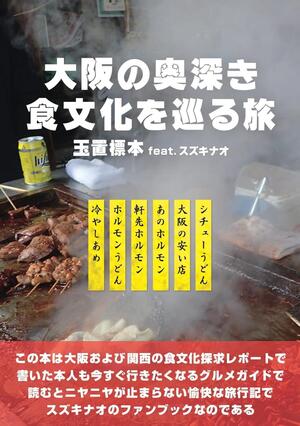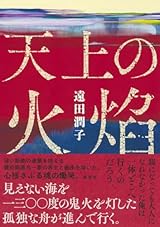10月27日(月)寅雄帰還
朝ラン6キロ。少し前は4時台に走れていたのに、今では6時を過ぎないと明るくならず、通勤を考えるとランニングのペースも上がる。
9時半に出社。すずらん通りで天を見上げ青空を睨む。社内には半分以下に減るはずだった段ボールが山積みで、しばらくすると荷物を預かっていた太田出版のSさんがお礼方々挨拶にやってくる。初参加で二日間完全中止という不幸に懲りず、来年も出店してくれることを願う。
昼食は錦華通りの「立喰いそば 梅市」でゲソかき揚げそば。最近のお気に入り。
3時過ぎに内澤旬子さんから「これ以上帰ってこないと辛くて寅雄の原稿が書けなくなるかもしれない」と中断していた「猫に転んで」の原稿がメールで届いたので、夢中になって読んでいるとその内澤さんから電話が入る。
原稿送付の報告かと思い電話に出ると、内澤さんの背後から猫の声が聞こえてくる。「杉江さん! 今、寅雄が帰ってきたの!! 原稿送ってすぐ目撃情報が届いて」。ううう、そんな奇跡みたいなことがあるのか。二十日間も行方知れずになっていた寅雄が帰ってくるとは。万歳三唱。さすが寅雄だ。
東京堂書店さんから『神保町日記2025』の追加注文をいただいたのですぐに持っていく。ISBNもついていないZINEを取り扱っていただけ、しかもこのように追加注文もいただけるとは大感謝。あっという間にこれまで直接注文で発送してきた数に匹敵する数が東京堂書店さんからお客さまの手に渡ったこととなる。
こうして基本直販のみの本を作ってわかるのだけれど、結局売り場のない本は売れないのだ。売り場があってこそ本は売れるのだ。本を売るには売り場を増やすしかないのだ。
夜、お茶の水の丸善さんに寄って、担当のSさんとお話。
新書売り場で多面展開している水島弘史『プロが大切にしている たった一つの料理のルール』(青春新書プレイブックス)は発売3ヶ月で300冊以上販売しており、さらに文庫売り場で展開を始めた昨年12月刊行の今村暁『朝「10秒そうじ」のすすめ』(王様文庫)は、多面積みを始めて1ヶ月で100冊以上売れているそう。
シッダルタ・カラ『ブラッド・コバルト コンゴ人の血がスマートフォンに変わるまで』(大和書房)と河野正『埼玉高校サッカーの復権を担う男たち』(カンゼン)を購入して帰宅。