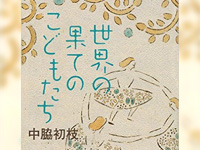
作家の読書道 第171回:中脇初枝さん
こどもへの虐待をテーマにした連作集『きみはいい子』が話題となり、『世界の果てのこどもたち』も本屋大賞にノミネートされ注目されている中脇初枝さん。実は作家デビューは高校生、17歳の時。でも実は作家ではなく民俗学者を目指していたのだそう。そんな彼女はどんな本を読み、影響を受けてきたのか。幼い頃のエピソードもまじえつつ、これまでの道のりを語ってくださいました。
その3「高校生で作家デビュー」 (3/4)
――高校に入ってからはどうだったのでしょう。中脇さんは高校在学中に『魚のように』で第2回坊ちゃん文学賞を受賞してデビューされるわけですが。
中脇:高校も休みがちだったんですけれど、柳田国男をよく読みました。なにしろ、彼は膨大な著作を遺していますので、いくら読んでも読み尽きることがない。すると、自分の知識だけでは読みこなせなくて、古典を読まないと駄目だということに気付くんです。それで、古典も読むようになりました。
いちばん好きなのは『古事記』でした。『日本書紀』やギリシャ神話も読んで、「神様も人が生んだものなんだな」と思いましたね。他には『今昔物語』とか。それに、落語。筑摩書房の文庫が解説もあって勉強になりましたね。自分でも語れるんじゃないかっていうくらい読んでいました。あれは、当時の人が当たり前に思っていたことが分かるんですよね。中学生の頃に夏目漱石の本に出てくる言葉が分からないからそのまま丸憶えして、あとからだんだん把握していったんですが、落語や古典もまさにそうでした。知らない言葉を知らないまま知ることが好きでした。
『古事記』などの神話も民間伝承をもとにしていますし、落語もそう。結局そういうものが好きなんでしょうね。あ、聖書も読みました。
――新約も旧約も、ですか。
中脇:やっぱり旧約が好きでしたね。でも「その妻」なんて書かれてあると、もう誰の妻だか分からなくなるから、頑張って家系図を書いたりもしました。そう話すと、どれだけ暇だったんだろうという感じですね(笑)。もちろん『古事記』でも神様の家系図を書きました。
夏目漱石も好きで、一通り読みました。わたしは6歳からお箏を習っていたのですが、その先生が読書家で、夏目漱石と出会ったのはそこでです。結局、お箏はものになりませんでしたが、たくさんの本と出会わせてもらいました。
――さて、小説を書くきっかけは何だったのでしょう。
中脇:わたしは文学賞といえば芥川賞やノーベル文学賞くらいしか知らなかったんですけれど、偶然、地元の高知新聞で「坊ちゃん文学賞」募集の記事を読んだんです。松山市の文学賞だから「愛媛って隣じゃない」と思って。しかも規定枚数が原稿用紙100枚だったんです。それで、「100枚なら書けるかも」と思ったんですね。そもそも夏目漱石が好きだったし。中学生の時は『虞美人草』のような耽美的なものに惹かれていましたが、その頃は『坑夫』がいちばん好きで。デビュー作となった「魚のように」は『坑夫』を読んでから書いていますね、文章を真似したくて。
――それが見事受賞して、17歳でデビューすることになって。その頃「自分はこの先小説家としてやっていく」とは思っていましたか。
中脇:思っていませんでした。民俗学者になることしか考えていなかったので。それで、どうしても筑波大学で、『妖怪の民俗学』などを書かれた民俗学者の宮田登先生のもとで民俗学を勉強したかったんです。その頃には宮田先生の本も読んでいましたから。
――すごい。全然ブレてない。そして実際、筑波大学に進み、民俗学を専攻されたんですよね。そこではじめて高知を離れたわけですね。
中脇:今でもやっぱり民俗学の本をいちばんよく読むんですが、先生の本の中では、『ヒメの民俗学』と『ケガレの民俗誌』がおすすめです。それと、瀬川清子の『女の民俗誌』という本は、ぜひ女性に読んでもらいたいです。宮田先生の著書と同じく、穢れと神秘性について書かれた本なんですけれど、いつもそのことについては考えますね。
『学校の怪談』を書いた常光徹の『しぐさの民俗学』もおすすめです。たとえば、霊柩車を見ると親指を隠しましたよね。ああいう俗信を突き詰めて考えられています。松谷みよ子の『現代民話考』もすばらしいお仕事だと思います。高知の民俗学者桂井和雄の『俗信の民俗』をはじめとする一連の著作もすばらしい。彼の筆にかかると、単なる民俗資料が詩になるんです。
昔話集では『沖永良部島昔話』などを編まれた岩倉市郎。奄美、新潟などの貴重な言語と昔話をわたしたちに遺してくれました。もっと長生きされたら、どれだけのお仕事をされたかと思います。
――前にジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』に感銘を受けた、というお話をうかがったことがありますが。地域や環境の違いによって文明や文化に違いが生まれるのであって、人種的な優劣はない、という。
中脇: そうそう。この本を読んで、自分は自分だと思っているけれど、人類史という大きなうねりの中で生きているんだということも感じました。今こうして服を着て歩いているのも、そこにたどり着くまでの必然というのがあった。人は一人で生まれて一人で死んでいくわけではないということも思いました。
――大学時代はフィールドワークなどいろいろされていたと思いますが、小説はまったく書いていなかったんですか。
中脇:いえ、書いていました。『魚のように』に収録されたもう一篇は高校3年生、18歳の時に書いたものですし、『稲荷の家(改題して『こんこんさま』)は大学生のときに書きました。『祈祷師の娘』もそうですね。でも、発表がかなり後になってしまいました。











