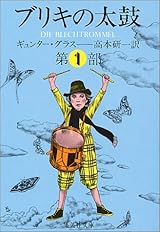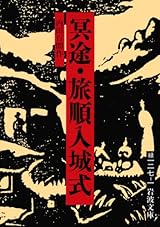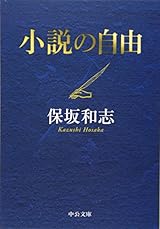作家の読書道 第190回:滝口悠生さん
野間文芸新人賞受賞作『愛と人生』や芥川賞受賞作『死んでいない者』をはじめ、視点も自在、自由に広がっていく文章世界で読者を魅了する滝口悠生さん。実は小さい頃はそれほど読書家ではなかったという滝口さんが、少しずつ書くことを志し、小説のために24歳で大学に入り学び、やがてデビューを決めるまでに読んで影響を受けた作品とは? その遍歴も含めて、たっぷりと語っていただきました。
その3「進学せずに本を読む」 (3/5)
――高校卒業後から20歳くらいまでに読んだのは、他にどんなものがありますか。
滝口:夏目漱石をちゃんと読み始めたのもこの頃かなと思います。高校の頃に読むのってだいたい『こころ』とかじゃないですか。『こころ』はあまり好きじゃなくて、『三四郎』『それから』あたりの勢いのあるところから入って、『行人』とか『草枕』とか『彼岸過迄』とかを読みました。『草枕』が一番好きですね。外の場面が多くて明るい。
太宰治も高校からこの時期にかけて読みました。その頃は長篇がいいなと思って読んでいましたが、最近になって短篇を読み返したらキレキレな感じで、すごく面白かったです。太宰は青臭いという印象が強くて遠ざかってましたが、ちょっと反省して読み直したりしています。あとはこの時期に安部公房もまとめて読みました。『砂の女』とか、作品集では『壁』が好きです。
あと、これも19歳頃に読んだんだと思いますが、水上瀧太郎の『大阪の宿』という小説があります。僕が買ったのは岩波の古本で、今は講談社文芸文庫に入っているんですがもう在庫がなくて、もっと刷ってほしいのでいろんなところで喧伝してます。水上瀧太郎は戦後の「三田文学」復刊などにも関わった人なんですが、生涯勤めながら小説を書いていた人で、『大阪の宿』も実際に仕事で大阪に赴任した時の話です。舞台は土佐堀川沿いで、全篇酒を飲みっぱなし、酔っ払いっぱなし。芸者さんたちと延々とお酒を飲んで騒いでいて、滞在している下宿のいろんな人間模様も書かれていて、それなりに切実な話も出てくるんですが、とにかく万事酒で納めていくところがいい。僕は小説に宴会の場面をよく書くんですが、昨年この本を久しぶりに再読して、ああこれを読んでたからなのかもと思いました。ラストシーンも素晴らしくて、これはおすすめです。
村上春樹もこの頃にひととおり読みましたが、一冊選ぶなら『ねじまき鳥クロニクル』。戦争中の、モンゴルの話がすごく長いのがいい。『海辺のカフカ』はちょうどその頃に出たのでリアルタイムで読みました。海外ものを読み始めたり、近所ではない古本屋に行きはじめたのもその時期で、村上春樹もそのきっかけのひとつかなと思います。
――海外ものでは何を。
滝口:ギュンター・グラスの『ブリキの太鼓』も読みました。ポーランドの話ですが、グラスはドイツ人ですよね。その頃知り合いに日本に留学していたセルビアの人がいて、ドイツ語の本を読んでいるというので教えてもらったんだと思います。印象に残っているのでは、カフカいろいろ。カミュの『異邦人』、『罪と罰』もその頃。この時期は手あたり次第に読んでいたので、記憶がごちゃごちゃしています。
――名作として読み継がれているものが多かったのですか。
滝口:聞いたことがあるな、という本も手に取るし、よく知らない作家の本もタイトルとかがピンときたらとりあえず読んでました。西荻の古本屋で買ったキイランドというノルウェーの人の短編集とか、よかったです。
日本では少し前の時代のもの、内田百閒の『冥途』とか、梶井基次郎の『檸檬』もその頃でした。基本的に古本屋で文庫本を買っていたので、同時代の作家の小説に出会いにくくて、文芸誌などを手にすることもほとんどなかったです。同時代の小説で読んでいたのは町田康さんですね。ひと通り読んで、その影響も大きかったですが、町田さんもどちらかというと音楽から入って知ったので、まだ日本の現代文学にはちゃんと出会っていないという感じです。
――本を読む以外はどのように過ごしていたのですか。
滝口:音楽は中学の頃から好きでよく聴いていました。学生の頃も、本より音楽の方が好きでしたね。あとはアルバイトをして、貧乏旅行をしたり。『深夜特急』とか好きで読んでいたので、海外に行けばいいのに、国内ばっかりでした。バイクや電車で東北に行ったり、九州に行ったり。
――20歳くらいまではよく本を読んだということで、20歳以降は何があったのでしょうか。
滝口:いろんな本を読みながら、何か書くことはしたいけれど茫洋としていて。その頃に保坂和志さんの『カンバセイション・ピース』を最初に読んで、そこから他の小説や小説論のほうも読み始めて、長いものを書くことが自分の中で少し現実的に感じられるようになってきたんですね。それで文芸誌なんかも時々読むようになりました。高橋源一郎さんの小説論も同じ頃に出て、そのお二人の小説論が、自分が実際に書き始める時の手がかりとしては大きかったと思います。保坂さんは『小説の自由』で、高橋さんは『ニッポンの小説』。
そういうのを読むと、小説だけでなくて、文芸批評の話が入ってきて、現代思想とか哲学とかの話にもなってくるじゃないですか。で、そういう入り口があるのかと思い、そっちの方面も読もうとなってくると、いきなりフランスの現代思想を読んでもよく分からない。それで勉強しようと思って大学に行ったんですよね。それが24歳くらいかな。
――しばらく学校教育から離れていて、そこから受験勉強をされたわけですよね。
滝口:そう。でも英語くらいですけどね。英語と小論文みたいな試験だったので。社会人向けの入試の枠があって、それはそんなに難しくなかったんです。今は学部の編成が変わってなくなってしまったんですけど、いい制度だったのになと思います。学びたくなってからも学べる、という門戸はもっと用意されていてほしいと思います。