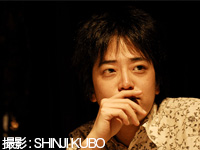
作家の読書道 第152回:中村文則さん
ミステリやスリラーの要素を感じさせる純文学作品で、国内外で幅広い層の読者を獲得している中村文則さん。少年時代は他人も世界も嫌いで、学校では自分を装っていたのだとか。そんな中村さんが高校生の時に衝撃を受けたのは、あの本。そして大学時代がターニングポイントに…。デビューの裏話などを含めたっぷりうかがいました。
その5「純文学は楽しい!」 (5/6)
――中村さんは純文学とエンターテインメントの区別を意識していますか。
中村:僕は純文学作家です。純文学はもっと面白いものだということは伝えたい。純文学の幅を広げたいんです。よく「文体か物語か」という二元論がありますが、僕はその意味がよく分からない。「文体も物語も」でいいんじゃないかと思います。物語性の否定というのはよく分かるしそういう作品も読んでいて好きだと思うけれど、みんながみんな物語を否定する必要はないんじゃないかと。純文学はもっと多様であるべきだと思います。それは、僕の原風景として、ドストエフスキーの物語性に富んだ作品があるからかもしれません。純文学だけどストーリーがあってスリルがあってハラハラドキドキしていていいじゃないですか。『掏摸〈スリ〉』や『去年の冬、きみと別れ』はもろにその手法にしていますね。『掏摸〈スリ〉』はドキドキする展開にしたし、『去年の冬、きみと別れ』はミステリですし。たった一文でがらっと変わってしまうというのも、元をただせば安部公房がメタ的なことをやっていて、その影響もあるかもしれない。
――今年、ノワール小説に贈られるデイビット・グーディス賞も受賞されましたよね。
中村:フィラデルフィアにあるノワールコンベンションという団体が2年に一度、1人に贈る賞だそうです。確かに僕の小説は暗いのでノワールと言えますね。『悪と仮面のルール』でブラム・ストーカー賞の候補になった時はダーク・ファンタジーの賞だと聞いてなるほどあの小説にはそういう面もあるよな、と思いました。好きなように読んでもらえたらいいです。アメリカではクライム・ノベルの棚に置かれていることが多いけれどリテラチャーの棚にもあるし、ヨーロッパに行くと純文学っぽい感じで読まれていたりもする。最初に欧米圏で翻訳が出たのは『掏摸〈スリ〉』なんですが、翻訳2冊目にそれぞれの国のカラーが出ていますね。アメリカは『悪と仮面のルール』でスペインは『何もかも憂鬱な夜に』、フランスは『銃』という風に。
――どの作品でも人間の中の"悪"がテーマになっていると思います。
中村:ずーっと書いていますよね。僕は人間を書きたいんです。人間を書く手段として、悪の側から書くというのをつねにやっている。そこに人間の根源があるような気がする。それは僕が今まで挙げてきた本の系譜に連なっていますよね。
――ノワールやミステリは読みますか。
中村:実は全然で...。『去年の冬、きみと別れ』を書く時に仕掛けが他の作品の真似になっていないか確めようとして、そこから有名なものをいろいろ読みました。ただ、古典的な海外の推理小説でも、そんな凶器で殺すってどうなの? と思ってしまうことがあります。犯人の動機や整合性も気になる時がある。リアリズムを求めてしまうんです。



