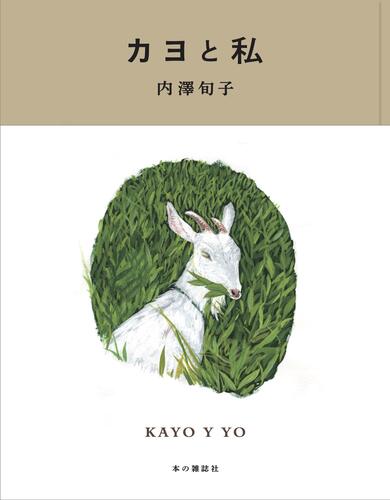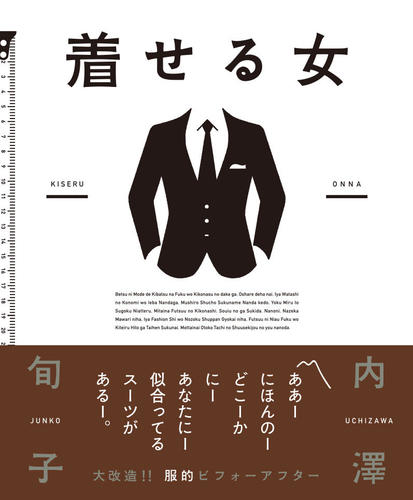第5話 寅雄、マムシに噛まれる
何度も何度もシュシュを投げさせられると、むかーし親せきの子どもと遊んだ時のことを思い出す。大人はすぐに飽きて疲れてしまうのに、子どもは延々と繰り返して遊びたがる。まさにアレだ。多分寅雄も大人になったらこんなふうにはしゃいで遊ぶこともないのかもしれない。今だけの狂乱ぶりと思うと、なんとも尊さが増す。いや、でも爪は鋭いままなので、私の手はズタズタに傷ついている。今のところ化膿したりしていないが、このままだといつか腫れ上がったり熱を出したりしそうだ。
寅雄は散々遊び尽くした後に、飲み残していたミルクを飲んで、フリース毛布と戯れながら、ウトウトしはじめた。おおお、やっとうちで寝てくれるの?? ハッと警戒してこちらを見る。いいんだよ、寝ていいんだよ、寅雄。
寅雄はウトウトしながらハッと目を覚ますを数回繰り返した後、パッと立ち上がり、台所の窓を仰ぎ見る。出ていきたんだね。ここで引き止めない方がいいだろう。はいよ。
窓を開けてやると、流し台にスッと飛び上がり、窓から半身を出して逡巡している。何も言わずに静かに見守っていると、迷った挙句に戻ってきた。はじめてのことだ。じわんと嬉しい。夜をここで過ごしてもいいのかも、と思い始めているんだろうか。
そろそろ私も寝るよ、歯を磨いて薬を飲んで、寝室に移動すると、トコトコと寅雄もついてくる。そうして寝室に入るとトストス歩いてそのまま猫ドアを開けて出て行ってしまった。と思ったらすぐにまた入ってきた!! 猫ドアからひょっくり顔を出して入ってきてくれた!! 少ししてまた出て行ってしまったけど、自分の意思で入ってきてくれた。ようやく窓以外の場所から入ることを覚えてくれたのである。
その晩は天井裏からゴソゴソ音が聞こえてきた。天井裏の探検をしているのだろうか。少しでも猫の気配があれば、ネズミは来なくなるのでとても助かる。
ウチで寝てくれるまであとひと押し、なのだろうか。もし朝まで一緒にいてくれたら、獣医さんのところに連れて行こう。鼻水を垂らしているからできれば早く連れて行ってやりたい。
寅雄をうちの子として迎えたい。むくむくと欲がもたげてきたのをはかったかのように、寅雄はなんとまた蚤取り首輪をしてきた。以前の首輪と同じ水色と白のストライプで、今回は少しきつめに装着され、余分はきっちり切り揃えられていた。
「うちで飼ってます」という意思がそこはかとなく感じられる。とはいえこうしてフラフラ外に出てくくるんだから、飼い主は私よりかは年配の方なのだろうか。獣医に連れていく気がまた挫けてしまう。
そうしてよその誰かがつけた首輪をつけたまま、寅雄はどんどん私の家にいる時間が長くなっていき、夜ご飯を食べた後に私に寄り添ってゴロゴロした後、寝室のソファで眠り、朝私が起きると同時に朝ごはんを要求するようになっていた。朝ごはんを食べると颯爽と外に飛び出していく。
寅雄をうちの子として迎えたい気持ちはありつつも、その頃の私はひどい睡眠分断障害に悩まされていて、果たしてこの子を家の中だけで飼えるのかどうか、毎晩深夜にドンジャラ暴れ回ったりしたらおそらく一睡もできなくなるだろうから、きついかなーと迷う気持ちもあった。
私に甘えてくれるようになった分、寅雄は椅子で爪研ぎするわ、家の中を駆け回って洋服箪笥の中で転げ回るなど、なかなかの暴れん坊ぶりを発揮してもいた。何もかもがあの大人しかった黒猫のノアールとは違うのだった。
猫を躾けることはできないようだし、暴れるのもまた寅雄の個性なんだろうし、なんなら愛しくもある。それでも夜中に寝られないのは、なあ。
ある夜は寅雄があんまり騒がしいので、もう暖かいことだし納屋で遊びなと外に出して猫ドアを閉めてみたら、入れて欲しいと大騒ぎだ。猫ドアを開けて入れてやり、夜は静かにしてくれないだろうかと真剣にこんこんとお願いしてみたところ、五時までなんとか目覚めずに寝ることができた。本でも読むかと思ったら寅雄は私が起きたことを察知してもう遊ぼうモードになって目をぎらつかせている。エネルギーの塊みたいな多動猫だ。キッチンはモノが多すぎるので、私がいる時以外は入れないようにいつもドアを閉めておくことにした。
初夏が深まり、草丈もしっかり伸び蔓延るようになってきた。夕方に寅雄がニャ......と弱々しく鳴きながら夕ご飯をもらいにきたのだが、なんだか元気なく座っている。いつもなら(いつもならという言葉を使ってしまうほど毎日毎晩一緒にいるようになった。もう当たり前のように私の布団に乗ったり枕元で寝ている)ご飯くれくれと鳴きながら私にまとわりつくのに、しょんぼり座って前足を片方浮かせている。何か罠に引っかかったとか?? 人間に意地悪された?? どうしたの、寅雄。
慌ててチェックしたけど体のどこにも外傷らしきものは見当たらない。一応歩いているし。そもそもうちに歩いて戻ってきたのだし。ご飯をあげてみたが、ほとんど食べない。そして足がどんどん腫れ出した。
蜂に刺されたの?? アシナガバチが家の周囲各所で鋭意営巣中なので、そこを触ったんだろうか?? スズメバチはまだ季節ではないし、飛んでもいない。
ぐったりしているので怖くなってネットで調べてみると、蜂に刺されてアナフィラキシーショック起こす猫もいるらしい。医者に連れて行ったほうがいいとも書いてある。金曜日の夜なんだが。パニックになって島の猫飼いの友人に直電をかける。直電なんてしたことないのでびっくりしている友人に、実は今通いの野良猫の面倒を見てるんだけど、蜂にさされたみたいで足が二倍くらいに腫れてしまったのと畳み掛ける。
あー、私の猫も蜂に刺されて顔がパンパンに腫れたことあって、慌てて獣医に連れて行ったんですけどね、猫は蜂に刺されてもマムシに噛まれても大丈夫だからって先生に言われて何にも処置なくて帰されましたよー。
え、そうなの??
それに港の動物病院なら土曜日もやってますよ?
うん......でも明日朝から岡山に仕事で行かなきゃならなくて......。
夜も六時半までやってるから。
あ、それなら間に合うかも!! ありがとう!!
とりあえず台所の床に敷いたフリースの上でぐったり寝ている寅雄を抱えて寝室に運び、私の布団の横に寝かせる。肉球に触ってみるけどそれほど熱は持っていない。あれ、二箇所濡れてる。ティッシュでぬぐうと薄すらと赤い。牙の跡か。つまりはマムシか!! マムシに噛まれちゃったのか......。念の為寝室にご飯とお水を移動させて置いておく。元気になったらすぐに食べられるように。
夜中に目覚めるたびに死んでいないかと寝息を確認する。ふと目覚めたらフリースの寝床を抜け出して私の顔のすぐそばに来て寝ている。いつものパターンだ。あれ、少し元気になったのだろうか。
五時半に起床してみると、脚の腫れは二倍のパンパン状態から1.2倍くらいにおさまりつつある。すごいな寅雄。しかもご飯も食べてる。六時すぎには出発しなければならなかったので、着替えて朝ごはんを入れてお水も換えて寝室におく。
大丈夫かい?と寝そべる寅雄に話しかけると私が被っている帽子の紐に戯れようとしてきた。動きはまだ少し鈍いけど、戯れる気持ちになったのだから、かなり回復している。噛まれたところをつまむように噛んでいる。痒いのだろうか。
夕方五時に帰宅すると朝ごはんは空っぽで、寅雄は寝室の猫ドアからお外に出たのか不在だった。出て行くくらいなら大丈夫なのだろう。病院に連れて行くことはやめた。
疲れて重い体を引きずり、ヤギ舎へ行く。山のようにブロッコリの抜き株が届いていたので十株くらい投げ入れたのだが、カヨは気に入らないようで食いが悪い。他の三匹はばくばく食べているのに、不満そうに私を見る。しょうがないので麦畑の中に青い穂をつけて茂っているイネ科雑草を刈ってカヨに与える。
暗くなりかかる頃に家に戻り、しばらくすると寅雄がにゃあと帰ってきた。脚の腫れは完璧に引いていて、すっかり元気そうだ。ご飯ちょうだい、それじゃなくてお魚はないのなどと鳴いている。よかったよかった。
和犬と和猫は蜂とマムシの抗体を持っているという説はどうやら本当らしい。
洋犬はダメらしく、近所の人の話ではマルチーズを飼っていてマムシにやられた人は、治療に十万ほど飛んだとか。ヤギ舎大家さんの飼い犬エイトは、甲斐犬と紀州犬の雑種で、お腹をマムシに噛まれた時には獣医に連れて行っても化膿止めだけ処方されて帰ってきたそうだ。
小豆島では犬や猫がマムシに噛まれるのは特に珍しいことではないようだ。
実は私自身も一度だけマムシと急接近したことがある。ヤギたちのご飯としてサツマイモの蔓をいただいた時のことだ。その時の蔓は畑の脇に山積みになっていた。一本が枝分かれしながら5メートル以上になっているものが絡まり合っていて、非常に扱いづらく、重い。二人がかりで山ごと持ち上げ軽トラックの荷台に乗せたものの、一人では下ろすことができない。荷台の端に押切りを乗せ、蔓を少しずつ切って下ろしていたところ、山の中に潜んでいたマムシまで気づかずに一緒に切ってしまった。
運良くちょうど頭から5センチくらいのところで切断できたので、首なしの胴体は跳ねて暴れまくっていたが、噛まれることはなく絶命してくれた。もし尻尾の方から5センチを切っていたら確実に襲われ噛まれていただろう。今思い出してもゾッとする。
そして寅雄はというと、その後も懲りずに蛇に手を出していることが、後々明らかとなるのであった。