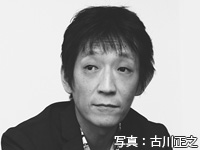
作家の読書道 第160回:薬丸岳さん
2005年に『天使のナイフ』で江戸川乱歩賞を受賞、以来少年犯罪など難しいテーマに取り組む一方で、エンタメ性の高いミステリも発表してきた薬丸岳さん。実はずっと映画が好きで、役者をめざして劇団に所属していたり、シナリオを書いて投稿していたことも。そんな薬丸さんを小説執筆に導いた一冊の本とは?
その2「"監督・出演"に憧れる」 (2/5)
――役者になりたいと思われたのは、いつくらいからですか。
薬丸:高校に入ってからですね。それまでは「映画に携わる仕事がしたい」と思っていました。小学校の頃は映画評論家になればただで映画が観られるしお金ももらえていいな、って(笑)。中学生になると「監督っていいな」と思うようになって。中学の終わりか高校に入ったばかりの頃に『竜二』という日本映画を観たんです。金子正次さんという方が作られた自主映画だったんですが、ご自身が主演して、脚本も書いて、3000万円くらいかけて作った作品だったんですが、公開と同時くらいにお亡くなりになったんです。33歳くらいで。それまでは無名な方だったんですが『竜二』がすごくクローズアップされて、もう伝説的な感じになっていって。それで、自分で物語を書いて、役者もできたらいいなというような憧れを抱きはじめました。
――『竜二』はどういう作品なんですか。
薬丸:やくざの話なんですよね。家庭を持っていたけれど妻子と別れてやくざとして生活していた男が、やくざを引退して妻とよりを戻して子供とも一緒に暮らし始めるんですけれど、結局やくざの世界に戻ってしまう。シルベスター・スタローンの『ロッキー』も自分で脚本を書いて主演している映画ですが、そんなに有名でなかった役者さんが自分で主演して映画を作って、それが世の中でぱあっと評価されるというのはすごいなあ、と。ですからあの頃は物語を作って、まあできたら役者にもなれたらなあ、という憧れを持ちました。
――実際に物語は作り始めたんですか。
薬丸:高校に入った頃にはシナリオを書いていました。あの頃はディレクターズ・カンパニーという、日本の監督さんが何人か集まってギルド的なものを作っていたんですね。相米慎二監督ですとか、当時若手の優秀な方が集まっていて、そのディレクターズ・カンパニーがシナリオやあらすじを募集していたんです。そこに応募していました。全然通らなかったんですけれど。
――どういう内容が多かったんでしょう。
薬丸:青春ものというか、暗い、変な話ですね。ATGなどの暗い映画が好きだったので。
――もともと文章を書くのは得意だったんですか。
薬丸:あんまり好きじゃないんです(笑)。今でもそうなんですよ。Twitterとかメールとか、駄目なんですよ。書く作業は全部小説にぶつけています。
――小説以外は、日記などもまったく書いていない、と。
薬丸:日記はデビューしてから一時期書いていました。たいしたものではなくて「今日こういうことがあった」ですとか「ここに行ってきた」とか。先日久しぶりに見てみたら、特に1年目、2年目は「俺はこのままでは駄目だ」とか書かれてあって、なんというか、笑ってしまいました。
――部活で演劇部や映画研究部に入ったりはしなかったのですか。
薬丸:アマチュアの劇団に参加したことはありました。舞台には立たなかったんですが、荻窪の区民会館に集まって一緒に稽古したりして。それと、エキストラのバイトをしていました。
――さて、高校を卒業後はどうされたのでしょう。
薬丸:東京キッドブラザーズという劇団のオーディションを受けて、研究生になったんです。僕の記憶では半年くらいいたつもりだったんですが、一昨年くらいにキッドの方とお会いすることがあって話していたら、どうやら4か月くらいで辞めたみたいです。
――あれ、ずいぶん短いですね。役者になりたいとずっと思ってきて、きっと倍率もすごかったんでしょうに。
薬丸:若かったんでしょうね(苦笑)。倍率は12倍くらいだったのかな。同期の何人かと「自分たちで劇団を旗揚げしよう」なんて話になって「じゃあ僕が台本を書く」と言っていたんですけれど、結局それも達成できず。中途半端な駄目人間だったんです。劇団を辞めてからはバーテンダーをやっていて、そっちのほうが面白くなって、一時は本当にその仕事をずっとやっていきたいと思ったくらいのめり込んだんですが、結局それでも、家に帰ったらワープロを打っていて。自分はやっぱり物語を作ることがやりたいんだろうなと思い、バーテンダーを辞めて、フリーターをしながらシナリオを書いてはコンクールに応募するという生活を送りました。22、23歳の頃に「独学では難しいな」と思い、六本木のシナリオ学校に通い始めました。そこで後に紅白歌手となる木山裕策さんと知り合うんです。学校自体は半年間くらいで、その後ゼミで1年間くらい一緒でした。
――学校とゼミは違うんですか。
薬丸:何人か先生がいらっしゃって、半年学校に行くと、その方たちのゼミに入ってもいいよ、という感じでした。ゼミは2週間に1回くらい、みんなで集まって作品を批評しあっていて。それを1年くらいやって、また独学に戻りました。......話していたら恥ずかしくなってきました(笑)。なんか僕、駄目駄目ですよね。
――いやいや。そうやってシナリオをどんどん書いている時って、インプットも必要だと思うのですが、映画を観たり本を読んだりもしていたのですか。
薬丸:映画は相変わらず、唯一の娯楽として観ていました。本は、20歳くらいからノンフィクションを読むようになりました。少年法に興味があって、女子高生コンクリ殺人事件の裁判のノンフィクションが出たら買って読んだりしていました。それはシナリオの勉強とは別で、勉強としては小説もある程度は読んでいました。年末に出る『このミステリーがすごい!』のランキングを基準にしていました。情報があまりなかったので、「このミス」で上位に入っている作品、たとえば真保裕一さんの『ホワイトアウト』とか大沢在昌さんの『新宿鮫』とか、東野圭吾さんの作品とかを読みました。
――ということは、ミステリのドラマを書こうとしていたのでしょうか。
薬丸:いや、単純に自分が好きだったんでしょうね。嗜好として。だから映画も、いろんなものを観てはいましたけれど、やはりサスペンスやアクションとかが好きでした。でも自分が書くシナリオに関してはそうでもなくて、日常の生活を描くもののほうが、まだ簡単に書けるように思っていました。それは思い違いなんですけれどね。今となっては分かるんですが、自分の努力が足りずに中途半端にしか考えていなかったからそう思っていただけの話であって。
――さきほど女子高生コンクリ殺人事件に少し触れましたが、それは薬丸さんにとってものすごく影響のあった出来事だったそうですね。
薬丸:事件が起きたのは僕が19歳の時だったと思います。高校を出て、キッドを辞めてしばらくした頃にあの事件が起きたんだと思います。恥ずかしい話ですが、それまで少年法のことも全然知らなかったので、すごく「こんな理不尽な法律があるんだ」と思ったんです。それに、被害者の方にしても加害者にしても、自分と1歳とか2歳しか変わらなかったことにも、非常に衝撃を受けました。同じくらいの世代で、こういうことができる人間がいるのかということがショックで。
――そこからいろんなノンフィクションを読むように
薬丸:でも、その時点では、物語に書こうという気持ちはなかったんです。単に自分の興味として、そういう事件ものは読んではいましたが、なぜか作品に反映させようとはまったく思っていませんでした。
いちばん大きかったのは、被害者の方やご家族の方への感情移入でしょうね。もしも自分の家族が、あるいはもしも自分の付き合っている女性がそんな目に遭わされたら、という、すごく単純かもしれませんが、そういう怒りだったんです。当時、『週刊文春』が実名報道してバッシングされたりしたんですよね。僕、編集部に電話して「応援します」って言ったんです。後にも先にもそんなことはないんです。それくらいあの事件は自分の心をかき乱されるものだったんだと思います。
――それが19歳の時で。20代はシナリオを書いて...。
薬丸:書いては落とされ、ですね。10何本か書いていると思います。
――その時書いたシナリオで、後に小説化したものはありますか。
薬丸:ドラマ用のシナリオではないですね。ただ、『ヤングジャンプ』の原作賞で佳作を何度か獲ったんです。それは大沢在昌さんが選考されていました。佳作なので漫画にもなっていないんですけれど、佳作のひとつの話のオチは『刑事のまなざし』の「オムライス」の原型なんです。
――あ、漫画原作ではミステリを書きはじめたということですか。
薬丸:そうです、ミステリやサスペンス的なものを書きはじめたのは、漫画の原作を書きはじめてからなんですよね。ドラマのシナリオではファンタジーや青春ものを書いて、漫画の原作は最初はスポーツものみたいな話を書いていたんですけれど、最初に佳作を獲ったのも次に佳作を獲ったのもサスペンスタッチのものでした。唯一漫画になったのは、誘拐ものでした。
――ドラマのシナリオにしろ漫画の原作にしろ、他の人が映像化するものの原型を作ろうとしていたわけですね。
薬丸:当時の認識として「小説は難しい」という気持ちがあったんですよね。今はそう思っていないですし、シナリオにはシナリオの難しさがあると分かっています。でも当時は、小説は描写を重ねていかなければいけないけれど、シナリオなら台詞とト書きだけで書けるから、素人のぱっと見でシナリオのほうがまだ可能性があるんじゃないかとい思ったんです。それは大きな思い違いでした。
――シナリオを勉強したことで小説の執筆に影響を与えていることはありますか。
薬丸:あるんだと思います。『天使のナイフ』で江戸川乱歩賞をいただいた時に、直接ではないんですが真保裕一さんが「シナリオを書いていた経験があったからこういう作品が書けたんだろう」といったことをおっしゃってくださったようで、それを聞いて僕としては、すごく無駄な回り道をしてきた感覚があったけれど、自分のいろんな引き出しになっているのは、シナリオを書いていた時期に得たものだなと思って。シーンの運び方なんかも、シナリオを書いていたことが原型になっていると感じます。
――シナリオを書く時は先に映像が頭にあったのでしょうか。小説ではどうでしょう。
薬丸:ぼくは映像が先にあって、文章はあまり考えていないですね。小説でも、自分の中に浮かんだ映像を文章に起こしている感覚です。

![竜二 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/4174OMEKvxL._SX160_.jpg)
![シルベスター・スタローン ロッキー ブルーレイBOX(6枚組)(初回生産限定) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/610-Xyrll6L._SX160_.jpg)

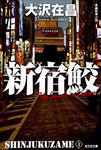
![ヤングジャンプ 2015年 5/28 号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51PQtEdUXhL._SX160_.jpg)

