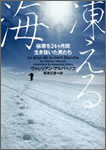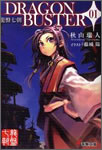WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年7月 >余湖明日香の書評
『デカルトの密室』
評価:![]()
高性能な人型ロボットが実用化された社会で、2組のロボット学者とそのロボットの対決が始まるかのような序盤。いかに人工知能が人間らしい受け答えを出来るかを競う大会で事件は起こり、「人間と機械の違いは何か」を読者に投げかけてくる。そう、この小説は全編を通して、主人公が悩み考えると同時に読者にも同じことを要求する。小説というより科学や哲学の講義の勉強をしているような気になる。最初は途中から用語や理論に頭がパンク、手に負えなくなったので、新潮社のホームページにあった瀬名秀明さんの「デカルトの密室 特別講義」を参考にしながら読み進めた。が、しかし、行きつ戻りつしながら丁寧に読み進めたけれど、自分がそれを全て理解できている自信はない…。
プロローグからもわかるように、『2001年宇宙の旅』とチェスが物語の重要な鍵となる。大学の認知心理学の時間に読んだシュテファン・ツヴァイク著『チェスの話』を思い出した。軍隊に全く何もない部屋に監禁された男は、偶然手に入れたチェスの本を繰り返し読み、暗記し自分の頭の中で繰り返し繰り返しチェスの対局を行うというものだ。
密室・チェス・心。このキーワードにぴんと来た方はぜひこちらもお勧めだ。
『どちらでもいい』
評価:![]()
な、なんなんだろう、これは?!アゴタ・クリストフを全く知らない私はこの不思議な短編たちに呆然。
ブラックユーモアよりも温度が低い。感傷的なようでいて感傷的ではない。詩?散文?エッセイ?ショートショート?故郷・家族・愛・人間・人生…そういったものに対する執着を吹き飛ばして、乾いた紙のページにひそやかに並べられた文章。特に気になったのが「間違い電話」や「ホームディナー」。読み終わった後にぞっとしてしまう。
戸惑いが大きく、まだページ半ばで私は「訳者あとがき」を盗み読んだ。ふむふむ、アゴタ作品の長編小説の元になっているもの・関連するものも多いのか。さて、帯で「奇跡のベストセラー」と称されている代表作『悪童日記』とはなんぞや。
ネットで調べてみて驚き。あの『MOTHER3』(ゲームボーイアドバンスのゲームです)は『悪童日記』の影響を受けていたんだ!『MOTHER』シリーズが大好きな私はそんな不純な動機から、すぐに『悪童日記』を購入。不勉強な私は『悪童日記』を読んで再挑戦しようと決意したのだった。
『ちなつのハワイ』
評価:![]()
大島真寿美さんの作品は、意識して読んでいたわけではないのに、ふと気がつくと私の読書生活の傍にあった。
図書館でタイトルが気に入って借りた『チョコリエッタ』、古本屋のセールでなんとなく買ってしまった『ほどけるとける』、しょっちゅう通っていた本屋さんで毎月もらってくる「asta*」に連載していた『やがて目覚めない朝が来る』、そして今回、送られてきて手に取った『ちなつのハワイ』。
今回今まで読んだその作品を思い返してみて、その時の私が欲しているなにかを、無意識に満たそうとして手に取っていたのではないかと思えてきた。
それは大切にしたい自分のリズムだったり、家族との時間だったり、尊重したい他人との距離感だったり。そういったものを物語を通してそっと差し出してくるのだ。
実は、本編よりも、あとがきの方を興味深く読んでしまった。この『ちなつのハワイ』は一度お蔵入りになったものだが、不思議な出会いによって出版されることになったそうだ。大島さんは、物語が出て行くのにふさわしい場所・形・時期を選んで勝手に動いていくという経験を何度かされていると語っている。まさに、私と大島さんの本との出合いもそうなのでは?
『凍える海 極寒を24ヶ月間生き抜いた男たち』
評価:![]()
まず、北極の氷に閉じ込められた船が1年半漂流しているところから始まるというのが驚き。それだけでもう一冊の本になるのではないかと思う。
だけどこの作品は、そこから11人の乗組員達が、助けが来るのを待って船に残ることを主張する仲間に別れを告げて、自力で助けを求めて旅立とうとそりを手作りするところから始まるのだ!!
わずかに残ったノートを元にこの作品を書き上げたアルバーノフの、生きる力に胸を打たれる。一日わずか数キロの距離を南進しては、進んでいる氷ごと北に押し流される。それでも彼は絶望せず、仲間をはげまし、なだめすかしながら着実に進む。生命を脅かすものは天候・野生動物・少なくなる燃料と食料・おぼつかない進路・慢性的な疲労・くじけそうになる心など数限りなくあるというのに。そんな中でも私が一番はらはらしたのが、仲間から裏切り者が出て、貴重なショットガンや食べ物を持ち逃げされたところだった。(そしてこの裏切り者の名前を最後まで明かさないところが、アルバーノフのもっとも男らしいところだと思う)
船に残ったメンバー、アルバーノフに同行したものたち、裏切り者達はどうなったのか、アルバーノフはどのように生還したのか、ぜひ読んで確かめていただきたい。
『DRAGONBUSTER 01』
評価:![]()
異世界中華風ファンタジー。十二国記も彩雲国物語も大好きなので、わくわくしながら読んだ。
まだ第一巻ということで、物語が動き出す前の、背景や登場人物の準備段階といった印象。第二巻を読んでみないとまだなんともいえないけれど、ひと癖もふた癖もある登場人物たちのやり取りが楽しい。
こういったファンタジーでは、いかに世界観が整っていて奥行き深く存在しているかが私は楽しみになるのだが、作中に出てくる芝居や、遊びなどが効果的に使われていて、入り込みやすい。実際にどこか中国の史実から元ネタを取ったのではないかと思ってしまった。
電撃文庫を久々に買ったら、(そういえば最後に買ったのも秋山瑞人作品でした)折込の新刊案内のチラシのボリュームがものすごくなっていた。このメディアミックス作品群、すごいなあ。
『子どもたちは夜と遊ぶ(上・下)』
評価:![]()
「すごく面白いんだけど、登場人物の存在や発言に納得がいかない伊坂幸太郎作品を読んでいるよう。」変な例えだけれどもし友人にこの本を貸すならこう説明するだろう。
かっこよくて頭のよい登場人物たちが、無記名の論文コンクールから始まった不可解な連続殺人事件に巻き込まれ、それぞれの孤独を抱えながらも気持ちを通わせていく。
伏線が丁寧で、下巻では驚く仕掛けも用意しぐいぐい引っ張る。
だが、登場人物がゲームや漫画の中の人物のように感じてしまうのだ。あまりにも自分の周りの大学生や教授と様子が違っているからかもしれない。もちろんこれは小説だから、かっこいい人も秀才も天才も美少女も遊び人も登場していいのかもしれないのだけれど…。物語が面白いだけに、その違和感が余計印象に残ってしまった。
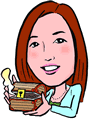
余湖明日香(よご あすか)
2007年10月、書店員から、コーヒーを飲みながら本が読める本屋のバリスタに。
2008年5月、横浜から松本へ。
北村薫、角田光代、山本文緒、中島京子、中島たい子など日常生活と気持ちの変化の描写がすてきな作家が好き。
ジョージ朝倉、くらもちふさこ、おかざき真理など少女漫画も愛しています。
最近小説の中にコーヒーやコーヒー屋が出てくるとついつい気になってしまいます。
好きな本屋は大阪のSTANDARD BOOKSTORE。ヴィレッジヴァンガードルミネ横浜店。
松本市に転勤のため引っ越してきましたが、すてきな本屋とカフェがないのが悩み。
自転車に乗って色々探索中ですが、よい本屋情報求む!
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年7月 >余湖明日香の書評