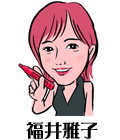WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年7月 >『デカルトの密室』 瀬名秀明 (著)
評価:![]()
「犬が人を噛んでもニュースにならない。でも、人が犬を噛んだらニュースになる。」ということわざがある。ではこの関係を、人とロボットに置き換えてみると、こうなる。「人がロボットを壊してもニュースにならない。でも、ロボットが人を殺したらニュースになる。」だから、マイケル・クライトンの小説を原作とした『ウェスト・ワールド』や、ウィル・スミス主演の『アイ、ロボット』など、ロボットの殺人は映画などで取り上げられてきた。最も有名なのが、スタンリー・キューブリック監督作『2001年宇宙の旅』だろう。ロボットの殺人を取り上げた本作にも、『2001年〜』は登場する。世界的な人工知能コンテストに参加するためメルボルンを訪れていた尾形祐輔は、プログラム開発者の中に、10年前に亡くなった天才科学者・フランシーヌ・オハラという名前を発見する。そして何者かに拉致された祐輔を救うため、ロボットのケンイチは、フランシーヌを射殺する。だがこの事件には裏があって…というミステリータッチのSF。複数の「ぼく」が語り手を務めることで、読者はいくつもの視点から、何度も物語を見直さなければならない。かなり頭を使うし、論理的なことも出てくるので、軽くは読めない。
評価:![]()
「チューリング・テスト」や「フレーム問題」など、人工知能の分野での専門用語が飛び交う本作ですが、物語の中でちゃんと説明が入れられているので、用語に対して戸惑うことはありません、しかし、作品中での議論の内容がちょっと難しく感じました。明確な答えが最後には得られるのだと思い、頑張って読んだのですが、結論も私の頭ではやはりよくわからないのでした。それでも、話は「人間や機械にとっての〈私〉とは何か」といった興味深い内容なので、わからないまでも惹きつけられるのです。
本作は謎解きがメインではなく、脳に閉じ込められた自己意識(これがタイトルの意味するところです)のことがテーマです。哲学書はいつも途中で読めなくなるのですが、デカルトを読めば、本作に対する理解度も上がるのでしょうか。
完璧に理解しようとすると難しいですが、ロボットのケンイチの言動にうるっときたり、驚きの展開など、単純に楽しめる小説でもありました。
評価:![]()
ロボットが登場する話は数限りなく書かれてきました。ほほえましかったり、恐ろしかったり、教訓を与えてくれたり。未来の夢物語は、おぼろげでも、希望がいっぱいでもいいけれど、共存の現実味を帯びてくるほど不安もまたある。そこに着目したのが瀬名秀明というのがいい。
さて、ヒト型ロボットのケンイチとロボット工学者の祐輔、進化心理学者の玲奈は、参加した人工知能コンテストで事件に巻き込まれる。人間とロボットとの境界とは何か、人間らしさとは何かを問いかけてくる。
はっきりいって、ある程度の知識がないとこの本を読むのはつらい。デカルトの「方法序説」、ちゃんと読んだことある人はどれほどいるだろう。飛び交う会話は、右から左と抜けていった。だから、奥山友美のような存在が、ついていけない読者の手を引いてくれるのはありがたかった。
読みこなすには難しすぎるという印象がある。でも、ケンイチたちのゆるぎない結びつきが暖かな気持ちにしてくれた。
評価:![]()
手ごわい本だった。謎めいた殺人事件が起きるけれど、エンターテインメント系のミステリとはちょっと違う。ロボットや人口知能が話題の中心にありながら、SFとも言い切れない。『デカルトの密室』というタイトルでもわかる通り、ストーリーの発想は哲学的。まさに作家であり研究者である瀬名秀明だからこその作品だ。
科学と哲学が好きである程度のレベルの知識がある人だったら、評価は五つ星なのかもしれない。読んでいて、面白さと深さの片鱗を確かに感じる。でも残念なことに、自分の知識と思考力が追いつけない! きちんと理解して読んだつもりでも、読み終えてみると半分しか理解していないような気がする。レベルが高くていい本だとは思う。でも、エンターテインメント系ミステリを期待して手に取った読者の大半が、途中で置いていかれてしまいそう……。
評価:![]()
高性能な人型ロボットが実用化された社会で、2組のロボット学者とそのロボットの対決が始まるかのような序盤。いかに人工知能が人間らしい受け答えを出来るかを競う大会で事件は起こり、「人間と機械の違いは何か」を読者に投げかけてくる。そう、この小説は全編を通して、主人公が悩み考えると同時に読者にも同じことを要求する。小説というより科学や哲学の講義の勉強をしているような気になる。最初は途中から用語や理論に頭がパンク、手に負えなくなったので、新潮社のホームページにあった瀬名秀明さんの「デカルトの密室 特別講義」を参考にしながら読み進めた。が、しかし、行きつ戻りつしながら丁寧に読み進めたけれど、自分がそれを全て理解できている自信はない…。
プロローグからもわかるように、『2001年宇宙の旅』とチェスが物語の重要な鍵となる。大学の認知心理学の時間に読んだシュテファン・ツヴァイク著『チェスの話』を思い出した。軍隊に全く何もない部屋に監禁された男は、偶然手に入れたチェスの本を繰り返し読み、暗記し自分の頭の中で繰り返し繰り返しチェスの対局を行うというものだ。
密室・チェス・心。このキーワードにぴんと来た方はぜひこちらもお勧めだ。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年7月 >『デカルトの密室』 瀬名秀明 (著)