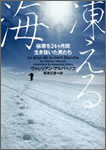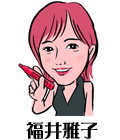WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年7月 >『凍える海 極寒を24ヶ月間生き抜いた男たち』 ヴァレリアン・アルバーノフ (著)
評価:![]()
海の中の綺麗な魚達が泳ぐのは見たい。でも、深く潜れば潜るほど圧力がかかる中で、流されずに動かなきゃならないダイビングは怖い。水は生命の源だが、反面、恐ろしい力で生命を奪ってゆく。優しさと、厳しさを併せ持つ水。でも、水に限らず、自然はその両面を持っている。それでも、人間は、厳しい自然に挑まずにはいられない。本書の著者、アルバーノフも、そんな自然に挑戦した一人である。1912年8月28日、聖アンナ号は23名の乗組員を乗せ、ロシア・サンクトぺテルブルクを出航した。過去一度しか成し遂げられていない、北東航路横断を行うためだ。しかし出発から2ヶ月たらずで、船は浮氷に閉じ込められてしまう。こうした状況に置かれた集団にお定まりの如く、内部で対立が起きる。航海士アルバーノフは、残留を主張する船長と決別し、脱出計画を実行に移す。「この足の下にもう一度硬い大地を感じられたら、それだけで私はどれほどしあわせだろう。(p71)」という言葉は実感がこもっていて、つい頷いてしまった。救いのロシア船を見つけたのに、第一次世界大戦の勃発により、敵船と間違われてしまう。そんな笑えない実話をはじめ、「これドラマにすると面白い」と思わせるエピソードがいっぱいだ。
評価:![]()
漂流記というものは、基本的には生還してこそ世に出るわけです。ですから、漂流記を読んでいて思うのは、何百何千万人もの生還出来なかった漂流者たちのこと。同じような遭難状況で、一方は生還して自分たちの体験を世に伝え、一方は「行方不明」という言葉でくくられて忘れ去られてしまう。両者の間にあるのは「死」という絶対的な壁。人知れず、どこかで生き残っている人もいるかも知れませんが、生還出来ない人がほとんど死んでいると考えると、私にとっては読んでいて恐怖を感じずにはいられないジャンルなのです。
本作は、氷に閉じ込められ身動きのとれなくなった船から脱出し生還した、航海士アルバーノフの日記を元に書かれています。自然の前に人間の力などあまりにも無力であることを痛感します。しかし、無力であるにもかかわらず、生き残るために自然に立ち向かう人々。読みはじめには絶対に無理と思われた脱出劇の成功は、私たちに生きる勇気を与えてくれるような気がします。
評価:![]()
冒険譚やサバイバル記のおもしろさというのは、自然の中での困難を乗り越えて「生き残った」という記憶を、居ながらにして追体験できるところだ。だから、過酷であればあるほどおもしろかったりする。
いまから96年前の1912年、北東航路横断を目指したロシアの聖アンナ号の乗組員たちは、出航から2ヶ月でカラ海の氷に閉じ込められてしまう。航海士アルバーノフと同士たちは、北極からの脱出のため悲壮な決意で船を離れた。けれど、脱出の旅は想像を絶する運命が待ち受けていた。
どんなにつらくても、助かる見込みがあればやっていけるだろう。けれど、足下は動き続ける氷河で、正しい地図もなし、計器もなし。その上、食料もどんどん減っていくという、いったい何重苦なんだ。アルバーノフが強い意志を維持し続けられているのが本当に不思議で、困難に立ち向かう姿は本当にすばらしかった。手に汗握って彼らの動向を見守りました。とにかく、間違っても、寒いところと海の上では遭難したくないと思いました。
評価:![]()
北極海で氷漬けになった船から橇を引いて徒歩で脱出した11人のサバイバルの記録なのだが、薄めの本ながらものすごい迫力である。これぞまさに「真実」の力。フィクションにはない、湧き上がるようなエネルギーがぐいぐいと迫ってくる。
乏しい食料、仲間同士のいさかい、歩いても歩いても氷盤ごと北に押し戻されてしまうもどかしさ、陸地が見えてこない不安、そして究極の寒さ……。どれをとっても想像しただけで気が狂いそうになる。結局著者は苦難の末に見事生還を果たすのだが、極限状態をサバイバルするには、強靭な肉体と強い精神力、勇気、冷静さ、賢さ、忍耐力などをバランスよく兼ね備えていないといけないということを思い知らされる本である。
断片的な日記と記憶を元にして作家ではない人間が書いた本だから、文章は決してうまくはないのだが、淡々と簡潔な文章はむしろ想像力をかきたてる。とにかく、圧倒的な「事実の迫力」の前に脱帽!
評価:![]()
まず、北極の氷に閉じ込められた船が1年半漂流しているところから始まるというのが驚き。それだけでもう一冊の本になるのではないかと思う。
だけどこの作品は、そこから11人の乗組員達が、助けが来るのを待って船に残ることを主張する仲間に別れを告げて、自力で助けを求めて旅立とうとそりを手作りするところから始まるのだ!!
わずかに残ったノートを元にこの作品を書き上げたアルバーノフの、生きる力に胸を打たれる。一日わずか数キロの距離を南進しては、進んでいる氷ごと北に押し流される。それでも彼は絶望せず、仲間をはげまし、なだめすかしながら着実に進む。生命を脅かすものは天候・野生動物・少なくなる燃料と食料・おぼつかない進路・慢性的な疲労・くじけそうになる心など数限りなくあるというのに。そんな中でも私が一番はらはらしたのが、仲間から裏切り者が出て、貴重なショットガンや食べ物を持ち逃げされたところだった。(そしてこの裏切り者の名前を最後まで明かさないところが、アルバーノフのもっとも男らしいところだと思う)
船に残ったメンバー、アルバーノフに同行したものたち、裏切り者達はどうなったのか、アルバーノフはどのように生還したのか、ぜひ読んで確かめていただきたい。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年7月 >『凍える海 極寒を24ヶ月間生き抜いた男たち』 ヴァレリアン・アルバーノフ (著)