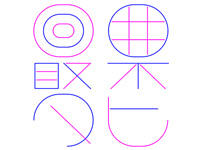
作家の読書道 第207回:最果タヒさん
学生時代に詩人としてデビューを果たし、今は詩だけでなくエッセイ、小説などフィールドを広げて活動している最果タヒさん。詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』が映画化されるなど常に注目され、とりわけ若い世代から圧倒的な支持を得るその感性と言葉のセンスの背景に、どんな本との出合いや創作のきっかけがあったのでしょうか。
その2「中1でネットを始める」 (2/6)
――では中学生になってからも、漫画が中心でしたか。
最果:中学に入るとネットを触り始めたので、萩尾望都さんのような、いろんな人が薦める名作や、小学生の視線だと見つからないものがたくさん見つかって、それらを読むようになりました。中学時代に、音楽にも出合ったんです。その頃の出合った本や音楽って、毎日を楽しく過ごすために読んだり聴いたりするものというよりは、むしろものすごく体力を使って接するものとして、夢中になっていました。
――その頃出合った音楽は、どんなものだったのですか。
最果:BLANKY JET CITYとかナンバーガール、ゆらゆら帝国。あとはっぴいえんどとか。日本語の歌詞で歌っている人たちなんですけれど、わかりやすいメッセージを歌っているバンドではないんです。何を言いたいのか分からない、という人もたぶんいるんだろうなと思います。バイト先か何かのお姉さんにその頃好きだった音楽をMDにまとめて貸したことがあって、そしたら「意味が分からなさ過ぎて、車運転している時に聴いたら事故りかけた」って言われましたから(笑)。確かに分かりやすいことは何も言っていないんですけれど、でも、なんか分かっちゃうみたいな。なんだろう、考えるより先に分かっちゃう感じっていうのがすごくある歌詞が多くて、それが私の中ですごくしっくりきたというか。そこがかっこいいと思ったんです。
もともと、説明するためだけの文章を読むのが好きじゃなかったんです。漫画が好きだったのも、そういう部分を言葉にしないからだったと思います。モノローグだけ入ってて、説明はないけれどなんか繋がりが分かってしまう、みたいなものがすごく好きでした。音楽の中でもそういうものがあると気づいた時に、言葉を書くっていうのがすごくかっこいいことに思えたんです。
――それまで書くことに興味はなかったのですか。
最果:小さい頃から言葉を書くのは好きだったんですけれど、作文を書くのは嫌でした。「ここの部分を分かりやすく書きなさい」って言われたり、「この時はどう思ったのか書きなさい」って言われたりして、書きたくないことを書かされるイメージがありました。それが苦手で好きじゃなかったんですけれど、歌詞を読んだら「あ、こういうのでいいんだ」って思えたんです。それまでは、自分の気持ちを他人に教えるために書くことがすごく気持ち悪かったんです。なんで教えなきゃいけないのかって。気持ちって教えるものじゃないのにって。でも、歌詞を見ていたら、「あ、やっぱり教えなくていいんだ、教えなくても見た人や聴いた人が『あ、来た』となる瞬間があるんだ」って思いました。
当時、ブログをやっていたのですが、そのころから、無理に「伝えよう」としない、ただ書きたい言葉を書く、というふうに変わりました。そうしたら「詩みたいだね」って見た人に言われるようになったんです。そこから、詩の投稿サイトに参加するようになって、「『現代詩手帖』に投稿すれば」って言われるようになりました。私は『現代詩手帖』ってなんじゃらほい、という感じでしたが親は知っていて、「詩とか書くなら『現代詩手帖』に載るぐらい、極めなさいよ」って。「何を言うんだ」と思いましたが、それよりまず「詩ってなんや」と思って本屋さんの詩の棚に行って、本をたくさん手に取りました。それが高校生の時です。
――歌詞に触発されて文章を書き始めたけれど、詩ではなかった、ということですか。そもそも「詩」というものを認識されていなかったんですね。
最果:そうですね。教科書などで詩を読んで「面白いな」と思ったりはしていたんです。教科書で文章を読むのはすごく好きで。中原中也とか谷川俊太郎とか好きだったし、太宰治とか夏目漱石とかも好きで、そこから本で読んだりもしていたんですけれど。熱心に吸収しようと思って自分から本を探して、浴びるように読もうとしたのは、詩を知ろうとしたあたりが久しぶりでした。
――探して見つけた本というのは、詩集とか?
最果:その時に見つけたのは吉増剛造さんと田村隆一さんの本だったかな。とにかく「めっちゃかっこいいやんけ」と思いました。私が歌詞でかっこいいと思うのは、1行目と2行目の間で意味が断絶していて、なんでこの2行目が来るのかわからない、でも、わかる、意味よりも早く、胸にどんときてしまう、みたいなものなんですが、田村隆一さんの詩は、その断絶が研ぎ澄まされて、詩そのものが断絶としてそこにある、感じがするんです、「腐刻画」とか最高です。すごく好きでした。読んで、「田村隆一さんみたいな作品を書きたい!」って強く思ったんですけれど、同時に「なれないな」ともわかりました。自分にないものに強く憧れている感覚でした。
吉増剛造さんも「燃える」っていう作品がすごくかっこよくて。言葉が、言葉であることを忘れさせるほどのスピードを持っているんです。意味なんていい、解釈なんていい、早く次の言葉が読みたい、と目がぐんぐん動く感じ。スピード感があって、言葉の理解を超えたところで突き刺さるものがあって。かっこいい、としか言いようがない詩です。
でも、みんなあまりにも違っていて、結局、詩は何なのかと思って詩の棚に行ったのに、「詩は......分からん」としか思えなかった。わからん、でもかっこいい、それだけがわかる、って感じでした。だから、書きたいように書くしかないんだな、と思って。
これまで何度も行っていた本屋さんに、こんなカッコよくて、やばいものがあったんだ、ということを知れたのはすごく嬉しかったです。そこから一気に本嫌いが治るというか、苦手意識がなくなるというか。読むより先に感じ取るみたいなことがオーケーだと思えてほっとしました。
――ところで、ネットに文章を書き始めたのが中学生の頃からってことですよね。まわりの中学生もやっていました?
最果:私は中1くらいの時にネットを見始めたんですが、周りはまだやっていなくて。当時はテキストサイトが全盛期で、画像はアップすると時間がかかるからあまりやっている人はいないという状態でした。
感想を言い合う場所もそんなにないから、みんな一方通行で書いているんですよ。もちろん、訪問者の数は出るんですけれど。みんな言うことが勝手で無茶苦茶で、その空気がいいなあ、楽しそうだなあと思ったのを憶えています。聞く人に対して親切に説明しなくてもいい感じっていうか。やっぱり中学になると、みんなと話していると空気を読んで、その場で求められることを言うということが何度もあって嫌だったんですけれど、ネットを見て、そういうのがない世界だなと思いました。それで、自分もやってみたくなったんです。
その時は、日記サイトをレンタルして書けるみたいな場所で書き始めたんですけれど、でも当時って面白い人しか発信してない空気がありました。面白いか、すごく本を読んでいるとか、すごく変な趣味を持っているとか。そういう特殊な人だけが書いていて、他のみんなはそれを見に行くという状況だったから、ただの中学生が書いた日記なんて何も面白くないだろうとは思いました。だから、日常とかは書かないで、頭の中身をそのまま書くしかないな、って思ったんです。思いついたまま1行目をさっと書いて、そのまま流れで考えるよりも先に書き終わったらオッケー、みたいな感覚だったと思います。
――思考が追いつくまでに書き終える......。
最果:言葉自体にリズムや勢いがあって、だから、意味なんて意識しなくても、そのリズムで次の言葉が出る、っていうことがあって。音楽のセッションとかと一緒なんだと思います。私はそれがすごく楽しくて、それを味わうために書いていました。だから結果的にできた文が支離滅裂であることも、矛盾しまくっていることもあったと思います。でも、あまり結果は気にしていなくて......。書くって楽しいし、ネットはまだ当時は別世界のようだったし。夢中になっていました。

![現代詩手帖 2019年 06 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41UbAPGpGeL._SL500_._SX160_.jpg)