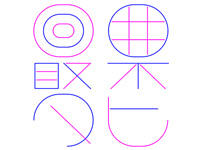
作家の読書道 第207回:最果タヒさん
学生時代に詩人としてデビューを果たし、今は詩だけでなくエッセイ、小説などフィールドを広げて活動している最果タヒさん。詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』が映画化されるなど常に注目され、とりわけ若い世代から圧倒的な支持を得るその感性と言葉のセンスの背景に、どんな本との出合いや創作のきっかけがあったのでしょうか。
その5「詩と小説」 (5/6)
――最果さんは詩だけでなく小説をお書きになっていますが、そのきっかけは何だったんですか。
最果:小さい頃から、お話を書くのは好きだったんです。絵本を読んでいた頃、落書き帳にいっぱい文章を書いていたし、中学や高校の頃も時々書いていたんですよ。その後やっぱり「詩のほうが楽しいかも」と思って書かなくなっちゃったんですけれど。でも、詩集を出してから、編集者さんに「小説を書きませんか」とちらほら言われるようになり、それで書くようになりました。中也賞を獲った後くらいに「群像」さんに小説を書いた時は、あまり詩と小説を区別せず、長い詩を書く感覚で書いていたと思います。詩は読み手に委ねる部分がすごく多いので、自分がこっちのつもりでも読み手があっちにいっていることもあるので、小説として話の筋が分かるよう、ちょっとだけ標識みたいなのをつけて、詩よりは長いものを書いたんです。それが短篇「スパークした」で、大森望さんが2009年の『年刊日本SF傑作選』に入れてくださって、それで大森さんが編者のSFアンソロジー『NOVA』でも書かないかと言われて書いたりして。
――SFは好きだったのですか。
最果:好きでした。大学時代にクラークの『幼年期の終り』が好きになり、SFを読むようになりました。気持ちを伝えるということと関係のない文章がいっぱいなところが良かった。SF的事実を伝える文章って無機質で落ち着くんです。オーソドックスな作品が好きですね。宇宙人がやってくる、みたいな(笑)。クラークの場合は文章がレポートのようで、ここまで徹底して平熱になれるのもすごいなって思って、好きでした。詩を書いていると、「それがあなたの気持ちなんだね」って受け取られることが多くて、それがすごく気持ち悪かったんです。自分の気持ちじゃないのに。
それでSFを読むようになったらSFを書かないかというお話が来てしまい、好きだからこそ恐るというか、「今までの書き方じゃあかんやろ」と思い、それで、お話を考えてから書く、ということをやりました。でもその時もマイペースに「この文章が書きたいからこうする」みたいな書き方もしていました。
それから『死んでしまう系のぼくらに』という詩集を出した後、筑摩書房の編集さんに、「この横書きの感じで小説書きましょう」って言われて。横書きにするならその理由が要るなと思い、手紙ってことにして『星か獣になる季節』を書きました。その時は焦りがなくて、バーッと詩のままに書けたような気がします。その後もいろいろと...。でも、なんだろう、小説って何、っていうところから考えなきゃいけないのが小説家でない自分の哀しいところなのかなあ、とは時々思います。いや、小説家の人も「小説って何」と考えているとは思うんですけど......。どうしても、詩と比較して小説を捉えようとしてしまうのがもどかしいです。ジャンルに境界線はないし、つながっているところもあるんですが、でも、詩のままで小説を書くのは難しくて、それがすごく不自由に思うこともある。でも、そこが振り切れたときって、書いていて、すごく新鮮な面白さがあって。そういうこともあるから、書いていきたいなとは思います。
――先ほど、無機質で平熱のクラークの文章を好きだということでしたが、ご自身ではどういう文章を書きたいですか。
最果: 平熱といえば、「文藝」で柴田元幸さんが海外の名作の冒頭だけ翻訳するという連載をしていて、A・A・ミルンの『くまのプーさん』を訳していたんです。それで改めて読み返してみて、プーさん、すごいなと思いました。二文に一個サービス精神が入っている(笑)。クラークとプーさんは方向性は違うんですけれど、言葉に対する態度が一緒なんですよね。目的に対する実直な感じがすごく好きで。完全に言葉をコントロールしていて、たぶんそれが通常の何倍も言葉のパワーを出している感じがして、格好いいなって思うんです。「プロの仕事だ!」って思って、興奮するんです。自分にないタイプだから憧れるというのもあります。平熱の文章って、簡単に言うとすごく手抜きに見える。そこにコクを出そうとすると、その人の心理が出てきて、むしろべたついてくる。そうじゃなくて、骨太なままでポンって行くところが格好いいなって、痺れた憶えがあります。クラークとプーさんは大学時代、すごく重要な心の2冊でした。今思い出しました。
だから、クラークみたいな物語をプーさんみたいな文章で書けるようになりたいって思っていて。それは無理なんですけれど。自分が書く言葉で、まず自分が楽しもうと思っている時点でそれは難しいんですけれど。






