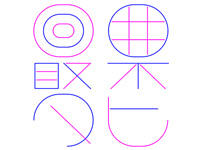
作家の読書道 第207回:最果タヒさん
学生時代に詩人としてデビューを果たし、今は詩だけでなくエッセイ、小説などフィールドを広げて活動している最果タヒさん。詩集『夜空はいつでも最高密度の青色だ』が映画化されるなど常に注目され、とりわけ若い世代から圧倒的な支持を得るその感性と言葉のセンスの背景に、どんな本との出合いや創作のきっかけがあったのでしょうか。
その4「詩を人に読まれるということ」 (4/6)
――大学時代、詩の投稿はされていたのでしょうか。
最果:雑誌への詩の投稿は、勧められてから1年くらい経ってから始めました。それまではネットでずっと投稿していて、その後雑誌に投稿して、1年後くらいに現代詩手帖賞をもらって、その1年後に本(『グッドモーニング』)を出して、中原中也賞をもらった、という流れでした。それから数年後に「別冊少年マガジン」で漫画家の人たちとコラボするという連載が始まったんです。
――『空が分裂する』ですね。最果さんの詩に、漫画家たちがイラストをつけている。
最果:それまでは結構、自分でも何を書いているか分からない状態で書くのを良しとしていたところがあったんですけれど、それだとなぜ自分は発表しているのか分からない感覚になることもあったんです。リアクションもないから、誰も読んでいないという感覚になることも結構あって。というか、自分が読まれたいのかどうかもわからなかった。でも、漫画雑誌にコラボが載るとなると、どうしても読者を意識するじゃないですか。読者のイメージがはっきりあるし、この漫画を読んでいる人がこの流れで自分の詩も読むんだって思うと、今度は読む人の目をすごく意識するようになって、そうしたらすごく言葉が出やすくなったんです。今まではなんで自分が一人で書かずにネットに書くほうが楽しいのかよく分からなかったんですけれど、そこで、自分にとって言葉は、自分の中の心情を吐露するために書くものというよりは、人と人の間にあるものを揺れ動かして相手の何かを動かすものであるんだとはっきりしました。やっぱり読む人がいないと書けないんだなって、はっきり分かったんです。
私が吉増さんや田村さんや谷川さんの詩を読んで「かっこいい」と思ったのって、別に詩人たちが書こうとしたことを受け取ったらから「すごい」と思ったんじゃなくて、それを読んだことで私の中にあるものが「ぐっ」となって反応したから「すごい」って思ったわけなんですよね。結局、詩を書いて誰かに渡すのが詩人というよりは、読んだ人を詩にしちゃうのが詩人なのかなってすごく思ったんです。その感覚がはっきりしたので、それからは書きやすくなりました。格好いいことを書こうとかいうような意識は要らないけれど、「読まれる」という感覚で言葉を書くとそうなるんだな、と分かりました。
――大学中に第1詩集の『グッドモーニング』を刊行し、それが中原中也賞を受賞したりというのはすごいことだと思うんですが、今、デビュー前後の時期についてさらーっと駆け足で語りましたね(笑)。
最果:ああ、いえ、ちゃんとめっちゃ嬉しかったですよ (笑)。でもその前に投稿欄で現代詩手帖賞をもらった時がいちばん、心臓にきたかもしれないです。1年間投稿した人の中から選ばれるので、「候補になりました」という連絡もないし、もらえなかったらまた1年同じ投稿を続けるんだと思うとしんどくて、「獲りたいな」って気持ちもあったけれど、なるようにしかならないっていう感覚も強かったような気もします。あんまり憶えていない(笑)。
やっぱり、本が読まれるって奇跡的なこと。本が出てもそれが本当に読まれるかという不安はありました。でもいちばん憶えているのは、池袋のジュンク堂書店さんで、私の詩集にPOPが付いていたっていうのを、読者の皆さんが教えてくれたこと。すごく嬉しかったのを憶えています。それまではネットに書いて5、6人が「良かったよ」「前のほうが良かった」とかいう感想を上げてくれたり、時々知らない人が私のことを何か書いているのを見ることはあったんですけれど、それくらいの数しかいないのではという不安があったのが、急に、自分の知らないところで窓が開いているみたいな感じがありました。「別冊少年マガジン」の編集さんも、そこで私の本を見つけてなんとなく手に取って読んで、「よっしゃ連載させよう」って思ったんだそうです。本が出たことよりも、本が出たきっかけでいろんな人が現れたことが私の中ですごくインパクトが強かったです。
――では、大勢の人に読まれるというプレッシャーはなかったのですか。
最果:結果を出さなきゃ、っていうプレッシャーよりは、「載っていいの? 本当に? 大丈夫?」みたいな怯え方をしていたと思います。その後、ネットでもおそるおそる詩を投稿してみたら、想像していたよりずっと反応があって「えっ、ええっ?!」とそのときもすごくビビっていました。
読む人を舐めていたんだなとも思いました。どうせわからないって思っていたのは、すごくアホらしいというか、馬鹿みたいなことで。自分が詩とか歌詞とか見た時に感じた、書いた人が何を書こうとしているか分からないけれど来ちゃうものがあるという感覚はいろんな人の中にあって、だからこうやって詩集がいっぱい売られたりとか、世の中にいろんな不思議な歌詞があったりするんだな、って。そこがすごく面白いって思ったんですよね。世の中いろんな人がいっぱいいるんだなっていうのをすごく知ったというか。だから、読まれているっていうのを意識すると、むしろ逆にすごく自由を感じます。読む人を信じることが一番、真っ白になる方法なんだなって思うと、半信半疑になっていた時よりも、好きに書けるようになりました。それがすごくいい経験でした。
――ペンネームはいつ決めたのですか?
最果:高校生の時に、詩の投稿サイトに投稿するために作りました。最初は、ひらがなで「たひ」だけで。その時にちょうど「言って気持ちいい言葉」を考えていて、「たひ」って抜けていて面白いじゃんって思っていたので、それを名前にしたんです。その投稿サイトは掲示板みたいな感じだったので、ひらがな2文字でよかったんですけれど、その後、別のサイトに投稿する時に、結構みんなフルネーム感のあるペンネームだったので、それで苗字を考えて、「たひ」だったら苗字は4文字かなって、なんとなく「さいはて」ってしたら漢字変換で「最果」って出て、「あ、ケバい」って思ったけれど(笑)、何回かしか使わないつもりだったので、とりあえずそれにしました。それに合わせてカタカナのほうが字面がきれいだから「タヒ」にしたというのが本当なんです。そのころは検索したら、「タヒ」ってモンゴルの馬しかでてこなくて。
でも、すごく疑われるんです。このあと、ネット上でスラングとして「タヒ」がじわじわ使われるようになってしまって。今ではそれが由来に違いないってよく言われてしまいます。否定しても嘘だって言われるし、どうしたらええんや......という気持ちです。言葉はほんと、何があるか分からないですよね......、何が後々流行るか分からない。今はタピオカブームなので「タピる」って言うらしいし(笑)。


