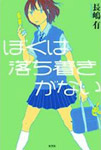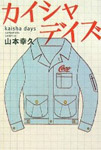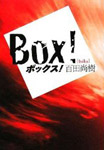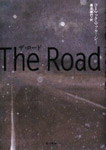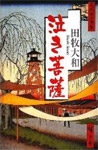WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年8月の課題図書 >佐々木克雄の書評
『ぼくは落ち着きがない』
評価:![]()
今頃になって気がついたんですけど、所謂「青春モノ」を読む時の基準値って、読み手の青春を「軸」にしていて、それでツボに入るモノがあるか否かではと。
そういう意味で、地方高校の図書部員たちの一年を描いた本作は、正直なところ自分の「軸」にはかすりもしなかったのですが、何故だか彼・彼女たちが気になるんです。(そもそも図書部なる部活の存在を知らなかったし、ましてや文芸部との確執なんて)たぶん、彼・彼女たちの描き方なのかなと思うのですよ。この手の作品って往々にして主人公の目線で話が進んで、成長していくてな展開が多いのですが、本作は部室の片隅に隠しカメラが据えられているような感じで彼らを淡々と描き、各々の感情が呈されていない。だからこそ、妙なリアルが浮かび上がってくるようでして──これは著者である長嶋さんならではの巧さなのでしょう。
余談ですが、作中にでてくる電グルの本、自分も大好きです。
『カイシャデイズ』
評価:![]()
当世、働く人々を描かせたら山本幸久はピカイチだ。
会社なるものを舞台に例えると、社員は役者となってドラマを繰り広げることになる。しかも利益を追求する集合体だから、各々のエゴイズムが縦横無尽に駆け抜ける。経済小説だったら専門用語が飛び交って、アクの強い人々のぶつかり合いに息を飲むだろう。
でも、山本幸久のカイシャは、どことなく「のほほん」としていて笑えるのだ。もちろん、内装会社にいる人々は一癖も二癖もあって、衝突することしばしば。けれど悪人は一人もいない。誰もが「コンチキショー」ともがき、耐えて、成長を見せてくれる。こんな会社で、こんな人たちに囲まれて仕事がしたいなあと思ったりして。
著者自身が内装会社に勤務していたバックボーンがあったと思うが、サラリーマン経験のある人なら作中に「自分」や「知ってる人」がいるはず。それを探すのも楽しいっすよ。
『ボックス!』
評価:![]()
ぶ厚くて、熱い全585ページの中には、高校ボクシング部の汗と涙と青春がギュウウウ〜ッと詰まっております。まずは、ここまで綿密に描ききった作り手側の熱意にプラスのポイントを差し上げたい。きっと世の中的には「あの小説のボクシング版でしょ?」てな比較をされてしまうかも知れないが、声を大にして言いたい。「いろんな青春があって当然でしょうが、スプリンターでもボクサーでも、何かにひたむきになってる姿は美しいのだあ!」
ひとりで勝手に熱くなってしまいスンマソン。ともかくこの小説には中途半端な文化系だった自分を揺り動かすモノがあったことは確か。天才少年と、最初はひ弱だったエリート君と、彼らを見守る顧問の女性教師──お互いの思いが螺旋状に絡み合って昇華していくてなプロセスは(ドラマティック過ぎる部分もあるが)読み手の心を鷲掴みにしてくれます。
「努力・友情・勝利」──そんな言葉をたまには肯定したくなるもんです。
『さよなら渓谷』
評価:![]()
かなりの依怙贔屓があることを自覚してはいるが、吉田修一は当代もっとも小説らしい小説を書く作家だと思う。でもってその小説はというと、もはや小説の域を突き抜けてしまっているとも思える。とみに昨年の『悪人』、そして本作は、実のところ簡単には評しがたい。
新聞紙面を埋め尽くす夥しい事件の裏側には、当然ながら当事者たちの履歴があり、さらには彼・彼女らに関わる人々も存在する。角度を変え当事者たちの過去を遡ることで、深遠な「個の履歴」が露わになっていく。被害者の傷、加害者の贖罪、そして彼らを追うマスコミまでもが冷静に、均等に描かれているから、各々の「人間」がグッと浮かび上がってくるのだ。終盤には驚くべき事実が待っており……う〜ん、重たい。この本に対する感情をどう表現していいか未だわからない。
深読みしすぎかなあ? でも、これも吉田作品の傑作のひとつに入るのは確かだ。
『平台がおまちかね』
評価:![]()
タイトルに未知なる言葉や専門用語があるとそそられる。例えば『ホワイトアウト』、『メフェナーボウンのつどう道』、『ボックス!』。で、このタイトルですが、「平台〜」って……(微笑)。出版業界ウラ話要素の強い大崎作品に関係者ファンが多いのも納得できます。
私事、カミングアウトしますと、かつて出版社におりました。主に編集職だったのですが、本を愛する書店営業担当さんたちの奮闘ぶりに感服した経験が多々あります。そんな彼らが主人公に重なるのですが、キョーレツな逆風が吹いている古巣の現状を風の噂で聞く度に、この作品は美化されすぎではなかろうかと思ったりもするのです。
でも、小説は小説として楽しまなきゃソンですからね、はい、楽しませていただきました。結論を言いますと、この作品は好きです。ソフトなミステリ、癖はあるが悪気のないキャラたち、人を見守る優しい視線──その読後感は、真夏に飲む微炭酸飲料のように爽やかなのです。
『ザ・ロード』
評価:![]()
こんな不思議な本に出会ったのは初めてであり、出会えて幸せである。
何かしらの危機的状況におかれた父親と息子が南に進んでいるのだが、ストーリー全体を俯瞰する説明がないのだ。読者は与えられた一字一句から最大限の想像力を働かせ、父子の置かれた状況を思い描くことになる。これがものすごく刺激的な読書だった。どうやら現代文明が破壊され、生き残った人間たちのサバイバル──らしい。
読んでいてヒリヒリするようなSFなのだが、ストーリーそのものより、父子の会話から見えてくるお互いへの愛、生きることへの希望と諦観がジンジン響いてくる。待ち受けるのは悲劇なのか、それとも救いはあるのか……終盤は祈るような面持ちでページをめくっていた。
独特の世界観はなかなか説明しづらいので、興味のある方はご自身の目で確かめていただきたい。ただ、読点が異様に少ないので、正直かなり読みづらいんですけどね。
『前世療法』
評価:![]()
エハラー度の高いウチのカミさんが同時期に同名本(中味は違う)を読んでいて、ちょっと驚いた。「偶然でなく、必然」てな、あのTV番組の言葉を思い出したりして。でも本作は「前世で人を殺した」と訴える少年をめぐるサイコミステリであるからして、科学的な話に転ぶのか、そうでないのか──の葛藤が読み手側についてまわる。でもって途中からは小児性愛者に話が膨らんでいくから、どうにもこうにも主軸の謎解きに集中できなくて……う〜ん。
ドキドキハラハラ具合としては、主人公の弁護士を追い詰める「声」なる存在がドクロベー様を彷彿させる万能ぶりを発揮しており、ズブズブと底に沈んでいくようなダークな展開にはデニス・レヘイン作品ばりの「救いのなさ」を感じるから(展開も何となく似てる)、それなりに引きつけられたのですが……残念ながら自分には合わなかった感じです。
ドイツ人作家の小説を読めた(←ヘッセ以来)という意味では、新鮮な読書でしたけど。
『盆栽マイフェアレディ』 山崎マキコ/幻冬舎
山崎マキコが描く「ダメっぽい女性」が好きだ!
同性が読むと、嫌悪感を覚えるか親近感を覚えるかパッキリと分かれそうな気がするが、ともかく自分はこの「ガムシャラに頑張っているんだけれども、悪あがきっぽく見えてしまう」女性たちが気になってしまう。
さて本作、長瀬繭子(22歳)は大学を卒業して盆栽師の修行中──何じゃこれ、と思う設定だが、さらにお金持ちの愛人として囲われるてな「?!」なお話。このギャップがたまらなく可笑しいのですよ。毎日予算300円の弁当を作っている彼女が高級料亭でもてなされる。土仕事をする爪にネイルアートが施される……などなど。盆栽か、マイフェアレディかで揺れる彼女のグズグズな揺れっぷりがイイ。どうなるかは読んでみてのお楽しみとして、軽快なテンポ、クセのあるキャラたちも楽しい恋愛小説です。
『泣き菩薩』 田牧大和/講談社
私事、ここ数年ほど浮世絵に興味があり、関連本を渉猟しております。北原亞以子『江戸風狂伝』や河治和香『侠風むすめ』『あだ惚れ』に登場する歌川国芳が一番好きなのですが、お馴染みなのは写楽、歌麿、北斎、そしてこの本の主人公、歌川広重でしょうか。
『東海道五十三次』や『名所江戸百景』などで有名なこの絵師が火消同心であったのは事実──なのですが、本作では江戸で起こる放火騒動に若かりし頃の広重が立ち向かうといったミステリ仕立てのストーリー。これがですねえ、もろもろ巧いんですよ。絵師ならではの観察力で謎を解いていく広重やチャキチャキの仲間たち、ホロリとくる人情、江戸の粋……かなりクオリティの高いエンタテインメントに仕上がってます。巷では和田竜が人気ですけど、この方も時代小説の新人さんとして、久々の「大当たり」です。期待値「大」。
これ、シリーズとして続けて欲しいなと。

佐々木克雄(ささき かつお)
好きなジャンルは特になく何でも読みますが、小説を超えた「何か」を与えてくれる 作品が好きです。時間を忘れさせてくれる作品も。好きな作家は三島由紀夫、宮脇俊 三、浅田次郎、吉田修一。最近だと山本幸久、森見登美彦、豊島ミホ。海外の作品は 苦手でしたが、カルロス・ルイス・サフォン『風の影』を読んで考えが変わりました。
10歳で『フランダースの犬』を読んで泣き、20歳で灰谷健次郎『兎の眼』、30歳で南 木佳士『医学生』で泣きました。今年40歳、新たな「泣かせ本」に出会うべく新宿紀伊國屋本店を徘徊しています。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年8月の課題図書 >佐々木克雄の書評