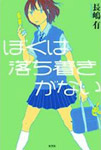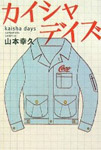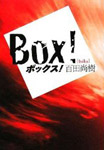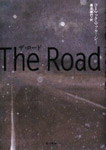WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年8月の課題図書 >下久保玉美の書評
『ぼくは落ち着きがない』
評価:![]()
「落ち着きがない」、読み終わった後いいタイトルだと思いました。高校時代の頃を思い返すと、あの頃の私たちは総じて「落ち着きがない」日々を「落ち着きがない」モヤモヤとした気持ちで過ごしていた。焦りや苛立ち、といった言葉でも表現できるだろうけど「落ち着きがない」といったほうがどうもしっくりくるような気がしてならない。
本書に登場する図書部の面々もまた「落ち着きがない」日々を過ごしている。前半部はユニークな登場人物たち、どことなく弛緩した図書室内の部室の光景、不思議な転校生の登場とドタバタ青春モノといった感じで物語は進行し、ありゃこのままドタバタで終わるのかなと思いきや、それは実は空騒ぎであり、後半部からはどことなくギクシャクとした空気が出てくる。そう、表面を取り繕っているだけで本当は誰もが持って行き場のない苦しさを感じているのですよ。「落ち着きがない」という言葉で空騒ぎであり、焦りであり、苛立ちであり、なんとも言えない苦しさを表しています。この表現ウマいな。
本書を読み終わった後、是非カバーをめくってください。また別の物語が楽しめます。ところであの不思議な転校生は結局どうしちゃったのだろう?それがとても気になります。
『カイシャデイズ』
評価:![]()
ある内装会社に勤める人々をコミカルに描いた短編集。
読んでいてこれほど楽しい本は久しぶりかも。仕事ってこうだよ、というような押し付けがましい人生訓のようなものはなく、ただ「仕事楽しい」と思っている人々、その予備軍を見るのはとても楽しい。中にはおいおい、という上司もおりますがそれも小説を盛り上げるのに一役買っています。
そんな楽しい人々の中で最も好きなのが天才型デザイナー隈元歳蔵。まるで明治時代に活躍した志士のような名前の持ち主ですが、彼のすることはとにかく可笑しい。自腹で大木を買ったり、上司とケンカしたり、「コレをしたい!」という希望のために周囲を巻き込んだり、で女性が苦手。出てくるたびにププッと笑ってしまいます。あと、あげるとすれば大屋時絵女史。「コワいオバサン」と会社中から恐れられているお局様ですが筋の通った仕事をします。
どうか、この内装会社が不況に負けて倒産しないことを切に祈るばかりです。
『ボックス!』
評価:![]()
先日、ボクシングの内藤の試合をテレビで見ました。9Rまで挑戦者有利だったので、内藤も今回で終わりかなと思っていたところ10Rの左フックから始まった反撃、そして右でダウン、防衛成功。ボクシングは恐ろしいスポーツだと改めて実感しました。
本書はそんなプロボクシングの世界ではなく、高校アマチュアの世界を天才的才能を持つ少年とその親友で勉強はできるけどいじめられっ子の少年2人を通して描いています。本書を読んで初めて知りましたがプロとアマチュアでは試合形式や戦術が全然違います。プロの一撃必殺ではなく、どれだけパンチを相手に多く入れたかをポイントで競います。簡単に言えば手数が多ければ勝ち、というもの。しかし、それでもボクシングは恐ろしい。本書には試合が何度も描かれていますが、そこにはポイントを競うということ以上に人間の闘争本能をむき出し闘う男たちの姿が描かれます。
そうしたボクシングの描写だけでなく、少年2人の成長も見逃せない。個人的にはがり勉タイプだった少年が練習を通して変貌していく様子をもっと見ていたいところです。
『さよなら渓谷』
評価:![]()
冒頭を読んだとき、ああこれは自分の子どもを殺してしまった母親の事件をモチーフにした小説なのかなと思いましたが、物語は私の予想をはるかに超えたところに進み、最後は想像以上の哀しさを覚えることになりました。
隣家で殺人事件が起きてしまったため、身辺を探られ秘密を暴き出されたある一組の若い夫婦。この夫婦はある事件から互いに幸せを求めることができなくなってしまった2人であり、不幸になるために一緒にいることを約束した2人です。この2人が抱える事情が物語中で明らかにされていくたびに、2人の抱える闇は一層濃くなっていくように感じ、哀しみを覚えずにいられません。そして世間の無責任さに自分もその一員でありながら憤りを感じます。最後のシーンがこの哀しさのかすかな希望となることを願ってやみません。
『平台がおまちかね』
評価:![]()
出版社営業は地味ながら、というか日頃は全くスポットの当たらない職業ですが出版業界の底辺を支えているんですよ。いくら作家が書いても、編集者がその本をまとめて世に送り出しても、その本を誰かが売らなければいけない。「いい本だから売れる」というのは常々幻想だと感じていて、「いい本」でもそれが埋もれてしまっては売れない。「いい本」であることを伝えないといけないのです。それをしているのが書店員であり、その書店員に販促をかけているのが営業さん。なのに出版の仕事というと編集の仕事と思っている人が多くて…、おっとこれ以上書くと仕事をしていたときの愚痴になりますね。
本書はこの出版社の新人営業マンである青年が営業先の書店や出版社主催のパーティで起きる不思議な事件を解決していく短編集。著者の特徴であるほのぼの、おっとりとした雰囲気が全体を包んでいてファンシーミステリーといった趣です。しかし、そうしたファンシーさの中にも第3話「贈呈式で会いましょう」での新人賞贈呈パーティ時に露呈される人間の持つ暗さを描くなどピリリとしたスパイスも欠かさない、というところがニクいです。ミステリとしてだけでなく出版業界の話も楽しめますよ。
『ザ・ロード』
評価:![]()
おそらく核戦争後、何年か過ぎた世界が舞台の本書。大地は荒廃し、生物もほとんど死に絶え、わずかばかりに生き残った人間が生存のためだけに生きている世界を筆者は淡々とモノクロームの風景を描くように表現しています。しかし、淡々とした描写であるゆえに底知れぬ恐怖を感じます。まさしく世界の終わり。
その世界の終わりをある父子が生き残るために南へ向かって旅をする、という単純極まりないストーリーでありますがその旅で描かれるのは父と子の絆であり、父が子を守ろうとする愛であり、そして子を守るためならばどんなことでもする強さでもあります。生存のためにどんなことでもするのはこの父子にだけではなく、他の生き残った人間たちもまた生存のためにどんなことでもします。本書のページをめくるたびに、どうかこの父子がこうした人間たちに出会わず無事南へとたどり着いて欲しいと思いました。しかし無情にも幾度かそうした人間たちに遭遇し、危険な目に遭ってしまいます。この非情な世界の終わりが描かれる中、唯一の光として存在するのがまだ幼い息子。他者への優しさを失わない彼がこの世界に希望を見出せる唯一の存在であるけれど、多少のじれったさを感じずにはいられないんですよね。
『前世療法』
評価:![]()
スリリングでスピード感あふれるサスペンス。前世治療により、前世で犯した殺人の記憶が蘇った少年が看護師の協力で敏腕弁護士をその殺人の現場に案内する冒頭から不穏な空気が漂い始め、この少年の話通りにその現場から死体が見つかった時から物語が一気に加速し、あれよあれよという間に少年が犯した前世での殺人が次々と暴かれていきます。
この殺人は本当に前世で犯した記憶なのか?という疑問と同時に少年を助ける弁護士の抱える暗闇にも物語は言及するため、複層的な展開を繰り広げられ一層の楽しみを感じました。前世での記憶に関する解答には少々ありゃ?と首をひねる部分もありますが小説全体としては一気に読めてしまいますよ。

下久保玉美(しもくぼ たまみ)
ミステリーが大好きでミステリーを売ろうと思い書店に入ったものの、ひどい腰痛で戦線離脱。今は休養中。とはいえ本を読むのだけはやめられず、黙々と読んでは友人に薦めてます。
好きな作家はなんと言っても伊坂幸太郎さん。文章がすきなんです。最近のミステリー作家の中で注目しているのは福田栄一と東山篤哉。早くブレイクしてもらいたいです。
本という物体が好きなので本屋には基本的にこだわりがありません。大きかろうと小さかろうと本があればいいんです。でも、近所の小さい本屋にはよく行きます。
どうぞよろしくお願いします。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年8月の課題図書 >下久保玉美の書評