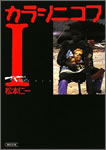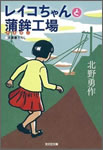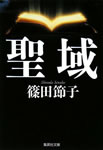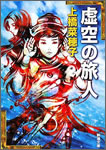WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >余湖明日香の書評
『カラシニコフ(1・2)』
評価:![]()
カラシニコフという名前は何度か耳にしたことはあったが、自分とは関係のない世界に存在するものだと思っていた。戦争や内戦のニュースを見ながら、ある一部の国で起こっていることで、その他の国は概ね平和に毎日が過ぎているのではないかとなんとなく感じていた。
朝日新聞の連載をまとめた本書は、カラシニコフを通して世界を知ることができる。カラシニコフの生まれたいきさつを発明者から聞き取るだけではなく、アフリカや中東の内戦が止まない、犯罪が絶えない国の若者への取材を通してカラシニコフが与えた影響を追う。中南米やアメリカ、中国、アジアで、貨幣の代わりにやり取りされるカラシニコフを追う。
読みながら自分は本当に無知であることを実感してしまった。東西冷戦の影響は朝鮮戦争やベトナム戦争だけでなく、また戦争が終了したからそこで終わりというわけでもない。世界各国の同盟国へ流れた銃は冷戦終結後も残るのだ。扱いやすく壊れにくく手入れのしやすいカラシニコフ。ロシアを救おうと発明されたその銃はその後世界を駆け巡り、多くの若者を兵士やゲリラ兵や犯罪者にし、また多くの人々を死に追いやった。
テレビのニュースではわからない、根の深い世界の貧困や犯罪という問題をカラシニコフを中心に描くことで鋭く切り取った一冊だ。
『ハチミツドロップス』
評価:![]()
うーん、好きだっ!うまいなあ、うまいなあ、と何度もうなりながら読んでしまった。
不真面目でお気楽なソフトボール部のメンバーと、その部長のカズ。練習一筋のバレー部の一年生が、ソフトボール部に揃って入部してきたことから、ソフトボール部(通称ハチミツドロップス)は変化してしまう。ときたら、練習に打ち込み、まじめな部になったのかと思うのだが、そうではない。厳しい一年生の練習についていけず、メンバーは部から離れていってしまう。
ぬるま湯のような居心地のいい空間を失ったカズは、メンバーそれぞれが部から離れて抱えている悩みや問題を見ることになる。それぞれのキャラを守って居心地よく付き合っていくだけでは中学生はやっていけないと気づくのだ。
それぞれの人物の個性や、中学生の生活の描写が、抜群にうまい。私は野球拳(ソフト部の面々が教室で野球拳をしていたらしい)のところで爆笑してしまった。児童文学・ジュブナイルにありがちなステレオタイプの中学生は登場しない。リアルで、読者にこびない。草野たきさん、これからも応援したいなと感じた作家さんだ。
『レイコちゃんと蒲鉾工場』
評価:![]()
蒲鉾工場に勤める甘酢君は、ずるがしこくて自分勝手な豚盛係長やませた小学生レイコちゃんに振り回されてばかり。そんな甘酢君が巻き込まれた事件を書いた連作短編集。
みごとに蒲鉾ばかりが関わってくる、寓話のようなコメディのような都市伝説のような、不思議な短編。私が一番気に入ったのは「消化」という一編。避難訓練の危機感をあおるために暴走してしまった危機管理蒲鉾の調査をしに行く甘酢君と豚盛係長。防護服に守られた豚盛係長と、なんとか防護服の恩恵にあずかりたい甘酢君のやり取りが滑稽。そのシュールさに笑いながら読んでいたら、ただ笑っているだけではいられない奇妙さが、蒲鉾の後ろから現れてくる。
記憶の入れ替えをして代替可能な人型蒲鉾、兵器として戦地に派遣される蒲鉾……。蒲鉾はそのまま人間に置き換えられる。スーパーで蒲鉾を見るのがちょっと怖くなってしまうような、不思議な読後感を残す小説だ。
『聖域』
評価:![]()
雑誌の編集者が、ふとしたことから未完の小説の原稿を手にする。その小説に惹かれた編集者は、小説の結末を追い求め、謎の多い作家の存在を探し始める…。小説と絵画という違いはあるが、今月の課題である『黙の部屋』と同じ展開を持つこの小説だが、ぐいぐいと引き込まれる展開と語りは圧巻。作中で書かれている未完の小説、編集者の運命、謎の作家の正体などが興味を引っ張り続け、一気に読んでしまった。
この謎の作家というのが、民衆信仰が残る村に自ら住み着き、祈祷や巫女などをテーマに作品を書くという。北海道に住んでいるとあまり実感することはなかったが、古い慣習や科学では解決できないことや合理的ではないことは、一昔前までは暮らしの隣にあり、それらと共存していたということを改めて思った。
後半では新興宗教の暗部が出てくるのだが、オウム真理教の一連の事件が起こる前に書かれたというから驚きだ。執筆から14年たった今も、色あせない面白さを持った小説である。
『マイナス・ゼロ』
評価:![]()
昭和20年の疎開先で受けた空襲。お隣に住んでいた学者風の父親はなくなり、ひそかに思いを寄せていた娘さんは行方不明になってしまう。
18年後、その場所を再び訪れた主人公は、タイムマシンに乗ってやってきた、18年前と同じ姿の娘を見つけることになる…。
ところが一風変わっているのが、タイムマシンを手に入れた主人公は、タイムマシンを自在に操って動き回ることができず、逆に振り回されその運命を狂わされてしまう。タイムマシンから取り残され、そこで生活していかなければいけい。じゃあどうやってお金を稼ぐのか。重大事件やスポーツや競馬の結果を知っていることを駆使して大金持ちになるのか。
この物語の主人公浜田俊夫は、派手なことはせずに、人情深い家族のお世話になりながら、務めていた電気会社での知識を使って生活をしていく。一歩一歩町を歩き、その町のことを知りながら、その町の人と暮らしていく。その地に足が着いたなんとも普通の人々たちがいい。それぞれの時代の丁寧な町の描写もや人々の生活も、タイムトラベルを使ったパラドックスも、どちらも楽しめる一級のタイムトラベル小説。
『虚空の旅人』
評価:![]()
「守り人シリーズ」の第4作目。このシリーズは未知なる冒険へのわくわく感、人や歴史、国が変化していく壮大さなど、ファンタジーの魅力が存分に詰まっている。大人も子どもも、男性も女性も楽しめるシリーズだと思う。
シリーズ第4巻だが、この作品から、短槍使いのバルサが主役の物語から、国と国をまたにかけた壮大なシリーズに変わっていく。一応今作だけでも読めると思うが、一巻から読み進めていると、今作主人公チャグムの成長ぶりに胸を打たれる。
シリーズでは全く違う文化を持った国が多く出てくるが、この物語の舞台となるサンガル帝国で興味深いのは、女性の王族によって国が密かに守られ反映してきたというところだ。女だけの集会で各地の情報収集をし、賓客の寝室に隠し通路を設けているという場面でぞくりとした。
アボリジニの研究をしていたという著者。ファンタジーだけれどヒーローはいない、勧善懲悪でもない。マイノリティへの視線、未知のもの、多様性への暖かい視点が、この世界に深みを持たせているように思う。
『黙の部屋』
評価:![]()
偶然に石田黙の作品を手に入れた美術雑誌編集者は、その絵の不思議な魅力と、なかなか正体がつかめない石田黙という人物にとらわれていく。同時に、石田黙の作品世界のような場所で、囚われ絵を描き続ける男のエピソードが重ねられる。
読んでいる私たちも水島と同じように、彼が実際に活躍していた画家なのか正体がつかめず混乱してくる。絵だけこの小説のために書かれた全くのフィクションなのか。囚われているのは石田黙なのか、別の誰かなのか。カラー図版とところどころに挟まれる白黒の写真を見ながら読み進めるうちに、石田黙の作品の虜になっていく。
石田黙の正体を読む前から知っている人はほとんどいないだろう。あとがきと解説を読めばその正体はわかるのだが、石田黙は正真正銘実在していた画家だ。
作者本人も、石田黙の作品に魅せられ、その足跡を追ううちに、ノンフィクションではなくミステリー仕立てにして世に伝えようと考えたらしい。ミステリーとしても美術書としても楽しめる。また画廊の仕組みや競売、ネットオークションなど普段関わることの少ない美術業界を知ることも出来る。ただし絵画の作品世界にあわせた緊張感漂う前半部分に比べて、後半の登場人物の描写や事件の動機や深みなどは今ひとつと感じた。
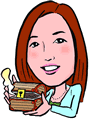
余湖明日香(よご あすか)
2007年10月、書店員から、コーヒーを飲みながら本が読める本屋のバリスタに。
2008年5月、横浜から松本へ。
北村薫、角田光代、山本文緒、中島京子、中島たい子など日常生活と気持ちの変化の描写がすてきな作家が好き。
ジョージ朝倉、くらもちふさこ、おかざき真理など少女漫画も愛しています。
最近小説の中にコーヒーやコーヒー屋が出てくるとついつい気になってしまいます。
好きな本屋は大阪のSTANDARD BOOKSTORE。ヴィレッジヴァンガードルミネ横浜店。
松本市に転勤のため引っ越してきましたが、すてきな本屋とカフェがないのが悩み。
自転車に乗って色々探索中ですが、よい本屋情報求む!
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >余湖明日香の書評