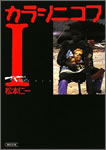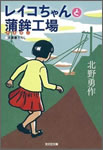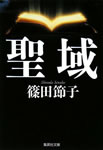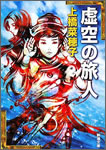WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >福井雅子の書評
『カラシニコフ(1・2)』
評価:![]()
心に残る新聞連載だったため、今回文庫本として再会できて幸せに思う。
扱いが簡単で過酷な環境下でも故障しないことから爆発的に世界中に広がり、ゲリラ紛争や子ども兵士を生み出す一因ともなったと言われる銃、カラシニコフ。その銃を軸にして、銃に翻弄される国家や人びとの姿を描き、国家とは何かを考える。国家としての機能を果たせていない国々と貧困にあえぐ人びと、拉致されて銃を持たされ人殺しをさせられて傷つく子どもたち、権力と金をめぐって争いを繰り返す政府高官やゲリラの幹部、銃と麻薬との密接なつながり──カラシニコフという銃を通して、今日の世界が抱える問題が次から次へと見えてくる。
持論を展開するための取材というよりは、今起きていることの真実を多くの人に伝えようという新聞記者らしい取材姿勢と客観的な視線が、カラシニコフの周りに渦巻く問題を実に効果的に浮かび上がらせている。取材対象やテーマへのぶれのない継続的なアプローチや、読みやすく上手な文章も素晴らしく、どこから見てもノンフィクション作品として最高レベルだと思う。文句なしの五つ星!一人でも多くの人に薦めたい本!!
『ハチミツドロップス』
評価:![]()
お気楽でラクチンな居場所を突然失った女子中学生たちが、もがきながらもそれぞれに精神的自立への一歩を踏み出す物語。
ちょっとデフォルメしすぎのような気はするが、中学生の女の子たちそれぞれのキャラクターが面白く書き分けられていて、なかなか楽しめる。ヤングアダルト小説にはあまりなじみがないのだが、少女マンガかコメディータッチの学園ドラマのような明るく楽しい雰囲気は好感が持てるし、さらっと楽しく読める親しみやすい物語だ。ただ、登場人物の会話や行動が全般的に、中学生というよりは高校生のもののような気がして、気になった。中学生って、本当にこんなふうだったっけ? という違和感が最後まで消えなかった。
『レイコちゃんと蒲鉾工場』
評価:![]()
これはいったい何なのか? 蒲鉾工場に勤める主人公が、怪物化した蒲鉾に同僚が食べられるなどおかしな事件ばかりに巻き込まれる話なのだが、そもそも物語の設定が奇怪で滑稽で、現実と虚構の区別があいまいなのだ。かといって、ファンタジーと呼ぶにはやけに不気味で、滑稽なのにどこか影がさしているような暗さがつきまとう。
だいたい、なぜ蒲鉾なのか?「人間だって、ごちゃ混ぜにしてねりもの(蒲鉾)にしちゃえばみんな同じ。生も死も、現実も妄想も、たいした違いはないんだよ……」という暗喩なのだろうか? とにかく「なんだ、なんだ?」と好奇心をくすぐられて、気づいたら最後まで読んでいた。ちょっと変わったSFのような、ファンタジーのような、不思議な味のある作品だ。少なくとも、「おっ、なんだなんだ? で、このあとどうなるの? これって何か深い意味があるの?」と頭の中にクエスチョンマークを点滅させ、その答えを探しながら読む楽しみが存分に味わえることは確かである。
『聖域』
評価:![]()
主人公の編集者が、たまたま目にした未完の原稿に魅せられて、その作者である水名川泉の消息を追うサスペンス小説。問題の原稿の内容といい、その後明らかになっていく水名川泉の足跡といい、これはもしかして一種独特ともいえる日本人の宗教観に真っ向から挑んだ小説なのか? とページをめくるのももどかしく、一気に読んでしまった。結論は、私としてはややはぐらかされたような気にはなったが、それでも、土着の「神様」を拝み、相談事は巫女に持ち込み、イタコの存在が生活の中に馴染んでいるような、日本の農村などにみられる複雑な宗教感覚を丹念に描き出している。強弱の差こそあれ、この特異な宗教感覚は日本人の多くが持っている(が外国人にはあまり理解されない)感覚ではないかと思うが、これをうまくまとめて小説に描いた著者の勇気と力量に感服する。
また、難解な表現を使わず、とても読みやすいのにぐいぐいと読者をひっぱっていく力のある文章には感心した。
『マイナス・ゼロ』
評価:![]()
私はタイムトラベルものと呼ばれるSFが苦手である。「タイムマシンで20年前に行って過去を変えてしまったら、その人の人生が変わってしまって、だからタイムマシンは作られないことになって……」とか、「過去の自分が殺されてしまったら今の自分は存在しないことになって……」とか、変わってしまった過去が及ぼす影響をたどっていくと矛盾だらけでわけがわからなくなるからだ。だから、タイムトラベルものの映画や本は、終わった後でも「何かがおかしい」という感覚がいつも残ってしまい、どうもすっきりしない。
しかし、この作品に関しては、過去と未来を結ぶ糸が複雑に絡まりすぎて、私にはお手上げだったのだ。複雑すぎて矛盾を感じる余裕すらなかったためか、ごまかされたような気にもならず、かえって素直に楽しめた。おそらく、タイムトラベル小説のファンなら至福の時間をすごせると思われる作品だった。
『虚空の旅人』
評価:![]()
日本を代表すると言っても過言ではない壮大なファンタジー作品「守り人」シリーズの続編であり、シリーズがさらに大きな流れに突入する転換点の物語。「守り人」シリーズの外伝的位置付けの作品かと思いきや、シリーズ全体の流れを左右する転換点となる物語であり、チャグムやシュガがキャラクターとしてさらに成長をとげ、人物像や人間関係に深みが増して、ファンはシリーズの展開からますます目が話せなくなる。
上橋菜穂子氏のファンタジーの魅力のひとつは、作品の世界に奥行きがあり、読者がその世界に吸い込まれそうなほど活き活きと臨場感があふれていることだろう。また、作品の世界の中に吹いている風や波の音が本当に聞こえてきそうな見事な表現力と、登場人物たちの喜びや悲しみが心にびんびん伝わってくる力のこもった文章も、昨今のファンタジー作家では群を抜いている。
この作品も、そんな上橋ファンタジーの魅力が詰まった秀作だ。「守り人」シリーズを読んでいない人でも楽しめるほど、ひとつの物語としての完成度も高い。読者の年齢や前作を読んでいるかどうかは関係なく、読む人すべてを楽しませてくれる作品だと思う。
『黙の部屋』
評価:![]()
たまたま入った骨董屋でみつけた奇妙な絵のとりこになり、謎の画家・石田黙の消息を追う主人公が、やがて奇怪な事件にまきこまれていくミステリー小説。実在する画家と実在する絵画を使って小説を書くという珍しい趣向をこらした作品。著者自身が実在する石田黙という画家の作品に惚れ込んでこの作品を書いたということで、作品展まで開いてしまったらしい。小説の中に登場する絵画は、実際に写真が挿入されていて、小説に臨場感を演出している。
内容云々よりも、とにかく実在の絵画を使って書く美術ミステリーという手法が斬新だ。次から次へと登場する絵画を中心にストーリーが動いて、最後に画家本人にたどり着くという展開なのだが、次は何が出てくるのか、画家はどんな人物なのか、読者はわくわくしながらストーリーから目が離せなくなる。読み終えて振り返ってみれば、話としては面白みに欠けるようにも思えるのだが、あれだけのドキドキ感を与えてくれた斬新な手法は一読に値すると思う。
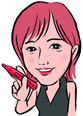
福井雅子(ふくい まさこ)
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >福井雅子の書評