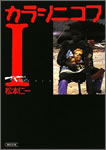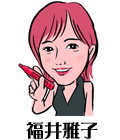WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >『カラシニコフ(1・2)』 松本仁一 (著)
評価:![]()
以前、普通の高校生2人が、彼らの通う高校で銃を乱射して自殺した『コロンバイン高校銃乱射事件』が取り上げられているマイケル・ムーア監督のドキュメンタリー『ボウリング・フォー・コロンバイン』を見た。「高校生が銃を持てるアメリカは怖い」と思っていたが、今は日本でも銃乱射事件が起きて、安心できない。さて、高校に通う前の少年達でも簡単に扱える銃、カラシニコフを開発したのが、ロシア人のカラシニコフ(銃と同名)だ。彼は、ライバルの米国製銃・M16の設計者から、「ベトナム(戦争)ではあなたの勝ちだ。」と言われて嬉しかったと語る。彼等が電気機器や製造機器の設計者ならば、互いの技量を認め合う技術者の会話として、普通に見過ごせた。けれど、彼等が造っていたのは、人を殺す武器だ。でも、銃を「人を殺す武器」にしたのは、紛れもないひと自身だとすれば、問題は、銃なのか、ひとなのか。映画『2001年宇宙の旅』で、骨が道具から人殺しの武器へと化してゆく冒頭シーンを思い出した。
評価:![]()
カラシニコフ、AK47やその模造品の銃を通して、世界の紛争や犯罪を追ったルポルタージュ。これを読むと、人類史上最も人を殺した兵器が原爆でも戦車でもなく、カラシニコフ銃だという言葉が大袈裟でないことがわかります。開発者のミハイル・カラシニコフが本書で語るように「日本には素晴らしい日本刀がある。それで人が殺されたら、刀鍛冶が有罪になるのか」という意見ももっともだとは思うのですが、簡単に何十人、何百人と殺せる兵器と日本刀とをひとくくりには出来ないというのも事実だと思うのです。簡単に扱えるということが、誘拐してきた子供を少年兵に仕立て上げるという別の被害を生んでいる。ただ、カラシニコフもロシアを守るために銃を開発したわけで、何が悪なのかとは一概に言えない。
国家の役割とは何なのか? 失敗した国家の現状を知ることでその答えも見えてくる。元少年兵が言った「この国で暮らすのはもういやなんだ」という言葉が胸を打った。
評価:![]()
住民の生活が保障され、安全が当たり前。「国家とは世界のどこでもたいていそんなものだ」という、日本人が持っている概念を覆される内容。そうじゃないと、頭ではわかっているつもりだった。しかし、私たちがいかに安全でどれだけ安心して住める国家にいるのか痛感させられる。「カラシニコフ」という自動小銃を通して、断片、あるいは想像もしなかった事実を知らされた。
まず、ショックだったのが、アフリカのシエラレオネという国の少女の話。11歳で、武装集団に連れて行かれ、レイプされ、盗賊のまねごとや人殺しもさせられる。そんなことが起こる世界があるなんて。読み始めて数ページで気分が悪くなった。そして、カラシニコフがもたらした悲惨な現実と対比するように、元気で朗らかすぎるともいえるカラシニコフの設計者のインタビュー。淡々と浮き彫りにされるのはショックなことばかりだ。
けれど、一方で不安定な生活を自分たちで整えていこうとする動きもあって、そこは唯一ホッとさせられる。知ったからと言って1人の力ではどうしようもないことだが、知らないというのは不誠実な気がした。
評価:![]()
心に残る新聞連載だったため、今回文庫本として再会できて幸せに思う。
扱いが簡単で過酷な環境下でも故障しないことから爆発的に世界中に広がり、ゲリラ紛争や子ども兵士を生み出す一因ともなったと言われる銃、カラシニコフ。その銃を軸にして、銃に翻弄される国家や人びとの姿を描き、国家とは何かを考える。国家としての機能を果たせていない国々と貧困にあえぐ人びと、拉致されて銃を持たされ人殺しをさせられて傷つく子どもたち、権力と金をめぐって争いを繰り返す政府高官やゲリラの幹部、銃と麻薬との密接なつながり──カラシニコフという銃を通して、今日の世界が抱える問題が次から次へと見えてくる。
持論を展開するための取材というよりは、今起きていることの真実を多くの人に伝えようという新聞記者らしい取材姿勢と客観的な視線が、カラシニコフの周りに渦巻く問題を実に効果的に浮かび上がらせている。取材対象やテーマへのぶれのない継続的なアプローチや、読みやすく上手な文章も素晴らしく、どこから見てもノンフィクション作品として最高レベルだと思う。文句なしの五つ星!一人でも多くの人に薦めたい本!!
評価:![]()
カラシニコフという名前は何度か耳にしたことはあったが、自分とは関係のない世界に存在するものだと思っていた。戦争や内戦のニュースを見ながら、ある一部の国で起こっていることで、その他の国は概ね平和に毎日が過ぎているのではないかとなんとなく感じていた。
朝日新聞の連載をまとめた本書は、カラシニコフを通して世界を知ることができる。カラシニコフの生まれたいきさつを発明者から聞き取るだけではなく、アフリカや中東の内戦が止まない、犯罪が絶えない国の若者への取材を通してカラシニコフが与えた影響を追う。中南米やアメリカ、中国、アジアで、貨幣の代わりにやり取りされるカラシニコフを追う。
読みながら自分は本当に無知であることを実感してしまった。東西冷戦の影響は朝鮮戦争やベトナム戦争だけでなく、また戦争が終了したからそこで終わりというわけでもない。世界各国の同盟国へ流れた銃は冷戦終結後も残るのだ。扱いやすく壊れにくく手入れのしやすいカラシニコフ。ロシアを救おうと発明されたその銃はその後世界を駆け巡り、多くの若者を兵士やゲリラ兵や犯罪者にし、また多くの人々を死に追いやった。
テレビのニュースではわからない、根の深い世界の貧困や犯罪という問題をカラシニコフを中心に描くことで鋭く切り取った一冊だ。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >『カラシニコフ(1・2)』 松本仁一 (著)