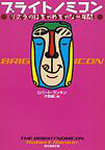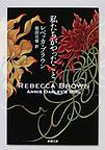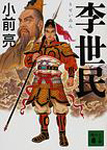WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >佐々木康彦の書評
『20世紀の幽霊たち』
評価:![]()
ホラー長編『ハートシェイプト・ボックス』のイメージから、本作もホラーかと思っていたらそうではありませんでした。謝辞中の短篇を一作目にカウントすれば三作目にあたる「二十世紀の幽霊」までは、ホラー作家の短篇集らしい作品が続きますが、四作目、親友だった空気人形との日々を回想する「ポップ・アート」からイメージが変わります。この作品集がホラーじゃない、ってわけではなく、ホラーでもあるし、幻想小説でもあるし、純文学でもあるけれど、どのジャンルにも所属していないといった印象を受けました。ホラーという土台の上にいろんな要素をブチ込んだ感じでしょうか。
『ハートシェイプト・ボックス』だけで、この作家のことを評価するのは間違っています。『ハートシェイプト・ボックス』がイマイチだった方も、是非是非読んで頂きたい。
『ブライトノミコン』
評価:![]()
謎の人物ミスター・ルーンと主人公がイギリスのブライトンという町に隠された秘密を解きながら、世界征服を企むオットー・ブラック伯爵の野望を阻止するというお話。
謎ごとに十二の章に区切られていて、毎回毎回挿入されるお約束の小ネタは爆笑するほどではないけれど、くくくっと笑ってしまう。ただここらへんは好みの分かれるところで、くどいと感じる方もいるかも知れません。「銀河ヒッチハイク・ガイド」や「サンダーパンツ!」のように、ふざけながらも実は真面目なスラップスティック・コメディ。でもやっぱりこういうのは、好き嫌いの差が激しいような……。
良い意味でふざけているというか、帯の「ま、とにかくオモシロイから読んでみて(by リズラ)」や実在しないラズロ・ウッドバイン探偵シリーズの紹介など、ストーリーとは関係ないところも人を食っていて笑えます。
『掠奪の群れ』
評価:![]()
ビリー・ザ・キッドやボニーとクライド、日本でいえば石川五右衛門など、アウトローのヒーローに胸躍らせるのは、男だけではなく女性も同じ。不良はモテるし、ハカイダーは子供に人気あり(古い)。Vシネマの任侠ものは結構観てしまう。悪いところではなくて、強いところにひかれるのですね。本作の主人公、ハリー・ピアポントも禁酒法時代のアメリカで銀行強盗を繰り返した「ディリンジャー・ギャング」の実質的リーダーというアウトロー・ヒーロー。初めて監獄に入れられた時の騒動から、ギャング時代、最後の投獄まで、カッコ良いイメージが崩れませんが、読了後よく考えてみると本作はノンフィクションではなく、小説なのです。実際はハンサム・ハリーもスケールの小さい男だったりしたのかしら、とか考えたりもしましたが、起こした事件は忠実にあることを考えれば、その事実だけでもすごいこと。映画みたいな本当の話(細部はフィクション)、スゴイです。
『私たちがやったこと』
評価:![]()
<安全のために、私たちはあなたの目をつぶして私の耳の中を焼くことに合意した>
表題作「私たちがやったこと」の一行目です。安全のために?物理的な意味での世界に対して、お互いを必要不可欠なものにすることで対応しようとしたのか。しかし、世界というのは個別のものであって、個人がひとつに繋がろうとしても、結局は亀裂が生まれるのでしょうか。
幻想的で夢の中の出来事のような雰囲気の「結婚の悦び」や淡々とした語り口で同性愛者の友の死を語る「よき友」と作品の幅があって楽しめた。特に「よき友」は胸をしめつけられるような思いで読んだ。「結婚の悦び」を動とすれば静。なのにこれが一番心に響くのは内容もさることながら、淡々と語られることも大きな要素なのかも知れません。こんなに悲しいんです、こんなに辛いんです、っていうのは逆効果になる時もある。語り手「私」を通じてありのままの現状を読むことで、読者は想像を制限されずに感情を揺さぶられるのでしょうか。
『チェンジリング・シー』
評価:![]()
中世の雰囲気と魔法、王子と庶民の娘との恋、王子の出生に隠された秘密、設定としてはかなりオーソドックスなファンタジー小説。わかりやすいので童話のような印象ですが、主人公の母親との関係や恋愛などには今っぽいものを感じました。
本作では海が主な舞台になっていて、突如出現した海竜をめぐっての騒動なんかも起こるのですが、全てはひとつの主題「チェンジリング」に繋がっています。このシンプルさは読者にとって物足りないとなるのか、読みやすいとなるのか人それぞれですが、やはり少年少女向けの読みものですね。
内容とは関係ありませんが、本作の少女漫画的挿絵は、満員電車で読書することの多い私にとってはちょっと恥ずかしかったです。小学館ルルル文庫は少女向けライトノベルですので仕方がないのですが、オッサンにはちと辛いものがありました。
『ムボガ』
評価:![]()
自分もそうなんですが、三十代後半って難しい年齢なんです。体も心も無理がきかなくなってきた、責任も出てきた、しがらみも多い、でも夢を捨てるにはまだ早いような気もする。若ければ後先考えずに出来ることが、家族の顔がまず浮かんでしまう。まだ何か始めるには間に合うけれど、それは確実に遅いということを自覚しないといけない。本作ではそんな年代特有のしんどさみたいなものがちゃんと描かれていて、同じ年代としてぐっとくるものがありました。そして物語に係わる重要な問題、外国人労働者のことには日本人として考えさせられることが多くありました。
著者の「床下仙人」とは相性が悪かったのであまり期待せずに読みましたが、かなり感情移入してしまいました。三十代後半から四十代前半の男性でこれを感情移入せずに読める方は、かなり充実した毎日を送っておられる方でしょう。
『李世民』
評価:![]()
本作は唐朝初代皇帝李淵が挙兵してから息子の李世民が皇帝になるまでを、多くの登場人物に満遍なくスポットを当てながら描いた歴史小説で、当時の情勢等がわかりやすく書かれていて非常に読みやすかったのですが、特定の事件や人物をあまり深追いしていないので、小説としては淡白な印象を受けました。当時の情勢などがわかりやすく描かれているので、中国歴史小説の入門書として良いかも知れませんが、逆に詳しい人にはちょっと物足りないかも知れません。
李世民が兄弟を殺す理由は史実だけを読んでいると理解出来ない部分もありましたが、本書を読んで、そういう状況もありえるか、と少し理解出来たような気がします(もちろんその状況はフィクションでしょうが)。中国語で「故事」とは単に昔話を指す言葉ではなく、物語のことなのだそうです。いろいろな思惑を持った人たちの物語が重ね合わさって歴史が作られていくということがよくわかる小説でした。
『本当はちがうんだ日記』 穂村弘/集英社
「今はまだ人生のリハーサルだ」と思うことで今のみじめさに耐えている、「芋虫が蝶に変わるように、或る日、私は本当の私になる」って、十代、二十代ならまだしも四十代のおじさんの言葉じゃない。このどうしようもなさが面白いのですが、全部読むと著者が努力せずにこういうことを言っているんじゃないことがわかり、面白いだけじゃなく、自分も頑張ろうと思える良い読み物でした。
「友達への道」や「夜の散歩者」で書かれている、人との相容れなさは、よくわかるけれど、客観的に読まされると笑えてしょうがない。「あだ名」も笑えて笑えて、笑いすぎてなんだか最後は泣けてきた。この辛さを外に向けるのではなく「あれこれと気を遣って、しょっちゅうもう駄目だと思いながら、びくびく暮らしている」ってところが、共感を呼ぶのではないでしょうか。
雑誌の対談とかだけだと真面目な人のイメージでしたが、印象が変わりました。面白い人だったのですねえ。

佐々木康彦(ささき やすひこ)
30歳になるまでは宇宙物理学の通俗本や恐竜、オカルト系の本ばかり読んでいましたが、浅田次郎の「きんぴか」を読んで小説の面白さに目覚め、それからは普段の読書の9割が文芸書となりました。
好きな作家は浅田次郎、村上春樹、町田康、川上弘美、古川日出男。
漫画では古谷実、星野之宣、音楽は斉藤和義、スガシカオ、山崎まさよし、ジャック・ジョンソンが好きです。
会社帰りに紀伊国屋梅田本店かブックファースト梅田3階店に立ち寄るのが日課です。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >佐々木康彦の書評