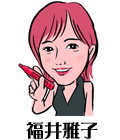WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >『20世紀の幽霊たち』 ジョー・ヒル (著)
評価:![]()
2月号課題本『ハートシェイプト・ボックス』の著者が再登場。前回はロックネタが散りばめられた長編だったが、今回一番感じたのは、「生理的な気持ち悪さ」。オープニングを飾る作品では、毎年『年間ホラー傑作選』(これが短編のタイトル)の編集を担当して、少々飽きている編者キャロルが主人公。そこに、身の毛もよだつような、けれども魅力的な作品『ボタンボーイ』が届けられる。この『ボタンボーイ』の主人公、残酷なことばかりするので、その様子を想像するだけで本当に気持ちが悪い。ああいやだこんなの、と思いつつ、この短編の結末はどうなるののだろうと気になり読んでしまった。まるでキャロルみたい。『蝗の歌をきくがよい』は、「ある朝、不安ではないが喜びに満ちた夢から目覚めると、フランシス・ケイは一匹の昆虫になっていた」で始まる。これは、「グレゴール・ザムザがある朝、なにか不安な夢から目を覚ますと、自分がベッドで巨大な虫に変わっていることに気づいた」で始まる、カフカ『変身』のパロディ。厄介者扱いされて死ぬザムザに比べると、こちらの蝗はエイリアンか変身した怪獣みたい。ああ、目の前にいたらと考えただけで気持ち悪い!
評価:![]()
ホラー長編『ハートシェイプト・ボックス』のイメージから、本作もホラーかと思っていたらそうではありませんでした。謝辞中の短篇を一作目にカウントすれば三作目にあたる「二十世紀の幽霊」までは、ホラー作家の短篇集らしい作品が続きますが、四作目、親友だった空気人形との日々を回想する「ポップ・アート」からイメージが変わります。この作品集がホラーじゃない、ってわけではなく、ホラーでもあるし、幻想小説でもあるし、純文学でもあるけれど、どのジャンルにも所属していないといった印象を受けました。ホラーという土台の上にいろんな要素をブチ込んだ感じでしょうか。
『ハートシェイプト・ボックス』だけで、この作家のことを評価するのは間違っています。『ハートシェイプト・ボックス』がイマイチだった方も、是非是非読んで頂きたい。
評価:![]()
「ハートシェイプト・ボックス」に続き、二度目のジョー・ヒル体験。すばらしい作品たちに、またほれぼれしてしまった。
まずは、クリストファー・ゴールデンの序文のあとの謝辞。ここには小品ながらハッとする作品が隠されていて見逃せないし、「年間ホラー傑作選」でいきなりホラー好きの心を踊らされ、「ポップ・アート」では胸がつまるような気持ちにさせられる。「蝗の歌をきくがよい」ではB級映画のクリーチャーの気分を味わわせてもらえるし、「おとうさんの仮面」では、子どものころの漠然とした不安を思い出さされた。読後の興奮を語りたい作品をあげればきりがない。どれも彼の才能が爆発していて、その広がりに驚かされるのだ。
当初、実力を試すため、スティーヴン・キングの息子という事実を隠してきたジョー・ヒル。七光りとは無縁の才能を持つとはいえ、語ると、つい、こうやって親の話もしてしまいがちだ。その父をすでに超えた?とは言いすぎかもしれないが、真実すごい作家のひとりだと思う。そして、これからも見続けたい作家だというのは間違いない。
評価:![]()
これがデビュー作とは聞いてびっくりである。「ホラー」をキーワードに短編を集めてはいるが、怪奇ものあり、幻想ものあり、アメリカ現代文学調のものや純文学風のものもあって、タイプの違う短編がよりどりみどりだ。「こんなのも、あんなのも、ちょちょいのちょいっと書けちゃうよ!」と言って、ジョー・ヒルが自身のずらりとならんだ才能の引き出しを順番に開けて見せてくれたような印象の短編集だ。しかもそのひとつひとつが、完璧ではないにせよかなりのレベルなのである。読者としては、今後の作品に期待せずにはいられない。
この本自体がものすごく面白いというわけではなかったが、驚きの才能を目の当たりにしてワクワクすることは確かだ。その才能をうまく活かしたオリジナリティーあふれる新作の登場に期待!
評価:![]()
ボリュームたっぷりで大満足、序文から作者のあとがき、訳者あとがきまで隅から隅まで楽しめてお得な短編集。
スティーブン・キングの実の息子であるジョー・ヒルは、偉大な父親と同じホラー小説という分野で七光りを跳ね返して活躍中だ。この作品集はグロテスクなものやホラーもあるのだけれど、ノスタルジックでホラーが苦手な人も楽しめると思う。
「十二歳のとき、俺の一番の親友は空気で膨らませる人形だった。」この一文から始まる作品「ポップ・アート」。小さいころは誰もがそうするように、動かない人形に話しかけて唯一の友達としていたのかと思いきや、小説の世界では本当に風船が生きて動いている。何度も風船が割れそうになって死にかけたりもしているけれど、学校でもいじめられているけれど、一生懸命に生きている友達「アート」との時間は主人公にとってかけがえのないものだ。アートがヘリウム風船を手にいっぱい持ち、空へ舞い上がって写真を撮るというゲームは物悲しくも美しい。
今まで「好きな短編は?」と聞かれて思い浮かんでいたのはレイ・ブラッドベリの「気長な分割」だったのだけれど、これからはジョー・ヒルの「ポップ・アート」と答えるだろう。
「そして、そういう物語というのは、決して一語たりとも必要以上に長かったりしないものだ。」これは短編の削除部分の掲載に当たって寄せられた文章だが、ジョー・ヒルの創作の姿勢を表すこの言葉どおりの良質な作品集である。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >『20世紀の幽霊たち』 ジョー・ヒル (著)