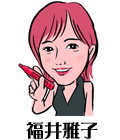WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >『ムボガ』 原宏一 (著)
評価:![]()
いやぁ、挑戦的ですね、このタイトル。何の意味だかわからない。さっさと言ってしまうと、人の名前です。アフリカ人で、日本に出稼ぎに来ていた若者の名前。彼が、北関東の田舎町でバンドを組んでいた中年男達を、自分の故国・トポフィ共和国(もちろん仮名です)に紹介すると、あら不思議、ツアーは大成功で、日本語で書くと「なんだこりゃ」と言いたくなるような歌詞が大ウケ。さてはこれ、世知辛い現実から目をそらしたくなることの多いミドルに捧ぐ、大人のファンタジー?でも話の中身は、結構イタイ。ホテルや旅館を対象とする最近の調査で、3割が「外国人を泊めたくない」と答えていた。でも、例えば介護の分野では、安い労働力として外国人の受け入れが始まっている。この辺りの、現実社会における、外国人に対する日本人の狡さや差別意識が、本作にも、かなり顔を出しています。ほら、イタイでしょ?あり得ない事ばっかりのフィクションを、笑い飛ばせる現実に…なるのかなぁ。
評価:![]()
自分もそうなんですが、三十代後半って難しい年齢なんです。体も心も無理がきかなくなってきた、責任も出てきた、しがらみも多い、でも夢を捨てるにはまだ早いような気もする。若ければ後先考えずに出来ることが、家族の顔がまず浮かんでしまう。まだ何か始めるには間に合うけれど、それは確実に遅いということを自覚しないといけない。本作ではそんな年代特有のしんどさみたいなものがちゃんと描かれていて、同じ年代としてぐっとくるものがありました。そして物語に係わる重要な問題、外国人労働者のことには日本人として考えさせられることが多くありました。
著者の「床下仙人」とは相性が悪かったのであまり期待せずに読みましたが、かなり感情移入してしまいました。三十代後半から四十代前半の男性でこれを感情移入せずに読める方は、かなり充実した毎日を送っておられる方でしょう。
評価:![]()
夢があるのは若者だけじゃない。年をとってくるとだんだん忘れてしまう、そう思っていた。でも、ほんとうは違うのだ。あきらめきれなかった夢はあっても、現実との折り合いをつけているだけなのだ。ほんとのところ、人はいつだって青春する用意があるのだ。
ここにでてくるオヤジたちもそうだ。田舎でアマチュアバンド組んで、「もしかして」の夢を見ることをやめていない。オリジナル曲づくりをしたり、夏祭りで演奏したりしている。ふつうはこのあたりでおしまいになりそうだが、アフリカの小国でメガヒットという奇跡が起こってしまうのだ。それだけで、テンションもあがっていくが、気を良くしたメンバーが日本でのメジャーデビューをめざすことで、隠れていた問題が浮上してくるのだ。その後の展開はぜひ読んで楽しんでもらいたい。
「コレステローラーズ」の面々の、オヤジ青春小説としても十分おもしろいが、ムボガの物語としても瞠目させられる。日常、見ていて見ていない、知らないことがたくさんあることに気づかされる。奇想天外なのにリアル。また、注目すべき作家に出会えてうれしかった。
評価:![]()
中年アマチュアバンド「コレステローラーズ」がひょんなことからアフリカの小国で大スターになり……という出だしから、ドタバタ喜劇小説かと思って読み始めたのだが、どうしてどうして、外国人労働者差別の問題と中年オヤジの生き方をめぐる葛藤という大きなテーマを正面から書いた真面目な小説だったのだ。
ノリと勢いだけで突っ走れる勇気はないが、かといって夢をあきらめることもできない宙ぶらりんの中年オヤジたちの葛藤が、妙にリアルで可笑しい。会社を辞めるときの同僚の反応や社内の様子など、細部にまでリアリティがある。そして、離婚届の用紙などリアリティを演出する小道具の使い方が上手い。夢が遠くなってしまったと寂しさを感じている年代の方々に勇気を与えてくれそうな作品である。
評価:![]()
本の売り場担当だった時、床下仙人が爆発的に売れていた。手に取ってみたけれど、話に聞いていたような、仕事に生きるサラリーマンの姿への共感はあまり起きず読み終わった。うーん、どうにも原宏一さんは私には早すぎるようだと思っていた。
中年の親父たちのバンドが、ムボガという黒人に気に入られ仲良くなったことから、彼の母国で曲は大ヒット、一躍大スターになってしまう。じゃあ日本でもメジャーデビューだ! とそれぞれの仕事を放り出して夢に向かって走り出した親父たち4人。そこに待ち受ける現実に悪戦苦闘する親父たちの姿を農村の後継者の問題や日本での外国人労働者の問題と絡めて描いている。
ただ現実でも深刻な問題であるこれらのテーマを書きたかったというよりは、中年おやじバンドの成長に無理やりくっつけているように感じられた。キャラクターの設定としてあるだけでなく、なぜ小説の中でそれが必要だったのか。色々描きたいんだろうなあという事は伝わってきたのだが、もっとページ数を割いて深く扱ってほしかった。
ところで巻末の高野秀行さんの解説がとても面白い。物語の構造を真面目に分析するタイプ、作者の人となりを語るタイプ、過去の作品や他の作家との関連を述べるタイプと色々な解説があるが、ユーモアたっぷりにそれらすべてを盛り込んで、読んでいない人も読みたくなり、読んだ人も楽しめるのだ。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年11月 >『ムボガ』 原宏一 (著)