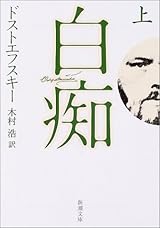作家の読書道 第104回:星野智幸さん
植物や水をモチーフにした作品や、政治や社会の問題を問いかけるような作品。幻想と現実を融合させた小説を発表し続けている星野智幸さん。少年時代に受けたカルチャーショック、20代の頃、新聞社を辞めてメキシコへと移り住んだ経験、影響を受けたラテンアメリカ文学、そして今の日本社会に対して感じていることとは。その来し方、そして新作『俺俺』についてもおうかがいしました。
その3「二人の小説家の出会い」 (3/6)
――高校に入ったら状況は変わったのでしょうか。国語の授業はどうでしたか。
星野:高校に入ると、今度は、名前は知られていないけれど小説家の人が国語の教師だったんです。古いタイプで、私小説命のような人だったんですが、この人の授業はむちゃくちゃ面白かったんです。それでようやく、日本の文学を読むようになりました。梶井基次郎の『檸檬』が教科書に載っていて、一読してなんだろうと思っていたら、授業で先生が「全宇宙がこの中にある」みたいな読解をして、それに驚いちゃったんですね。それから授業を聞くようになって、明治から昭和初期に至る、古典的な日本の作家たちを一気に読みました。それに、ちょっとカッコつけてる奴がいたんですね。太宰治なんかをわざと机の上に置いている奴がいて(笑)、それにも影響を受けたと思います。知らないって言えないなという気持ちが働いたのかも。
――その先生のお名前は。
星野:中石孝先生です。もう亡くなられたんですよね。小さい出版社から数冊本が出ていたんですが、それも高校の教師と生徒が出てくるような、私小説風の作品でした。先生の授業はファンが多かったんですよ。昔の文士という雰囲気を漂わせていて。酒飲みだけど、すごく穏やかな先生でした。
――先生の影響で読んだ作品のなかで、特に好きな作品というのはありますか。
星野:やはり梶井基次郎が好きでしたね。あれも私小説といっても幻想的な要素があるので。ただ、読んで嫌だなと思う作品はなかったですよ。夏目漱石からは人間ひねくれてよい、前向きに何か健全なことを目指す必要はないんだということを学びましたし(笑)、先生の影響でこっそり創作を始めたときは、太宰を真似したくなりましたし。太宰と村上春樹は真似したくなる文章なんですよね。だれも森鴎外を真似しようとは思わない(笑)。
――私小説風なものを書こうとしていたんですか。
星野:先生の授業を受けていると、なんか自分も書いてみたくなるわけなんですが、さすがに気軽には書けなくて。人生の大問題を抱えているようなことを書きたいのに、そんなものは何もない。だから書き出しをヘンに深刻に、もってまわったように書いたりするんです。「今日も私はあの店に寄らずに帰ったのだった」といったような(笑)。それでちょろっと書くものの、数行で終わりで完成しないという。ああ、思い出しました。話が戻りますけれど、中学時代に仲のよかった友達が行っていた塾の先生が、やっぱり小説家を目指していて、僕たちが中2のときに新人賞を取ってデビューしたんです。僕はその塾には通っていなかったけれど、「うちの先生が作家になったお祝いにカレーを食べにいくから来いよ」と誘われて、行ったんです。そのときはじめて本物の作家を見たわけですね。そこで即、自分も何かを書こうと思ったわけではないけれど、作家になるという選択肢がありうると気付いたのはそのときが最初だったと思います。
――その方のお名前は。
星野:五十嵐勉さんといって、『流謫の島』で群像新人賞を受賞した方です。全共闘世代で、受賞後はタイに住んでカンボジア問題にたずさわったり、「東南アジア通信」という雑誌を作ったりと、ジャーナリスティックな活動をしていました。そんなわけで、作家という人を二人知っていたんですね。中石先生の強い影響を受けていたから文学関係の方面に進もうと思っていて大学は早稲田に入ったのですが、高校時代に世界史も好きになっていたので、外国文学も読むようになっていたんです。それで、専攻を文学にするか世界史の方面にするか迷って決めかねて、どちらの授業もとれるように文芸科に進みました。五十嵐さんも早稲田の文芸科の出身で、平岡篤頼先生の弟子だったんです。なので、そういうヌーボーロマンの先生がいるということも知っていましたから、そんな影響もあったんだと思います。
――外国文学はどんなものを。
星野:大学に入ってからは仏文がどどーんと増えるんです。とにかく片っ端から古典とされる作品を読みました。18世紀くらいの、近代文学の始まりからですよね。仏文、英文、独文と、どの授業もとれるので、「18世紀フランス文学概要」といった授業を受けていたんです。仏文は年代順にだーっとヌーボーロマンまで読んで、ロシア文学も基本的なものを読んで。まわりにそんなものはとっくに読んでいるよ、という連中がたくさんいたんです。「20世紀四大文学読んでないの?」と言うような。そのとき彼が言っていたのはカフカ、フォークナー、プルースト、ジョイスでした。それは最低限の基本だよと言われたんですが、さすがに学生時代に全部は読めませんでした。でもそれは基礎であって、時代はニューアカですからドゥルーズとかフーコーだとかを読んでやっとスタートラインだと言われていました。そういう現代思想を読む連中か、村上春樹に熱中している人たちかばかりでした。その当時、ちょうど『ノルウェイの森』が出たんですよ。僕は古典を年代順にはじめていたから、そこに到達するのは無理だろうと思って、もうラスコーリニコフの気分で世の先端に背を向けて19世紀に閉じこもっていました(笑)。ちょっと退屈だなと思うものもありましたが、やはりこういう機会がないと読まないだろうとも思っていましたし。熱中したのはカフカ、ヌーボーロマン、ドストエフスキーと安部公房でした。
――それぞれどの作品がお好きだったのですか。
星野:カフカは短編が好きでした。「橋」という短編があるんですが、それは橋が一人称で語っている。人が自分の上を歩いていて、どんな人だろう、よし見よう、と思ってひっくり帰ったら落ちてしまった、という話。意味があるのかないのか分からないものが大半です。ヌーボーロマンはロブ=グリエがいちばん好きでした。『スナップショット』という作品は授業で読みましたね。ただ情景がずーっと描写されていって、また逆方向に描写されてもとの情景に戻っていったときに、少しだけ違っていたりする。ドストエフスキーは時期によって好きな作品が変わりますが、あの頃は『白痴』が好きでした。何もできない、何もなさない、というところが。安部公房はどれも好きだったんですけれど、「壁」とか「人魚伝」という短編。この頃から人魚が好きだったんです(笑)。
――星野さんの著作には『目覚めよと人魚は歌う』という作品がありますからね(笑)。創作の授業はあったのですか。
星野:ええ、演習とあと、卒業論文も創作でした。この頃は安部公房の影響を受けたものが多かったですね。あとは友達とも創作をしていたんです。それぞれが好きなことを何でもしようというサークルを作って、僕は小説を書きたいと言い、ほかの奴はテニスやら何やらをやりたいと言い。だから僕もテニスをしましたし、テニスをしたがった奴も小説を書きました。僕はとにかくグロテスクな幻想小説を書いていました。一方で赤瀬川源平が尾辻克彦名義で書いているものもよく読んでいて、卒論は安部公房的なテーマを尾辻的な小説にすることを目論んだんです。テーマは、小説家になって書いている作品と結局は通じてますね。「家」というタイトルで、家族像がテーマだったんです。共同体が自明なものではないという観点から、家族というのはそれ以上崩せないものだということを疑い、偶然の産物じゃないかということを書いて。一応、尾辻的なので、コメディなんですよ。
――小説家を目指そうとは思っていなかったのですか。
星野:そこまでは思っていなかったですね。小説を書くのは強烈な才能があって、人格的にも自分とは違う、極端な人だと思っていました。自分は違うと思っていて、就職しようと考えていました。