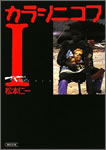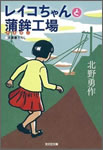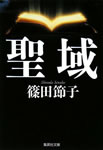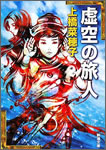WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >佐々木康彦の書評
『カラシニコフ(1・2)』
評価:![]()
カラシニコフ、AK47やその模造品の銃を通して、世界の紛争や犯罪を追ったルポルタージュ。これを読むと、人類史上最も人を殺した兵器が原爆でも戦車でもなく、カラシニコフ銃だという言葉が大袈裟でないことがわかります。開発者のミハイル・カラシニコフが本書で語るように「日本には素晴らしい日本刀がある。それで人が殺されたら、刀鍛冶が有罪になるのか」という意見ももっともだとは思うのですが、簡単に何十人、何百人と殺せる兵器と日本刀とをひとくくりには出来ないというのも事実だと思うのです。簡単に扱えるということが、誘拐してきた子供を少年兵に仕立て上げるという別の被害を生んでいる。ただ、カラシニコフもロシアを守るために銃を開発したわけで、何が悪なのかとは一概に言えない。
国家の役割とは何なのか? 失敗した国家の現状を知ることでその答えも見えてくる。元少年兵が言った「この国で暮らすのはもういやなんだ」という言葉が胸を打った。
『ハチミツドロップス』
評価:![]()
恋に部活に家族の悩み。悩み多き中学生の日常をお気楽なソフトボール部、通称ハチミツドロップスのキャプテン、カズの視点から描いた作品。
等身大の自分で良いんだよ〜♪ とか、自分らしく生きるんだ〜♪ みたいな歌詞がよくありますが、誰だって少しくらい演技して生きているんです。それも含めて自分なわけで、自分らしく生きられないからとか、自分のつくったキャラを続けられないからって悩む必要はないんだと思います。自分が生きやすい様に使い分けたら良いんじゃないでしょうか。そんなことを主人公のカズが、色々な経験を通じて理解するまでが描かれている作品と読みました。ハチミツドロップスの個性的なメンバーも面白く、「こんな奴いたなあ」と学生時代を懐かしんで読みました。ただ、青春ド真中過ぎて赤面してしまう場面もあり、私みたいなオッサンが読むには少々辛いところもありました。
『レイコちゃんと蒲鉾工場』
評価:![]()
タイトルから連想される「チャーリーとチョコレート工場」のようなファンタジー系のコメディですが、あれよりはちょっとSFよりです。何せ、本作で登場する蒲鉾っていうのは「蛋白質素材とシリコン基板とを貼り合わせてハイブリッド化したもの」なのですから。蒲鉾で造った人工知能で工場が運営されているといっても過言ではない状況なのです。本作中にも登場しますが、2001年宇宙の旅のHAL9000と本作中での蒲鉾は等価なのですね。と、最新鋭の人工知能と蒲鉾が同じってどんな話やねん、って感じですが、そういう設定を当たり前のものとして行われる蒲鉾工場の従業員のやりとりが笑えます。
笑いだけではなくて、虚構と現実が入り乱れる後半には何か深いものを感じました。最後のページでの「暗転中の注意事項」なんかは、人生の不遇の時期における注意事項として読んだ。
『聖域』
評価:![]()
偶然発見した未発表小説の続きを読みたくて、所在不明の作者を捜す編集者、という展開の中に、八世紀の東北を舞台に天台宗の僧侶が魑魅魍魎と対決する(か?というところで作品は未完成となっている)という幻想小説風の作中作「聖域」が組み込まれていて、この作中作が滅法面白い。そして現実世界の展開も、謎が明らかになるにつれて幻想的な描写になっていき、尻上がりに面白くなっていく。死について語られる後半にはとても惹きつけられるものがあった。「向こうの世界とこちらは、膜一枚でつながっている」のか? それとも熱力学の第二法則により、人が死んだ後、魂は世界中に拡散し、あの世というものを存在させないのか。最初から最後まで面白い小説だけど、この最後の方の展開は最高。ここで出てくるあの世感というかこの世感には、全部じゃないけど納得。スピリチュアル本を読むのも良いけれど、そういうのに興味がある人にも本作を読んで、「生と死」について考えてみて欲しい。
『マイナス・ゼロ』
評価:![]()
年末まで一ヶ月毎に復刊される予定の広瀬正小説全集の第一巻。
タイムパラドックスがナンボのもんじゃい!ってな感じに、時間の輪の中で人をぐるぐるまわしていて、最後は驚きの真相が明らかになる。そんなのアリか。登場人物が自らタイム・マシンで出来ることの実験をしているような描写もあり、これはかなりの確信犯。存在の環? 歴史の自己収斂作用? そんなこと知りませんが、過去・現在・未来の時間の中で人物の相関図が出来上がっていくのを読むのはすごく面白かった。そして読んだ直後は納得出来るんですが、よくよく考えてみると「どういうこと?」と考え込んでしまうところもあり、その考える行為自体も楽しい。
昭和初期の東京の街並は思った以上に進んでいて、物価の細かい描写も含めて、時代の空気感のようなものが味わえて、その部分でも楽しめた。
『虚空の旅人』
評価:![]()
女用心棒バルサが主人公だった前作までと違い、〈守り人〉シリーズ4作目となる本作では新ヨゴ皇国皇太子チャグムが主人公。守られる立場だった前作までとは違い、皇太子としての気品と人間的な強さを身につけたチャグムの活躍にシリーズ通読者は感涙にむせぶのではないでしょうか。まさに、巣立つ雛鳥を見守る親鳥の気分。本作だけを読んでも楽しめるつくりになっていますが、一作目から読んだ方が登場人物に対する思い入れがある分、絶対に面白いと思います。私はこのシリーズ未読でしたが、これを機に一作目から通読したところ、すっかりハマってしまいました。
「シリーズの流れを大きく変えた重要な一冊」とあとがきで著者も言うように、本作ではファンタジー的要素に加え、国家間の駆引きなども重要な要素になっており、近隣諸国だけでなく、ついに南の強国が動き出し策謀をめぐらせます。物語の厚みが増し、ファンタジーが苦手な読者の鑑賞にも堪える作品ではないでしょうか。
『黙の部屋』
評価:![]()
表紙の黒を基調とした不思議な絵。表紙をめくると同じ画家のものと思われる絵がまた数点カラーで現れる。この絵は何なのか。そして本文では、閉じ込められ絵を描くことを強要される記憶喪失の男。彼を閉じ込めた謎の男はこの記憶喪失の男のことを「石田黙」と呼ぶ。一方、美術雑誌の編集長が偶然購入した謎の絵。その絵を描いた画家の名前も石田黙。一体、石田黙とは何者なのか。謎だらけで始まり、中盤、読者に全容が見えたと思わせておいて、最後にまたスッコ〜ンとひっくり返す面白さ。主人公でもある美術雑誌の編集長のパート、監禁された謎の画家のパート、石田黙の妻と思しき女性のパートとこの三つを繋ぐ時間軸がはっきりしないので、読者は事実と虚構を行きかう不思議な感覚を味わう。あまり謎をひっぱられると、私みたいな辛抱足りない人間は、我慢出来ずに最後とか解説とかを読んでしまうのですが、展開の仕方がうまく、本作ではそういうことをせずに読めました。
『ロズウェルなんか知らない』 篠田節子/講談社
寂れた観光の町で、偶然(?)、降って湧いたUFO騒ぎや心霊現象の噂。青年クラブ(といっても皆中年ばかり)のメンバーが、それに乗っかり、「日本の四次元地帯」として町を売り込もうとする奮闘や騒動を描いた作品。
町の話題づくりに必死な青年クラブのメンバーに対して、老い先短い老人たちや生活の心配の無い役所の人間は非協力的。青年クラブの試みは突飛過ぎるかも知れませんが、座して死を待つよりも乾坤一擲の大勝負に出た彼らの行動を誰が笑えるでしょうか。こういったことは一般の会社組織でもあることで、私のような業績の良くない零細企業の社員にとっては胸を打つ場面もありました。全体的には今月の課題書「聖域」のシリアスな雰囲気とは違い、コミカルな感じでまたタイプの違う作品なのですが、根底に流れる世界観のようなものは「聖域」と同じだと感じました。こちらの作品も超お薦めです。

佐々木康彦(ささき やすひこ)
30歳になるまでは宇宙物理学の通俗本や恐竜、オカルト系の本ばかり読んでいましたが、浅田次郎の「きんぴか」を読んで小説の面白さに目覚め、それからは普段の読書の9割が文芸書となりました。
好きな作家は浅田次郎、村上春樹、町田康、川上弘美、古川日出男。
漫画では古谷実、星野之宣、音楽は斉藤和義、スガシカオ、山崎まさよし、ジャック・ジョンソンが好きです。
会社帰りに紀伊国屋梅田本店かブックファースト梅田3階店に立ち寄るのが日課です。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【文庫本班】2008年9月 >佐々木康彦の書評