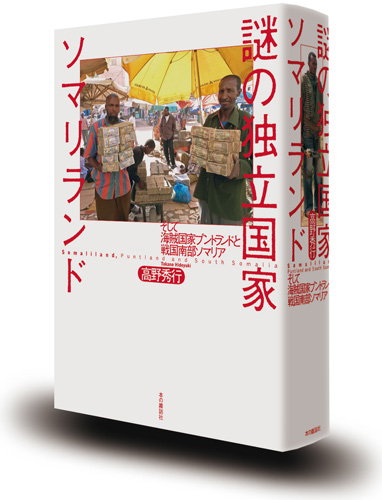第7回 ソ連古典SFのおどろくべき怪作(後編)
ソ連SFの草分け、アレクサンドル・ベリャーエフの『ドウエル教授の首』の続き。
ベリャーエフについては、幸運なことに、昨年(2022年)12月に「ロシア・ビヨンド」なるロシアの国営通信社系のサイトでかなり詳細な記事が掲載された。筆者はアレクサンドラ・グゼワというロシア女性。
それによれば、ベリャーエフは1884年生まれ。子供の頃から空想癖が強く、冒険小説に夢中だった。空を飛ぶことに憧れ、自力でグライダーやパラシュートを造ったり、さまざまな実験を行ったりしていたという。法律を学んで弁護士となったが、演劇とジャーナリズムをこよなく愛し、新聞記者も務めていた。
ところが、1915年(記事では「1905年」とあるが間違いだと思われる)、30歳頃に結核性の脊椎カリエスになり、両足が麻痺、三年以上も寝たきりになった。すでに結婚していたが、この闘病時代に妻に捨てられた。しかも、ソ連の革命と内戦という凄まじい動乱の時代。彼の母は飢餓で亡くなったという。しかし、不屈の闘志をもつベリャーエフは当時最先端の科学技術の潮流を読み漁ると同時に、ジュール・ベルヌやH.G.ウェルズの小説に没頭した。
1922年、奇跡的に足が回復し、当時最新の発明だったコルセットを装着することで再び歩けるようになる。それからSF小説の創作を開始。第一作が『ドウエル教授の首』である。
つまり、自分が両足麻痺で何年も動けず、妻に逃げられ、母は餓死という絶望体験の中からこの奇想は生まれたのだ。首だけ人間の苦悩がひじょうに生々しく描かれているのもうなずける。
1920年代の半ばから、彼は作品を次々に発表。後に大衆から熱狂的に支持されるようになり、作品のいくつもが映画化されたとのことである(※詳しくはサイトをご覧下さい)。
だが、『世界のSF文学総解説』などによれば、ソ連の体制内の批評家からは「荒唐無稽・非科学的」と評価されなかったという。
まあ、無理もない、と『ドウエル教授の首』を読んだ私は思う。ベリャーエフは、文章力や物語の展開力に欠ける。旧東側諸国の後輩作家である『ソラリス』のスタニスワフ・レムや『ストーカー』のストルガツキー兄弟のような筆力はない。登場人物も善玉と悪玉がはっきりしすぎているし、会話や描写は単調かつ芝居がかっていて、現代の大人が読むにはちょっと厳しい部分がある。ジュブナイルとしてはちょうどいいのだが。設定は江戸川乱歩の奇譚風、文章と物語は同じく乱歩の少年探偵団風と言えばわかりやすいかもしれない。
しかし発想は非凡で面白いのだ。二人のマッド・サイエンティストはさらに若い男女二つの生首を入手する。助手のマリーが鉢植えを育てるようにその二つの首の世話をする。
悪者のケルン教授は遺体置場にせっせと通い、移植によさそうな「よい死体」を物色。ロシア(旧ソ連)は昔から酔っ払って路上で凍え死ぬ人が大勢おり、身元不明の遺体にあふれていたと聞いたことがあるから、遺体置場にもわりと自由に出入りできたのかもしれない。やがて、たまたま列車の事故で死んだ、アンジェリカという有名な女性歌手のきれいな遺体を見つけると持ち帰り、ブリケという場末のキャバレーの歌い手で、拳銃で撃たれて死んだ女性の首と接続手術を行い、見事成功。
ブリケの方は生き返ったばかりか、もっとスタイルのよい体を手に入れて有頂天。早くシャバに出たいと、ケルン教授が彼女を学会で公開するまで待てず、研究所から逃げ出してしまう。
ここからがまた面白い。突然物語はグロテスクな研究所の室内での心理劇から、広い世界での冒険譚に早変わり。ケルン教授は目の色を変えて彼女の行方を追う。いっぽう、有名歌手アンジェリカは列車事故から忽然と行方を断ってしまい、マスコミやファンが大騒ぎしている。たまたま逃亡中のブリケを見かけた若い男性ファンが、「顔はちがうけど、スタイルや仕草がそっくり」と驚き、彼女の後を追いかける。
二人の人間をくっつけて一人の新しい人間を造ったものだから、首を追う者と体を追う者という二種類の追跡者が生まれてしまうのだ。
これはミステリとしてもサスペンスとしても斬新極まりない。さらに父親の行方を探すドウエル教授の息子が追跡劇に参加し、ドウエル教授の首とマリーに危険が迫り、登場人物の間に恋愛感情が発生するなど、面白くなる要素だらけなのだが、惜しいかな、著者の力量を超えているようで、わりと普通の活劇に収まってしまっている。
なんとももったいない。『海底二万里』とは別の意味で、本書もポテンシャルの塊なのだ。
本書もぜひ改変したい。私が編集者なら、まず島田荘司氏に本格ミステリに仕立て直してもらうだろう。『占星術殺人事件』に匹敵する傑作が誕生するかもしれない。
もう一つの案は新作落語にしてもらうこと。ベリャーエフの小説には独特な滑稽味もあるから相性もよさそうだ。第一候補は三遊亭白鳥師匠だろう。
白鳥師匠は美内すずえの名作マンガ『ガラスの仮面』を落語に転換させた「落語の仮面」や、「ムーミン」と古典落語をくっつけた「メルヘンもう半分」など、大胆な改変噺が得意中の得意。しかも、本格ミステリ並みに伏線を編み込んだ上で、壮大なストーリーを展開し、最後に必ず伏線回収してくれる。落語の方がハードルは低いかもしれない。白鳥師匠をその気にさせるだけでいいのだから。
最後にこぼれ話を一つ。私は本書が妙に気になって、訳者の田中隆氏に直接電話で簡単ながらインタビューしてしまった。それによると、現在のロシアでは、ベリャーエフの全集が刊行され、「偉人伝」みたいな彼の伝記も出版されているという。「ソ連のベルヌ」改め「ソ連の乱歩」は今、それなりに評価されているらしい。
ちなみに、田中さんは2011年にロシア滞在中、書店でたまたまこの本のペーパーバック版を見つけて購入。読み始めたら、「これ、昔、学校の図書館で読んだ話だ!」と気づき、あまりの懐かしさと意表をつく面白さから、翻訳企画を知り合いのいる出版社(未知谷)に持ち込み、無事刊行される運びになったという。田中さんは私より二つ上の1964年生まれ。おそらく同じ岩崎書店のSF少年文庫版を読んだと思われる。
子供の頃に呼んだSFを原書で再読するばかりか翻訳出版までしてしまう人がいたわけで、さすがソ連SF幼年期の怪作、魔力が尋常でないのだった。