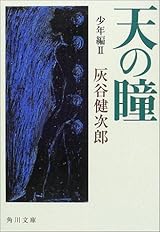作家の読書道 第174回:彩瀬まるさん
2010年に「女による女のためのR‐18文学賞」読者賞を受賞、2013年に長篇小説『あのひとは蜘蛛を潰せない』で単行本デビューを果たした彩瀬まるさん。確かな筆致や心の機微をすくいとる作品世界が高く評価される一方、被災体験をつづった貴重なノンフィクション『暗い夜、星を数えて 3・11被災鉄道からの脱出』も話題に。海外で幼少期を過ごし、中2から壮大なファンタジーを書いていたという彼女の読書遍歴は?
その2「中2でファンタジー作品を書き始める」 (2/7)
――文章を書くのは得意でしたか。
彩瀬:サンフランシスコの日本人学校にいた時から国語の成績はよかったんです。で、お話を作る授業があったんですね。たとえばゴリラがいる檻の前を飼育員が通っていて、ゴリラがひょいと手を伸ばしてその人のお尻のポケットに入った鍵を抜いているイラストだけを渡されて、「ここからお話を作ってください」というような課題があったんです。それの出来がいいからと、みんなの前で朗読させられたこともありました。だから文章を書くことは結構自分に向いているんじゃないかなと思っていました。でも作家になりたいと思ったのは大学3年生です。あ、でも中2から小説は書いていました。
――どのようなものを。
彩瀬:それこそ流星香さんの真似のようなファンタジー小説です。私、アフリカの体験が記憶に強くて。私はご飯に困らないし、服にも困らないし、運転手つきの車で学校に通っているけれど、道端には私と同年代の物乞いの子がいる、ということがずっと引っかかっていて。
この瞬間に車がなくなって正面から対面したら、私はなにを言うだろう、この子たちになにを言われるだろう、きっと許してもらえない、という恐怖心が強かったんです。5、6歳の頃ですね。それがたぶん根っこにあって、中学2年生の時に書いたのは、生まれついた時から背中についている痣で身分が分けられてしまう世界を舞台にしていました。血族によってどの身分の痣が出やすいかも変わるので、一番上の身分に生まれた王族の王子の主人公が、王家を飛び出して自分の父親を殺すって話を書こうとしたんです。
――おお、父親殺しという永遠のテーマを。
彩瀬:そう。家を出て、結果的に別の身分の人とつきあうなかで、最終的に王家打倒をするって話を考えていたんですけれど、3~400枚くらいいったあたりから「じゃあ平等ってなんだ。痣が全部消えればいいのか」というふうに考えて、書けなくなって。「生まれた赤ちゃんの痣をみんな焼きごてで消せば平等って設定になるの?」みたいなことを考えていくうちに萎んでいって書けなくなったんですが、それを中学から高校の間に書いていて、プリントアウトしたものを持っていったら友達や部活の先輩が面白がってくれて回し読みしてくれたんです。たぶん、毎日原稿用紙5、6枚、下手すると10枚書いて感熱紙にプリントアウトして持っていくと、どんどん人が読んで、誰かが分厚いリングファイルに綴じていってくれて、一冊の本状態になって、それがひとつ上の学年で回し読みされて...ということがあったんです。私の黄金期です(笑)。
――すでに読者を獲得していたんですね。なのに作家を目指そうとは思っていなかったということですか。
彩瀬:職業としては意識しにくかったですね、やっぱり。親が外交官とか公務員を望んでいる節があって、自分が親の意向から抜けるってイメージがなかったですね、その頃は。
――では、中学生時代の読書生活といいますと。
彩瀬:中学生くらいから文芸書を読むようになりました。誕生日だったかに母親が、私が普段読んでいるようなイラストつきの小説ではなくて、そろそろ文芸書を、と考えたんだと思いますが、灰谷健次郎さんの『太陽の子』をくれたんですね。はじめはイラストも可愛くないし、と思って手に取らなかったんですけれど、何かの拍子に手に取ったら面白くて「ああ、こういう形の本ももう読んでいいんだ」となって、灰谷先生の本から入っていきました。『兎の眼』とかって、なんかこう、子どもが読んでもキリッとくるんですよね。
――新米の学校の先生と生徒たちの話ですよね。
彩瀬:蠅を集めている、しゃべらない男の子が出てきたりして、読んでいてつらくなるけれど読んでしまうんですよね。『天の瞳』も全部読みました。灰谷健次郎さんの本は基本的に子どもが主人公だから子どもの私も読みやすいと思ったんですけれど、短篇集を読んだ時に当たり前ですが大人の男の人が主人公だったり、子ども以外のお話もあったりしたので、「そういうのも読んでいいんだ」と思い、ちょっとずつ読む本が広がっていきました。そういえば下村湖人の『次郎物語』も読みましたね。家の本棚にありました。家にあったということは、さりげなく親が買っておいた本を、そうと気づかずに読んだのかな。
――夏目漱石や太宰治といった古典的なものなどを学校の教科書や課題で読んだりはしませんでしたか。
彩瀬:灰谷健次郎や下村湖人のようなやんちゃな男の子の成長物語よりちょっとねじれているから、難しく感じて食指が動かなかったんです。中学生になっても相変わらずライトノベルなど10代向けの本を読んでいましたし。『ロードス島戦記』は学校で回し読みしていました。中学校の後半ではハリー・ポッターが流行っていたな。私は1巻で「いいや」と思って読んでなかったんです。読めば空想を羽ばたかせる快感もあったんだろうけれど、当時そこまでそれを求めてなかったんです。だから実は、3巻以降どうなっているのかよく分からないんです。
私はたぶん、『おてつだいねこ』もそうなんですけれど、小さい頃から「やるせない」がどこかテーマにあると、引っかかるんですよ、きっと。日常の、制限のある中で生きていかなきゃいけないときの「やるせない」が引っかかる。だから魔法の世界で何かしらの魔法や神の手が入り込む余地があると感じるものは引っかからなかった気がする。