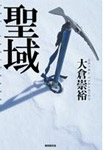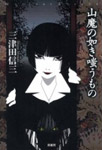WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年6月の課題図書 >松井ゆかりの書評
『聖域』
評価:![]()
山岳ミステリーというものには常に一定の需要があり、必要十分な量かはわからないがコンスタントな供給もある。私自身はそれほど詳しいわけではないのだが、ある種の読者には強く訴えかけるジャンルであろう。
「聖域」でいちばんよかったと思うのは、主人公が恋愛にかまけていないところだ。山岳ミステリーには(それほど数を読んでいるわけではないのだが、私の読んだ限りでは)もう、山で亡くなった主人公の親友を忘れられないヒロインとその彼女に密かに想いを寄せる主人公という両名を登場させなければならない決まりでもあるのか、と思うくらい必ず出てくるような気がしていたのだが、本書ではスルー。もしかしたら主人公草庭は亡くなった親友安西の恋人だった絵里子に特別な感情を抱いていたのかもしれないが、その辺のことは詳しく描写されない。よしよし。
“著者渾身の一作”と呼ぶにふさわしい作品であることは、「あとがき」の著者の文章からもうかがえる。「あとがき」でもうひとつ、桜庭一樹さんのエッセイでおなじみとなった東京創元社の伝説(でありながら現役)の編集者、K島K輔氏に触れられているのも一興。
『乾杯屋』
評価:![]()
著者の名前を初めて知ったのは第137回直木賞候補にあがったとき。そのときの候補作の題名から時代小説家なのかと勝手に思いこんでいたら、ずいぶんと下世話な(中傷して言っているのではないが)現代ものだったのでちょっと驚いた。
本書には6つの短編が収められており、そのほとんどの主人公が多かれ少なかれいずれも、ギラギラしていて人生まだまだあきらめはせんぞと息巻いている中高年男性だ(若者が主人公の場合も、野心的なタイプ)。本書を読んで「俺だって」と意気込む同年代諸氏は多いのかもしれないが、個人的には(自分も十分中年なわけだが)ちょっと食傷気味。もちろん年配の人々がエネルギッシュであることに対して文句を言うつもりはまったくないのだが、「好みのタイプ=笠智衆&山本学」である身には少々刺激が強かったな〜。
『風花』
評価:![]()
率直に言って、川上弘美さんの描く登場人物に対して時に苛立ちを感じることがある。本書の主人公のゆりにしても優柔不断過ぎやしないか?と思うし、夫の卓哉もはっきりしないし、卓哉の不倫相手は感じが悪いし、と今回は特に読み始めてしばらく「なんだかなあ」感が強かった。
しかしながら、原因はわかっている。自分にものゆり的要素が多分に含まれているからなのだ。私はのゆりと同じく専業主婦で、世間的にはまあ気楽な身分とみなされているのだと思うが、それでも日常生活においてさまざまな選択を強いられる場面に遭遇することはある。母から任された亡父の法事の手配、加入するべき保険の決定、息子たちの衣類の購入などなど…。そんなときふと、「ああ、こういうの全部先送りしちゃえたらな」と思う。後になってたいへんになるのはわかっているにもかかわらず。
卓哉みたいな夫とはさっさと手を切るべき。できるだけ早く自活の道を考えなければだめ。と、言うだけならたやすい。でももし自分が同じ立場だったらやはり知らないふりをしてしまうかも。のゆりに感じる不満は、結局のところ近親憎悪なのだろう。
『山魔の如き嗤うもの』
評価:![]()
みなさんは髭男爵というコンビのお笑い芸人をご存じだろうか。ここでその魅力を詳細に語るのは紙幅の制約もあるし、本稿の主旨から外れるのでやめておく。が、本書のカバー見返しに印刷されたあまりにも怖ろしげな童歌を読んだにもかかわらず、髭男爵がネタに入る前の「パンを盗んだ少年を優しく許してあーげる」「素敵なマドモアゼルをダンスにさーそう」といった口上を思い出し、恐怖心が一気に和らいだことはぜひとも明記しておきたい。さもなければ、こんなにも怖さを煽るような表紙をもつ本など読み進められたかどうか自信がない(文章だったら多少怖ろしい内容でもなんとか読み進められるのだが、漫画イラストや映像で怖いものはまったくだめ)。
かねてより本格ミステリー者の間ではえらく評価の高かった三津田信三氏の最新作。なるほど、評判に違わぬ実力とお見受けした。怪現象がきれいに理詰めで説明される快感は、怪奇趣味的な描写(&表紙の怖さ)を乗り越えて読む価値があったと思わされる。できれば最後の最後にオカルト風味を付け加えない方がよかったと思うが、それは読者によって好みの分かれるところであろうか。
『享保のロンリー・エレファント』
評価:![]()
「拾いもの」という表現はたいへん失礼なのだが、著者に関する予備知識がなかったせいとの言い訳をもってご容赦いただきたい。著者略歴によれば、薄井ゆうじ氏は時代小説を専門に書かれている作家ではないようだ(まあ、言葉選びなどからも推察できるが)。個人的には、時代小説を読むなら「端正で趣のあるものを」「現代語の使用などもってのほか!」という保守派なので、若干否定的な気持ちを押さえられないまま読み始めたのだが、思いがけず心打たれた。象という、時代小説においてはファンタジー的な存在があったのがよかったのだろうか。特に気に入った作品は「マン・オン・ザ・ムーン」(思いっきり現代語、しかも外来語だ!)
エピローグの無理矢理取って付けた感じはマイナスポイントではなかったかと思わないでもないが、江戸時代の人々のたくましさを描いて、それもありかも。
『壁抜け男の謎』
評価:![]()
これから本格的に有栖川作品を読んでいこうと思う人間にとって、本書を最初に読むというのはどうなのだろうか。というか、少なくとも私にとっては失敗だったかもしれないなという結論に達しつつある。手を抜いて書かれた作品はもちろんひとつもないと思うが、まずは長編をじっくり読んでみるべきだったという気がしている(長編の有栖川作品の魅力を知っている読者には、より楽しめる内容かと思われるが)。
しかし、これだけははっきり言える。どの短編においてもアリス先生のミステリーへの愛情がひしひしと感じられるということだ。「あとがき」もしかり。短編ひとつひとつについて自ら解説されており、読者サービスということを常に忘れない先生のお人柄が偲ばれる。
本書には16作品が収められているが、やはり注目は“あの有栖川有栖による官能小説”「恋人」。まあ官能小説といってもかなりの変化球なのだが。個人的には主人公の心の動きに共感するのが難しい部分もあるけれど、アリス先生がどうしようもなくロマンチストだということがわかりました。執筆を依頼した津原泰水氏がすごい。いろんな意味で。
『変愛小説集』
評価:![]()
昔、私にとって“本を読む”という行為はすなわち“外国文学を読む”ということだった。「あしながおじさん」「飛ぶ教室」「赤毛のアン」…。それがいつの間に変わってしまったのだろうか、ふと気づけば追いかけるのは日本文学の新刊書がほとんど。この「今月の新刊採点」の課題図書にリストアップされているため自動的に読む以外の翻訳書は、めったに手に取らなくなってしまった。
そんな私をかろうじて外国文学につなぎ止めてくれる最大の功労者が岸本佐知子さんである。正直、その岸本さんの本にしても翻訳ものよりエッセイの方がよりおもしろく感じてしまうのだが、今回はかなりの当たりだったと言っていいだろう。本書の短編はどの作品も岸本さんが自信を持って薦められているものだと思うが、恋人同士の結びつきが描かれていて個人的にいちばん好みだったのは「僕らが天王星に着くころ」、主人公のバービー人形への歪んだ愛情に震撼させられたのが「リアル・ドール」、寓話と現実が奇妙に融合したような物語に不思議な読後感を味わったのが「母たちの島」。
『狐火の家』 貴志祐介/角川書店
夫と私の過去に影を落とすひとりの男がいる。彼の話題を出せばお互いに気まずくなるのがわかっているので、あえてその名を口にすることはない。その男とは…貴志祐介その人だ。
もう4年前になるか、夫に「何かおもしろい本ない?」と問われた私は、読み終えたばかりの「硝子のハンマー」をそのまま手渡した。そして数日。「何これ?」と能面のような無表情で本を返して寄こした夫の姿を私は忘れないだろう。
私の主張→「多少強引なところがあってもいいじゃない、本格ミステリーへの愛があれば!」
夫の主張→「いろんな意味でありえない。以上」
その貴志氏がこの春上梓した本書は、またもあのコンビが主役で、またも密室もの。懲りな…いや、それほどまでに本格ミステリーへの意欲に燃える氏に、私は喝采を送りたい。そんなわけで、夫に読ませるのはかなり難しいんですが、本欄をお読みのみなさまにはぜひ。

松井ゆかり(まつい ゆかり)
好きな作家は三浦しをん・川上弘美・村上春樹・伊坂幸太郎・蘇部健一・故ナンシー関。
影響を受けた作家ベスト3は、ケストナー・夏目漱石・橋本治(日によって変動あり。でもケストナーは不動)。
新宿の紀伊國屋&ジュンク堂はすごい!聖蹟桜ヶ丘のときわ書房&くまざわ書店&あおい書店は素晴らしい!地元の本屋さんはありがたい!
最近読んだ「桜庭一樹読書日記」(東京創元社)に「自分が買いそうな本ばかりに囲まれていたらだめになる気がする」という一節がありました。私も新刊採点員の仕事を させていただくことで、自分では選ばないような本にも出会ってみたいです。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年6月の課題図書 >松井ゆかりの書評