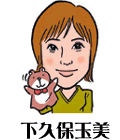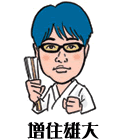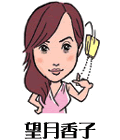WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年6月の課題図書 >『享保のロンリー・エレファント』 薄井ゆうじ(著)
評価:![]()
変幻自在なストーリー・テラーとして、この作者の小説には信頼を寄せているのですが、ほほう、まさか時代モノでくるとは……ちょっぴり意外、だからこそ注目大でありました。
享保年間、徳川吉宗の命で象が輸入されたのは史実。現代だって東京にアザラシが出現すれば大騒ぎだもの、江戸時代に象なんて大変だったでしょう。本作は、その象が長崎に上陸してから江戸に落ち着くまでの、各地点で繰り広げられるドラマを紡ぎ上げたもの。これがまあ、話の作り方がどれも巧い。大御所先生が描くようなシッポリ感は薄いのですが、情感と幽玄がブレンドされた特異な時代モノに、入り浸ってしまいましたよ。
とどめはエピローグの「吾輩は、象である」って……やられました、降参です。さんざんしんみり読ませておいて、かなりトリッキーなことをしでかしてくれますから、たまらないです。もう一回、時代モノをおかわりしたい気分です。
評価:![]()
最近、上野動物園のパンダが死んだということでいろいろと報道があったり、日中間でいろいろと交渉があったりとパンダ愛好家ではない私にしてみれば「パンダぐらいで…」と鼻白んだものです。しかし、パンダが初めて日本に来たときの話を聞く限り、ものすごくフィーバーしたらしい。やっぱり初めて見る動物が来るのはワクワクするもの。メディアが発達した現代ですらドキドキするのだからメディアの発達していない江戸時代、見たことのない動物が来るとなればそりゃワクワク×5くらいはおかしくない。本書は江戸時代に象が海外から来る!ということで獣医や役人など直接関わった人々から一見物人まで象が来たことで動き始めた人間模様を描いています。中でも象を呼んだ張本人8代将軍吉宗と息子の家重との交流を描いた「千日手の解法」がよかった。虚弱体質の息子に多くを求める質実剛健の父親とその父親に反発してしまう息子が象を介して徐々に心を通わせていく情景が心温まる。しかし、最後の象から見た人々を描いた「象を引く」は必要ないかも。後日談がどうしても説明口調になってしまい一連の流れに合わないように思います。
評価:![]()
版元やレーベルによって「こういう本なんだろうな」って、読む前からある程度のイメージが浮かぶことってあるよね。本格ミステリだろう、とか、ラノベっぽいやつかな、とか。で、本書は岩波書店。固めの重い本(中身が、ですよ)を予想していたのだけれど、良い意味で肩透かし。固さも重さも適度な連作短編集でした。
享保十三年、徳川吉宗に所望された象が長崎に着く。象は陸路を徒歩で江戸に向かう――
その時代に生きている人々の日常が、象という非日常の存在によって少しだけ変化する。いや、象はきっかけにすぎない。本当はずっと前から、変わるはずだったのかも。
象の来訪により訪れる変化は、必ずしも良いことばかりじゃない。でも、その変化に向き合うきっかけをくれたことを、象に感謝するべきなのかもしれない。
最後の1編、良いですね。それまでの全てをつなげる1編。ファンサービス。
評価:![]()
「拾いもの」という表現はたいへん失礼なのだが、著者に関する予備知識がなかったせいとの言い訳をもってご容赦いただきたい。著者略歴によれば、薄井ゆうじ氏は時代小説を専門に書かれている作家ではないようだ(まあ、言葉選びなどからも推察できるが)。個人的には、時代小説を読むなら「端正で趣のあるものを」「現代語の使用などもってのほか!」という保守派なので、若干否定的な気持ちを押さえられないまま読み始めたのだが、思いがけず心打たれた。象という、時代小説においてはファンタジー的な存在があったのがよかったのだろうか。特に気に入った作品は「マン・オン・ザ・ムーン」(思いっきり現代語、しかも外来語だ!)
エピローグの無理矢理取って付けた感じはマイナスポイントではなかったかと思わないでもないが、江戸時代の人々のたくましさを描いて、それもありかも。
評価:![]()
享保13年の長崎が舞台。長崎の湊に到着した象。象は、歩いて江戸城へと向かう…。
象の糞を売る人、象を斬ろうとする娘、象を診る医師、象の錦絵を描く絵師など、それぞれから、人生のひとかけらが語られます。
人間模様、それぞれの人生が描かれているのですが、それがドラマティック。印象的なシーンが多くあり、ところどころにアフォリズムが込められているようです。
最初から終わりまで、そのリズムが保たれていて、特にラストがたまりません。著者の小説、もっと読みたいです。
WEB本の雑誌>今月の新刊採点>【単行本班】2008年6月の課題図書 >『享保のロンリー・エレファント』 薄井ゆうじ(著)