『女たちのテロル』ブレイディみかこ
●今回の書評担当者●ときわ書房志津ステーションビル店 日野剛広
ブレイディみかこという書き手と今の時代をともに生きるということは、この不穏な世の中にあって、とても幸福なことである。
彼女のプロフィールについては、いまさらここで説明する必要はないだろうが、ひとつ個人的なことを書かせて貰えれば、彼女の文章との初めての出会いは5年前、ネットで目にした『墓に唾をかけるな』という一文だった。
マーガレット・サッチャーの死去に対し、その墓に唾をかけるなと言ったのは、かのジョン・ライドンである。サッチャーリズムの後始末に追われる名もなき市井の人々の苦闘とライドンの発言を、対比ではなく共感として位置づけたコラムは、格差の進む英国の現状と人々の悲哀をリアルに伝えた名文中の名文である。
本コラムは現在でもele-king.netで読むことが出来るが、2013年刊行のコラム集『アナキズム・イン・ザ・UK』(Pヴァイン)所収なので、ブレイディみかこがどういう人なのかを知りたい人は、ぜひ入門書代わりに紐解いて頂きたい。必ず魅了されることだろう。
彼女の文章には常に英国の「地べた」からの視点があり、世界中、そしてこの日本と地続きの切実な問題や社会の課題を照らし、切り込む力がある。なぜ彼女は英国の「地べた」をリポートし続けるのか。それは現在の英国の抱える問題は世界の縮図であり、今日の英国は明日の日本だからである......いや、もう今日の日本だ。
さて、前置きが長くなったが、ブレイディみかこの新刊が2冊ほぼ同時に刊行された。発売日こそ1ヶ月ほどズレているが、この刊行タイミングは画期的なことである。
100年前の3人の女性の闘争を描いた評伝『女たちのテロル』(岩波書店)。
息子との親子の絆と成長を描くエッセイ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)。
この2冊はテイストが違うようでいて、実は双子といっても良いほどその作品の核は同じである。同時刊行されたことにこそ意味があると思い、無謀ながら2冊同時レビューを試みたい。
まず『女たちのテロル』。
貧困と差別の中にあって、個人の尊厳の為に国家に抗ったアナキスト、金子文子。イングランドの女性参政権獲得の為に闘い、壮絶な最期を遂げたサフラジェット、エミリー・デイヴィソン。アイルランド独立のため、イースター蜂起を支援した凄腕のスコットランド人スナイパー、マーガレット・スキニダー。本書の主人公は、今から100年前、ほぼ同時代に闘いに身を投じた3人の女性である。
彼女たち3人に接点は無い。しかしそれぞれの敵は皆同じ顔をしている。権力と権威と暴力は、一個人の、特に女性の尊厳を根こそぎ奪い、苦しめ、諦めさせる。そして大衆をミスリードする。
ファシズム国家の中にあって、個人の尊厳を主張することは死と隣合わせだ。命を賭して支配する者へNO!を突きつけたが為に、迫害されながらも最後まで闘い続けた文子とエミリー、NO!と突きつけた大衆のために闘ったマーガレット。
その三者三様の闘う生き様がリンクし、交互に交わっていく構成は見事で、3人が本当に共闘しているかのような錯覚を呼び覚ます。
更に、これだけ重苦しいテーマにも拘らず、学術的にならず、ユーモアさえ感じさせるその文体は、現代の私達の目線に合わせて"翻訳"する彼女の、書き手としての力量であり、本書にもその鮮やかな筆致が冴え渡っている。
だが読者は同時に、この権力、暴力の理不尽さが100年経った今、蘇りつつあるということを、大きな不安と危機感をもって対峙することとなる。だからこそブレイディみかこが、この3人を現代に蘇らせたことには特別な意味がある。
ラストまで読むとわかるが、ブレイディみかこはこの3人の女性に導かれて本書を書き上げたとしか思えない節がある。それは栗原康が伊藤野枝に導かれて『村に火をつけ、白痴になれ』を、梯久美子が島尾ミホに導かれて『狂うひと』をそれぞれ上梓したことに並ぶ、運命的な出会いの賜物である。
本書はただの評伝ではない。この3人の女性たちの闘争の記録であり、現代にも連なる見据えるべき敵の正体を暴く告発書であり、彼女たちの魂を弔う檄文である。
そして『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』。
本書はブレイディみかこの、中学生の息子とのふれあいを通じて、「地べた」の英国を一緒に見つめていく物語だ。
日本よりも早く格差の進んだ英国。世界の縮図と言われる所以としての貧困、差別、分断は、ブライトンでつつましく暮らす親子の身近にも忍び寄る。戦争、紛争、武力行使という大きな暴力でこそないものの、言葉、隔離といった形の暴力をまとった社会の中でシビアに生きていくこともまた、現代の闘争であり、それは100年前の女性たちが体感した理不尽と変わることはない。
しかし母親をはじめ、差別の撤廃を目指して変わろうとする学校や大人たち、共に悩み、学ぶクラスメートたちに囲まれて頼もしく成長していく息子の姿は、微笑ましいという季節はとっくに通り過ぎて、凛々しい大人への扉を開けつつある。英国の抱える困難は彼女の息子を、正しさの軸を自分の中に据えて生きていく少年へと成長させていく。だがこの子の成長はこの親あってのもの。
この子に向けられた母親の眼差しは、とても優しく愛に満ちたものであるが、それだけではない。彼女の息子への視線は、『女たちのテロル』の3人の女性へのそれと実は似ているのではないかと思うのだ。肉親としての愛情と、過去の会ったこともない女性たちへの視線が同列に語れるのかどうかはわからない。ただ、これだけは言える。ブレイディみかこは自分の息子を1人の人間として信用し、その尊厳を守り抜いている。
親だからといって支配はしない。息子の気持ちを慮り、尊重し、時には息子の言動から新たな発見があり、それを受け入れる。だからその眼差しは100年前の3人の女性たちへ向ける尊敬と憧憬の眼差しとそう遠く離れてはいない。これは母親であるブレイディみかこ自身の成長物語でもあるのだ。
この親子の見つめる先には、これからも多くの困難が待ち受けるだろう。しかし、親子で育んできたフラットな視線は、そのまま生きる知恵や知性となり、世の中を変えていく力を蓄えていくはずだ。
最後に、ブレイディみかこの文章は、老若男女問わず支持を得るはずだが、あえておせっかいを言わせて貰えれば、ぜひ若い人たちにこそ読んで欲しい。
人を嗤い、嘲り、蹴落とすことでしか自身の存在価値を高められず、所詮は権力に寄り添って生きている新自由主義の申し子たちに憧れるくらいならば、人への尊重と尊厳を、愛と知性とユーモアで説くことのできる、ブレイディみかこのような大人に憧れてくれ! と、切に願うのである。
ブレイディみかこの作品がもっと多くの人々に届けば、多分、いやきっと、いや必ず世界は変わるぜ!
- 『まなざしが出会う場所へ』渋谷敦志 (2019年6月6日更新)
- 『牙』三浦英之 (2019年5月9日更新)
-
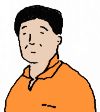
- ときわ書房志津ステーションビル店 日野剛広
- 1968年横浜市生まれ 千葉県育ち。ビールとカレーがやめられない中年書店員。職歴四半世紀。気がつきゃオレも本屋のおやじさん。しかし天職と思えるようになったのはほんの3年前。それまでは死んでいたも同然。ここ数年の状況の悪化と危機感が転機となり、色々始めるも悪戦苦闘中。しかし少しずつ萌芽が…?基本ノンフィクション読み。近年はブレイディみかこ、梯久美子、武田砂鉄、笙野頼子、栗原康、といった方々の作品を愛読。人生の1曲は bloodthirsty butchers "7月"。


