『ブードゥーラウンジ』鹿子裕文
●今回の書評担当者●ときわ書房志津ステーションビル店 日野剛広
オレはこの本を紹介するために、この「横丁カフェ」の執筆依頼を本の雑誌社から受けたのではないか。
話は昨年末に遡る。本の校正を生業とするその可憐な女性はオレにこう言った。
「私、実は人に本を勧めることって滅多にしないんですよ。でもこの本だけはぜひ、ぜひ、ぜひ!読んで欲しいんです!」
「ぜひ」を3回も繰り返したかについては正直に言って盛ってしまった感は否めないが、そこに非常に強い語気が込められていたことは嘘ではない。この本の校正を担当し、「チンチン」や「うんこ」という言葉が平気で飛び交う原稿を隅から隅まで熟読したであろう牟田都子さんがそうおっしゃるのだからこれは読むしかあるまい、売るしかあるまい。
福岡の介護施設「宅老所よりあい」を舞台に、パワー溢れる人びとの奮闘を描いた稀代の傑作ノンフィクション『へろへろ』(ナナロク社→ちくま文庫)を世に送り出し、その名を轟かせた雑誌編集者鹿子裕文。もちろん『へろへろ』は読んでいた。その鹿子さんの4年ぶりの新刊、しかも舞台は福岡の伝説のライブハウス、その名も『ブードゥーラウンジ』。オレの期待値がMAXに膨れ上がったのは言うまでもない。
『ブードゥーラウンジ』。往年のロックファンならば思い浮かぶのが、ローリング・ストーンズ1994年の同タイトル作品だろう。だがもうブードゥーラウンジという言葉は、ストーンズのキャリアでさほど目立つことのないこの作品よりも、福岡のライブハウスと本書を指す言葉に刷新された。もしもストーンズの作品を引き合いに出すならば、本書はむしろ60年代末期の傑作「ベガーズ・バンケット」や「レット・イット・ブリード」に例えたい。
このライブハウスブードゥーラウンジを舞台に繰り広げられる狂騒の中心にいるのが、レギュラーイベント「ラウンジサウンズ」をプロデュースする、自主制作レーベル「ヨコチンレーベル」代表取締役ボギーさんである。
彼は自分が楽しい、面白いと思うことしかしない。彼の人柄、自由さ、持って生まれた人を惹きつける力が人々を引き寄せる。そんなボギーさんの周りには実に楽しい人々が集まり、面白過ぎる音楽集団が次々とイベントにブッキングされていく。そして「ヨコチン」なんて品の無いネーミングには、実は世間から「はみだし」たものにこそ価値があるという、海よりも深い意味がある。
ブードゥーラウンジには、まさにヨコチンのようにはみ出した奇特なピープルが集まる。世間の常識、お行儀よさからはみ出し、居場所も拠り所もない、しかし己の心情を吐き出したい衝動を抑え切れない人たち。ロックとはそんな人たちの為のものでは無かったか。そしてブードゥーラウンジはそんな人たちにとっての至上の楽園であり、感情を極限にまでヒートアップさせ、爆発させることの出来る最後の場所である。
ミュージシャン、バンド名も、ザ・ボットンズ、カシミールナポレオン、漢方先生、鮫肌尻子とダイナマイトなどなど、イチイチ素晴らしく、彼らのステージの模様、放たれる音、歌、叫びを鹿子さんは文章に落とし込んでいく。それは単なる文字起こしではない。音楽そのものを文章化することの困難さなどはじめから無かったように、ロックの持つ怒りと悲しみと情け無さを全て内包させ、未だかつて聴いたことも無い音楽が、文章を目で追うオレの耳に確かに聴こえてくるのだ。
そんな彼らの世界の中でも、一際異彩を放ち凄まじい存在感を示すのが、本作のもう1人の主人公、ボギーさんの実弟オクムラユウスケさんである。この兄弟は性格も生き方も違うらしく、兄が陽のキャラでロックスターだとすれば、弟は陰でアンダーグラウンドのカリスマとも言えるだろう。しかし、この両者の違いこそが物語に奥行きを与えて行く。
鹿子さんは、オクムラユウスケの鬼気迫るパフォーマンスと呪詛のように繰り返されるフレーズ、ギターをかきむしる指、振り乱れる髪の毛、飛び散る汗も一つ残らずすくい取り、映像を見せてくれるかのように実況し、放たれる音像が唯一無比であることを、文面で伝え切るという離れ業を成し遂げている。まさしくこれこそが読書からはみ出していく体験である。
しかし、運命は残酷で、オクムラユウスケの身には次々と悲劇が襲いかかる。その物語が本書の重要な核となり、ライブハウスの狂騒と対比するように、人間の悲しみを体現していく。そして兄もまた弟の運命を受け入れ、ともに生きていく。弟あってこその自分だと改めて気づく。この兄弟の葛藤と愛に圧倒される。この兄弟愛を目の当たりにするだけでも本書を紐解く価値は途轍もなく大きい。
悲しみを抱えてこそ、ロックのノイズは激しさを増し、ソウルは磨かれ、ブルースは深く染み渡る。この2人が体現していることは、そんな音楽の本質ではないか。
人は皆、生きていく上でジレンマを抱える。
「しなければならないこと」と「したいこと」の狭間でもがきながら生きていくのである。義務や権利という、そういう理屈とは違う。オレたちは何のためにこの世に生を受け、生きるのか?という根源的な問いに近い。しかし、その根源的な問いを、皆なかなか直視しようとしない。しない故に好きでもないことをし続け、疑問も不満も封印し、我慢して生きていくのである。もちろんそんな人たちをオレは笑う気には全くなれない。オレもそんな一般ピープルの1人に過ぎない。しかし、誰しも心に燻らせていることの1つや2つ、心に抱えた傷なんて無数にある筈だ。だから、この本に出てくるフリーダムな人たちと、あなたとオレと、どこがそんなに違うだろう? この本を、ブードゥーラウンジを、ロックが好きなだけで世間に馴染めない連中の閉ざされた世界だと思うのならば、それは大きな間違いである。なぜならば、人は誰しも「はみ出し者」だからだ。
だからブードゥーラウンジの間口は狭くないし敷居も高くない。生きていれば誰でも扉を開けて歓迎してくれる筈だ。福岡の地で起きた局地的な喧騒、繰り広げられる人間模様は、実に楽しいがそれは決して遠くの特殊な出来事なんかじゃない。
そして補足すれば、もしあなたが普段ロックを聴かない人でも、福岡という地に縁が無い人でも、本書に触れることへの抵抗感は全て捨てて欲しい。登場するミュージシャンの音源を聴いていないと楽しめないのではないか、という不安も一切持つ必要は無い。ちなみに筆者は本書を読む前に関連音源は一切耳にしていない。つまり、本書は誰でも楽しめるということだ。
オレはもう、彼らを、ブードゥーラウンジの周りの人々を楽しそうで羨ましいなどとは思わない。むしろ、オレも生きなくちゃ、面白いことしなきゃ、というエネルギーをもらった。読んだ人それぞれの生き方を大いに後押ししてくれる、そんな稀有な本である。
何度も言うが、飛び交う言葉はうんこやチンチンなのに、圧倒的な感動があなたを待っている。そして感動的なのに、どこかアホ、どこか狂っていることが、この『ブードゥーラウンジ』の最大の魅力に他ならないのだ。
鹿子裕文はこの作品でその名を文学史に刻むことになる...かどうかはわからないが、少なくとも本書がオレたちの心に永遠に刻まれるマスターピースとなることは間違いない。
あー、もう、この本の魅力を伝えきれないオレの文章力、語彙力の無さがもどかしい!
- 『実像』秋山千佳 (2020年1月9日更新)
- 『グレタ たったひとりのストライキ』マレーナ&ベアタ・エルンマン、グレタ&スヴァンテ・トゥーンベリ (2019年11月7日更新)
- 『ナチ 本の略奪』アンデシュ・リデル (2019年10月3日更新)
-
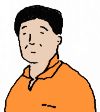
- ときわ書房志津ステーションビル店 日野剛広
- 1968年横浜市生まれ 千葉県育ち。ビールとカレーがやめられない中年書店員。職歴四半世紀。気がつきゃオレも本屋のおやじさん。しかし天職と思えるようになったのはほんの3年前。それまでは死んでいたも同然。ここ数年の状況の悪化と危機感が転機となり、色々始めるも悪戦苦闘中。しかし少しずつ萌芽が…?基本ノンフィクション読み。近年はブレイディみかこ、梯久美子、武田砂鉄、笙野頼子、栗原康、といった方々の作品を愛読。人生の1曲は bloodthirsty butchers "7月"。

