『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』石井光太
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
初めて子どもを産んで病院から退院するときのこと。世界中が、道沿いに咲く満開の花たちまでもが自分と子どもを歓迎している、と思った。
「子どもを産む」ということは親自身も喜び、周りからも祝福されることだと信じて疑わなかった。
望まれないまま生まれてきた子どもたちがいることは当然知っている。けれど、自分が体験してきた絶対的な幸福感がその現実への認識を薄めていた。
望まない、あるいは望まれない妊娠をしたとき、母親はどうすればいいのだろう。
人工妊娠中絶。文字通り、人工的に妊娠を中絶すること。現在は22週までの人工妊娠中絶は認められている。というか、逆に22週までしか認められていない。かつては28週でも行われていたという。この6週間の違いは何か。なぜ22週以上の中絶が禁止されたのか。
書いているのが石井光太さんだしタイトルや表紙も一見ノンフィクションっぽい。けれど、これはその法律の意味とそこから続く「特別養子縁組法案」の制定を勝ち取るまでの菊田昇医師の闘いを「小説」という形で描いている。小説でしか描けないことがあった、ということだろう。
普段の感覚でいくと、6週間なんてあっという間だ。6週間前の私と今の私の違いといったら、髪の毛が少し伸びたことと、体重が少し増えたことくらいか。
けれど、胎児の成長にとってその6週間は「人」になるかどうかという大きくて長い時間だ。
28週で中絶された胎児は時に生きてこの世に生まれてくる。生きているということは「出産」されたということで、つまり戸籍にその存在が記されるということだ。
中絶する親の多くは自分の戸籍にその出産が記載されないことを望む。では、生きて生まれてしまった胎児をどうするのか。
医者が、そっと、「殺す」のだ。
生きて生まれたことを無かったことにしてしまうのだ。暗黙の了解のうちに仕方ない事として行われていたという。
遊郭で育った菊田医師は妊娠や堕胎、そしてそれによる死を身近に経験していた。だからこそそんな悲しく悲惨な現実を変えたい、変えねばならない、という強い信念を持つようになる。
彼は悩みながら考える。危険な堕胎をせずひっそりと出産させ、生まれてきた命を子どもを欲しがる夫婦の実子としてあっせんすればいいのではないか。その時に必要な書類は偽造すればよい。それは法律に違反することだ。当然罪に問われることになる。けれど、菊田医師は、様々な圧力に屈することなく、自分の信念を曲げず、信じた道をがむしゃらに進み続ける。
組織を、そして国を動かし変えていくのは簡単なことではない。鋼の信念をもってしても、たった一人の力ではかなわなかったこの偉業。
妻や、彼の元でともに医院を守り切った看護師たち、そして支えてくれた友人たちの力あってこそ。関わった人すべてが素晴らしい。
でも、これで終わったわけではない。
「子どもなんて産まなければよかった」とわが子を憎む母親や、「自分なんて生まれてこなければよかった」と自分の命を呪う子どもがいる限り、この闘いは続いていくのだろう。
泣きながら読み終わった後、自分の中に小さくて強い何かが生まれたことに気付く。この小さくて強い何かを持ち続けること。忘れずにいること。いつかどこかで必要になったとき、必ず取り出すこと。
それがこの本から受け取ったバトン。
- 『ザリガニの鳴くところ』ディーリア・オーエンズ (2020年4月23日更新)
- 『文身』岩井圭也 (2020年3月26日更新)
- 『ドミノin上海』恩田陸 (2020年2月27日更新)
-
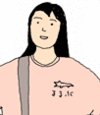
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

