『トリニティ』窪美澄
●今回の書評担当者●ジュンク堂書店滋賀草津店 山中真理
1960年代、高度経済成長期、女性の大半が結婚・出産を機に退職し、専業主婦となっていた時代。こんなに熱く生き抜いた女たちがいた。
トリニティとはキリスト教における三位一体を意味する。男・仕事・結婚・子どものうち、手に入れようとした三つのものとは。
本書は、ある出版社を舞台にして、昭和・平成・未来にまたがり、その激動の瞬間とともに、時代の寵児と言われたイラストレーター妙子、ライターの登紀子、主婦の鈴子の男・仕事・結婚・子どものうち選んだものと捨てなければならなかったものを描きながら、それぞれの人生のうねりを交差させ、熱い心を呼び起こさせる大河小説ともいえる物語である。
昭和三十九年、妙子は雑誌の表紙をレギュラーで描き始めるようになる。そして「結婚仕事子どもどれも自分は欲しい。すべてを手に入れたい」と願う。しかし、結婚生活の中には仕事という色が濃く、家族とのすれ違いで溝が生まれてくる。登紀子は結婚をし、ライターとして夢を追い続ける。鈴子は編集者にならないかという誘いをけり、出版社を辞め、専業主婦の道を選ぶ。
出版の変遷としても想いを馳せるところが。「読み手の半歩先を歩け」数歩先を歩いてしまえば読者はついてこない。情熱をかけた昭和の本づくり。そんな時代からイラストも文字も写真も雑誌を作るための道具という変遷が......小説と知りながら寂しく心に落とされた。日々、本に関わる人にとって、何かを感じるはずと考える。
特に圧巻は1968年「新宿騒乱」三人がくり出した場面。機動隊の放つ大量のガス弾の煙、それに対抗して学生たちが投げる火炎瓶。輝くネオンの下の無秩序状態、多くの叫び声が混ざり合い、ひとつのノイズとなって、三人の鼓膜を震わせ、登紀子が取材をし、妙子が絵を描く。
「楽しい!」
「こんな夜がずっと続けばいいのに」
三人の想いが結実した瞬間、何も重荷を背負うものではなく、魂の叫びが放たれた瞬間で、目に焼き付いて離れなかった。
妙子、登紀子は、晩年最先端の場から離れ、寂しい世界に身をおくことになる。三人はそれぞれどちらかを選んだ。そして、代わりがきかない存在、かけがえのないものになることを求め続け、闘ってきたのだと思う。
現代に生きる私達も仕事・結婚・子ども・男、選ぶものと捨てるものに迫られ、代わりのきかない存在になることを求め続けているのではないか。
これは私達の物語だ。
読者はきっと、自分の胸に手をあてることになると確信する。
- 『歪んだ波紋』塩田武士 (2019年5月16日更新)
-
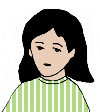
- ジュンク堂書店滋賀草津店 山中真理
- 生まれも育ちも京都市。学生時代は日本史中世を勉強(鎌倉時代に特別な想いが)卒業と同時にジュンク堂書店に拾われる。京都店、京都BAL店を行き来し、現在滋賀草津店に勤務。心を落ちつかせる時には、詩仙堂、広隆寺の仏像を。あらゆるジャンルの本を読みます。推し本に対しては、しつこすぎるほど推していきます。塩田武士さん、早瀬耕さんの小説が好き。

