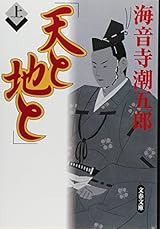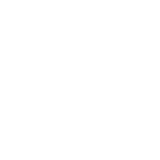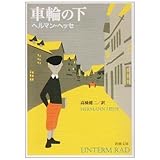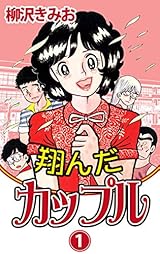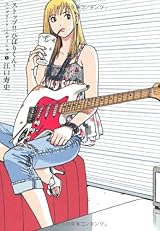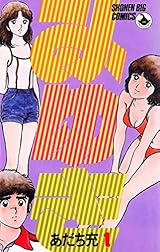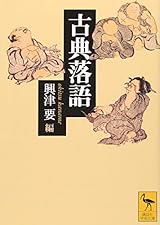作家の読書道 第278回:丸山正樹さん
2011年に手話通訳士、荒井尚人が主人公の『デフ・ヴォイス』でデビューした丸山正樹さん。同作や『夫よ、死んでくれないか』はドラマ化され注目に。つねに社会的に弱い立場の人を掬い上げる作風は、読書歴を含めどんな道のりのなかで育まれてきたのか。幼い頃からの遍歴をたっぷりおうかがいしました。
その3「高校時代の乱読」 (3/7)
――高校時代はいかがでしたか。
丸山:板橋の私立の男子校にいったんですが、殺伐とした、暗い高校生活でした。進学校なんですけれど当時はツッパリ(今でいうヤンキー)もいて、恐怖による統治みたいなことをやっていて。日常的に喧嘩もありました。あの高校生活が、自分にダークな面を持たせた要因だと思っているんですけれど。中学から剣道をやっていたので高校も剣道部に入りました。生徒は大体ツッパリか勉強君か体育会系の3つに分類されるんですけど、最初は私も一応体育会系にいたんですね。でも封建的な部活で、精神を鍛える目的なのか、詩吟をやらされたりして。先輩たちの前でやらされて、声が小さいなどといって正座をさせられて、しごかれて。それが嫌で2年生の時に仲間みんなで辞めたんですね。それはやはり、ひとつのことを成し遂げられなかったという挫折体験でした。今も体育会系なものに対して抵抗感があるのは、その頃植え付けられたのかもしれません。
通学に1時間15分くらいかかっていたので、その間本を読みましたし、家に帰ってからもそんなに勉強をしないで読んでいました。ただ、剣道部を辞めてからは、映画に夢中になりました。ほぼ毎日、学校帰りに池袋の「文芸座」か銀座の「並木座」に通う、という至福の日々でしたね。
――高校時代、小説はどんなものを読みましたか。
丸山:乱読で、日本の近代文学を片っ端から読みました。まあ本好きの正統的な読み方みたいなものです。夏目漱石、森鴎外、川端康成、谷崎潤一郎、島崎藤村、三島由紀夫、太宰治、宮沢賢治、石坂洋二郎...。漱石は『吾輩は猫である』や『坊ちゃん』よりも、青年の成長譚として『三四郎』『それから』『門』の三部作が好きでしたし、太宰はやっぱり多くの人と同じように、私も『人間失格』を読んで自分のことを書いているんじゃないかと思いました。太宰の道化とか三島の仮面といったものは、自分が内包している思いが投影されているように感じましたね。後に島田雅彦さんの『僕は模造人間』という小説を読んだときに「ああ、自分たちの世代の太宰が出てきた」と思いました。
日本史が好きだったし、大河ドラマも見ていたので、時代小説も読みました。海音寺潮五郎の『天と地と』、吉川英治の『宮本武蔵』、山岡荘八の『徳川家康』、司馬遼太郎の『竜馬がゆく』や『国盗り物語』など。
さきほどどうやって本を見つけたか分からないと言いましたが、考えてみると高校以降は、文庫に関しては各版元が出している出版目録を見ていたと思います。あれは読むだけで面白くて、宝の山のようでした。
詩歌も読みました。中原中也なんかは、高校生くらいの時に読むと、なにか直接入ってくる感覚がありました。それと、さきほど話した高村光太郎の『智恵子抄』、あとは北杜夫の流れで斎藤茂吉とか。
――歌人の斎藤茂吉は北杜夫のお父さんですものね。
丸山:高校の同級生が大学に入ってから現代詩を書き始めて、「ユリイカ」に投稿していたんです。その影響で自分も「ユリイカ」を読み、現代詩も読むようになりました。現代詩文庫という新書サイズのレーベルはかなり持っていますね。
――翻訳小説は読みましたか。
丸山:中学から高校にかけてですが、父親の書棚にあった世界文学全集を読んでいました。父親は全然本を読まないので、飾りで置いてあったんですよ。最初は難しいかなと思ったんですけれど、手に取ったら意外と読めたんですよね。そのなかでよく憶えているのがパール・バックの『大地』。舞台が中国なので身近で読みやすかったのかもしれません。すごくスケールが大きな物語の中に、貧困や差別や、知的障害のことが描かれていて。ドストエフスキーの『罪と罰』やヘッセの『車輪の下』やジッドの『狭き門』、ゲーテやツルゲーネフも読みましたが、いま真っ先に思い出したのが『大地』なので、無意識のうちに影響を受けたのかもしれません。
――漫画で印象に残っている作品は。
丸山:諸星大二郎を読んだのが高校時代かな。手塚治虫賞を受賞したデビュー作を読んですごいなと思っていたんです。決定的だったのは『暗黒神話』ですね。手塚治虫の『火の鳥』にも通じるような神話的で壮大なスケールの話で、ちょっと怖さもあって。諸星大二郎は自分の中で特別な存在でした。
高校時代か浪人時代の時に、少女漫画にもはまりました。くらもちふさこの『おしゃべり階段』を読んではまって、くらもちさんの作品は全部読みました。
――読んだきっかけってなにかあったのですか。
丸山:友達が教えてくれたのかな。剣道部時代の友達が、まあ硬派っぽい奴なんですけれど、そいつが「別冊マーガレット」を買ってくるのでみんなで回し読みしていたんですよ。とにかく『おしゃべり階段』が衝撃でした。男子校で恋愛経験が全くない中で、理想的な青春がここにある、って。漫画で人の心の機微をこんなに描けるのか、とも思いました。そこから少女漫画を深く広く読んでいったわけではないんですけれど、大島弓子や萩尾望都の漫画も読み、新しい世界を知りました。
ジュニア小説も高校時代によく読みましたね。彼女がいなかったので疑似恋愛的なものとして富島武夫にはまったんです。すごく純粋な世界が書かれていたので、後々、富島武夫が官能小説を書いていたと知ってショックだったんですよね(笑)。
疑似恋愛的な読み方としては、漫画で、柳沢きみおの『翔んだカップル』や江口寿史の『すすめ!!パイレーツ』や『ストップ!!ひばりくん!』、あだち充の『みゆき』や『タッチ』もはまりました。『翔んだカップル』は内容が面白かったんですけれど、江口寿史とあだち充はとにかくもう、登場人物に恋しちゃうくらい絵が可愛かったですね。
それと、本とは関係ないですけれど、お笑いブームにもどっぷりはまりました。19歳くらいの頃に漫才ブームがあったんですが、私はただ笑うだけじゃなくて、理論的なほうにいったんですよ。小林信彦の『日本の喜劇人』や、テレビ朝日のプロデューサーだった澤田隆治という人が書いている『私説コメディアン史』といった演芸関連の本を片っ端から読みました。落語も、聴くようになる前から興津要編の『古典落語』で読んでいました。