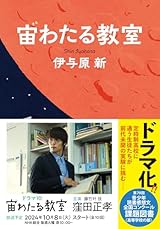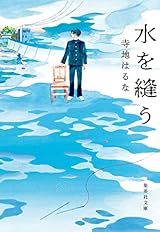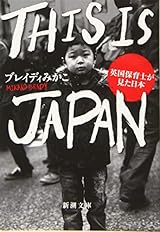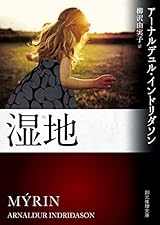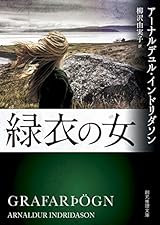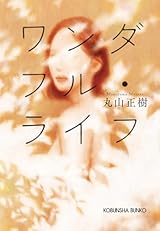作家の読書道 第278回:丸山正樹さん
2011年に手話通訳士、荒井尚人が主人公の『デフ・ヴォイス』でデビューした丸山正樹さん。同作や『夫よ、死んでくれないか』はドラマ化され注目に。つねに社会的に弱い立場の人を掬い上げる作風は、読書歴を含めどんな道のりのなかで育まれてきたのか。幼い頃からの遍歴をたっぷりおうかがいしました。
その7「最近の読書と今後の予定」 (7/7)

-
- 『縁を結うひと(新潮文庫)』
- 深沢 潮
- 新潮社
-
- 商品を購入する
- Amazon
――その後の読書生活は。
丸山:小説家になってからは知り合った、といっても私の場合ほとんどSNSでのお付き合いですけど、作家の本を読むことも多いですね。姫野カオルコさん『彼女は頭が悪いから』、葉真中顕さん『ロスト・ケア』、伊与原新さん『宙わたる教室』、寺地はるなさん『水を縫う』、深沢潮さん『縁を結うひと』、足立岬さんの『春よ来い、マジで来い』、水沢秋生さん『君が眠りにつくまえに』...。ブレディみかこさんは『THIS IS JAPAN--英国保育士が見た日本』以降の作品はすべて読んでいるし、木村紅美さんはデビュー作の『風化する女』から最新作の『熊はどこにいるの』まで全部読んでいます。
知り合いじゃないですけど、以前の「純文学系新人賞を読む」が最近また復活してきて、『最高の任務』や『本物の読書家』などの乗代雄介さんは最新の推し作家です。
――翻訳小説は読まれていますか。
丸山:最近は翻訳家読みになっていて、柴田元幸さんからの流れで岸本佐知子さんを知って、今は「岸本さんが訳したものなら読もう」という感じです。どれも面白いですよね。ニコルソン・ベイカーの『もしもし』や『中二階』とか、ミランダ・ジュライの『いちばんここに似合う人』とか。それとルシア・ベルリン。『掃除婦のための手引き書』や『すべての月、すべての年』といった短編集は、一篇一篇が短いのにどれもガツンときますよね。岸本佐知子さんには、エッセイも含めて、絶大な信頼を寄せています。
それと翻訳ものでは『湿地』『緑衣の女』などのアーナルデュル・インドリダソン。犯罪捜査官エーレンデュルのシリーズは、何森のシリーズに多少影響を与えているかなと思います。それと、『犯罪』などのフェルディナント・フォン・シーラッハの淡々とした筆致は、自分の目指すハードボイルドだったりするので参考にしています。
――ノンフィクションで印象に残っている作品はありますか。
丸山:シナリオライターを目指していた頃、なかなか入選しないのは題材が普通すぎるからかなと思ったことがあって。自分にしか書けないようなものを見極めなきゃいけないと考えた時に、自分には吃音や妻のこともあるし、障害のことを書こうと思ったんです。実は、『刑事何森 孤高の相貌』の「二階の死体」の、頸椎損傷の少女のお母さんが二階で殺されているという話はデビュー前に書いているんですよね。
それから『ワンダフル・ライフ』の「仮面の恋」に出てくる重度脳性麻痺の青年が、名前を偽ってネット上で知り合った女性に会いにいく話もデビュー前に書いているんです。あの話は実はモデルがいて。妻が行っている施設に脳性麻痺の青年がいて、最初のうち、コミュニケーションもとれないので、私は彼に知的な障害もあると思い込んでいたんですよ。でもメールアドレスを交換してやりとりするようになったら、とっても知的な文章で明瞭な会話を交わすことができて、びっくりして。本当に自分の偏見と無知が恥ずかしくなったんです。でもきっと、そういうことは自分だけじゃないよなと思って、小説にしようと思ったんです。でもうまく書けなくて。
それで、他の障害の人のことも知ろうと思い、いわゆる自閉症とか発達障害の人が起こした事件のノンフィクションをいろいろ読みました。そのなかのひとつが、佐藤幹夫さん『自閉症裁判 レッサーパンダ帽男の「罪と罰」』です。これがすごいノンフィクションなんですよ。路上で女性が刺殺され、捕まった青年が自閉症と軽度の知的障害と診断された事件について書かれている。犯人の育成歴とか、加害者の家族がその後どうなったのかに衝撃を受けました。こうしたことってみんな知らないことだよなと思った時に、小説に書いてみたらどうだろうと思って。障害者の内面って、みんな普段は全然関心がないけれど、事件を起こすとその内面や背景や動機をすごく追及される。だから、障害者が加害者になる話を書こうと思いました。私がわりと障害者が被害者でなく加害者になる話、誰もが被害者も加害者になりうるという話を書くのは、ここが原点かもしれません。
それと、山本譲司さん『累犯障害者』は、刑務所にいる障害者についてのノンフィクションで、このなか暴力団のろう者の話があるんです。そこではじめてろう者と日本手話ということを知りました。そういう意味では『デフ・ヴォイス』の原点ですね。
――1日のタイムテーブルは決まっていますか。
丸山:私は午前中型ですね。朝6時頃には起きて、食事の支度とか妻のケアを一通り終えてから、8時半くらいには机に向かっています。午前中にどれくらい書けるかが勝負です。午後からの予定は日によります。週3回介護ヘルパーが来てくれるので、その日は昼から出かけて打ち合わせだったり取材だったりをして、そうした仕事がなければ映画を観に行くかジムに行くか。ただ、外出する時もパソコンは常に持参して、用事が終わってから図書館や喫茶店で2時間程度は仕事をしています。家にいる日の午後も、妻のケアや家事のかたわら、資料を読んだり、調べ物をしたりはしますね。基本的に夜は仕事はしないです。
――そういえば、ボクシングジムに通われているとか。
丸山:小説家デビューした年、つまり40歳を過ぎてから始めました。「あしたのジョー」世代なので、子供の頃からボクシングの試合を見るのは好きで。いつか自分もやってみたいと思いながら実現できないでいたんですが、たまたま近所にボクシングジムを見つけたんです。すごく小さなジムだったのでコロナ禍の時に感染対策が難しくなり、それからは大きなジムに移りました。そこでブラジリアン柔術のコースがあってやってみたことで、『キッズ・アー・オールライト』が書けたところがありますね。今はそのコースをとる時間がなくなったので、自主トレみたいな感じでサンドバッグを叩いたりしています。
――今後の刊行予定はいかがですか。
丸山:東京創元社の「紙魚の手帖」という隔月刊の雑誌に『デフ・ヴォイス5』の連作を連載しているんですが、もうすぐ完結して来年単行本になる予定です。それが終わると、15年ぶりに文春で2冊目の単行本を出させていただけることになったので、それに取り掛かります。今、打ち合わせをしているところで、こちらも来年か再来年に刊行できればいいなあ、と。医療少年院や刑務所に勤務する精神科医の話を考えています。
(了)