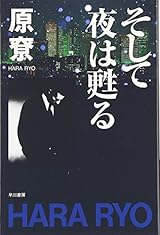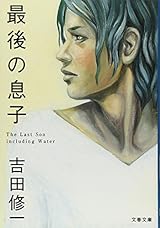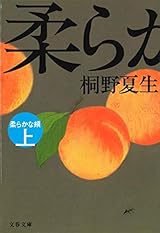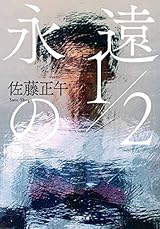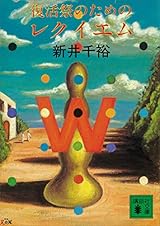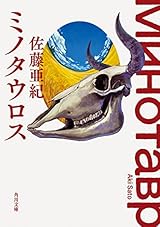作家の読書道 第278回:丸山正樹さん
2011年に手話通訳士、荒井尚人が主人公の『デフ・ヴォイス』でデビューした丸山正樹さん。同作や『夫よ、死んでくれないか』はドラマ化され注目に。つねに社会的に弱い立場の人を掬い上げる作風は、読書歴を含めどんな道のりのなかで育まれてきたのか。幼い頃からの遍歴をたっぷりおうかがいしました。
その5「影響を受けた2人の脚本家」 (5/7)
――映画やドラマもかなりお好きだったようですね。
丸山:ドラマはよく見ていて、実は、自分が作家としていちばん影響を受けたのは、倉本聰、山田太一という脚本家の両巨匠ですね。
私は15歳の頃に、山田先生の――どうしても「先生」をつけてしまうんですけれど――『岸辺のアルバム』の新聞連載を1回目から読んでいるんですね。毎日毎日楽しみで、連載で完結したら単行本でまた読んで、さらにドラマで見ました。当時15歳の少年が、主婦が不倫する話を楽しみに読んでいたっていう。山田先生のドラマは「男たちの旅路」や「沿線地図」、「想い出づくり。」や「ふぞろいの林檎たち」も好きですけれど、私の人生を決定づけたのは「早春スケッチブック」です。
ジェームス三木という脚本家が、「倉本聰は『What Is Life』で、山田太は『How To Live』だ」ということを書いているんです。中学生くらいの時にそれを読んで、私が感じていたのもまさしくその通りだと思いました。倉本さんは人生を丸ごと書く。人間の嫌なところも悪いところも、情けないところも。山田先生はもう本当に、人生どう生きるかっていうことを書く。
まず、山田先生の「沿線地図」というドラマを18歳の時に見たんです。主人公も18歳で、受験間近の優等生なんですが、ちょっと不良っぽい女の子を好きになってしまう。その子が「親に逆らわずに毎日学校行っていて楽しいの?」みたいなことを言うので影響されて、駆け落ちみたいにして家を出て学校を辞めるんです。それで二人で生活して肉体労働を始めるという、そういう話なんですね。それを見て、自分も親の言うこと聞いてレールを敷かれた人生歩いていていいのかと思いました。幸か不幸かその時は相手がいなかったので道を誤らずにすみましたけど(笑)
その次に、大学生の時に「早春スケッチブック」を見たんです。主人公は当時の私よりちょっと年下の青年なんですけれど、ほぼ同世代。彼は母親が結婚前に、別の男との間に作った子なんですね。その後母親が結婚した相手、つまり現在の父親は小市民というか。会社では上司に逆らわず、家で愚痴を言うような、いってしまえば小さい人間なんです。そんなある日、青年の本当のお父さんが現れる。山崎努さんが演じていて、フリーのカメラマンで、無頼を絵に描いたような強烈なキャラクターなんです。その父親が主人公に「お前こんな生き方していていいのか」と言うんです。「その気になりゃいくらでも深く激しく広く優しく、世界を揺り動かす力だって持てるんだ」ということを言うわけですよ。これについては、私は「ユリイカ」の山田太一特集に寄稿しています。
大学時代にそれを見て、自分のやりたいことをやろう、就職なんかするのはやめて脚本家になろうと思いました。本当に単純ですよね(笑)。
大学卒業後はバイトしながら脚本を書く生活に入ったんです。その後山田先生にお会いする機会もあったんですが、「弟子にしてください」と言えなかったのが悔いですね。でも心の中ではずっと、自分は山田先生の弟子だと思っています。
――倉本聰さんの作品は何がお好きだったのですか。
丸山:中3の時に「前略おふくろ様」を見たんです。いまだにあれが自分にとって最高のテレビドラマです。後々、大学の後半になって「早春スケッチブック」を見て山田太一派になるんですけれど、それまではどちらかというと倉本聰派でした。実は大学生の時に「北の国から」の最終回を見て、弟子入りしよう思って北海道の富良野に行ったんですよ。連絡先も何も知らなかったんですけれど、富良野に行けば有名人だから会えるんじゃないかと思って。そうしたら本当に泊まった民宿の女将さんが「倉本先生なら知ってるよ」と言うんです。「先生は今富良野にいないよ」って。でも先生の友達に連絡してくれて、その人のトラックで「北の国から」で作った丸太小屋に連れていってもらって、そこで一日番人をさせられました。東京から来たただの大学生なのに(笑)。一日観光客の相手をして、東京に帰ってきました。きっと私みたいな弟子志願の人間がたくさん来たんでしょうね、後に倉本聰は富良野塾を作るんです。もし私があの時倉本さんに会っていたら、きっと富良野塾の第一期生として共同生活して農業しながら芝居の稽古をして、今小説を書いていないので、会えてなくてよかったんでしょうね(笑)。
――では大学卒業後はバイトをして、脚本を書いて...。
丸山:バイトしながらオリジナルの脚本を書いてコンクールに応募していました。官公庁や企業が作る30分くらいの啓発教育もののビデオドラマを作る仕事をやり始めたので、それで生活していました。30代の時に一応Vシネマでデビューするんですけれど、泣かず飛ばすでした。
――その頃の読書生活は。
丸山:20代の頃は、純文学を読むことが多かったんですよね。新しい作家を発見する、みたいな感じで、純文学の新人賞の作品を続けて読んだりしていたんです。『群像』や『文學界』といった文芸誌を買って読んでいました。
それと、時期は不確かですが、社会人になってからハードボイルドにはまったんです。矢作俊彦さん『マイク・ハマーへ伝言』、原尞さん『そして夜は甦る』などの沢崎シリーズ、志水辰夫さんの『行きずりの街』、『いまひとたびの』とか。志水さんや原さんの作品はミステリのランキングで1位になったから知ったんだと思います。
あとは吉田修一さんですね。文學界新人賞受賞作の『最後の息子』からずっと読んでいました。新人賞受賞作を読んでいたと言いましたが、その一作を読むだけで終わる人もいれば、その後ずっと読み続ける人もいて、吉田さんは後者でした。その後出た長篇の『悪人』は、純文学というよりエンタメに近いと思って。私は純文学とエンタメの狭間にいる人が好きなんですよね。それが理想だという気もします。桐野夏生先生もそうですよね。『OUT』はエンタメだけれど、『柔らかな頬』はエンタメとして読むだけでいいのか、と思うし。打海文三さんの作品も、自分の中ではミステリの枠を超えています。特に『時には懺悔を』は、ご自身の息子さんの障害そのままミステリの題材としていて、ああ、こういうことをしてもいいんだと思いました。じゃあ自分もしてもいいのかな、と思ったところがありますね。
他にも、純文とエンタメの狭間にいる人はたくさんいますよね。町田康さんや川上未映子さんも最初は純文学として読んでいたけれど、エンタメとして読むこともできる。阿部和重さんも純文学だけど、映画を志していたこともあってかエンタメ要素がありますよね。他にも、絲山秋子さん、帚木蓬生さん、池澤夏樹さん、宮部みゆきさん、横山秀夫さん、重松清さん...。帚木さんの『閉鎖病棟』は自分が目指す小説の形のひとつですね。
――『閉鎖病棟』は読んで大号泣した記憶があります。
丸山:ですよね。私も、ああ、こういう小説を書きたいと思いましたね。簡単に言うと、困難な状況にある人たちを描き出していて、だけど小説として面白くて、感動があるっていう。そういうものが書けたら理想ですよね。
それと、太宰治賞を受賞した時からずっと読んでいるのが津村記久子さん。リアルタイムで単行本を買っています。面白くない作品がひとつもなくて、すごい人だなと思っています。細かい描写が本当にうまいですよね。文章を読んでいるだけでほれぼれするっていう。
やっぱり自分は、文書が上手い作家が好きなんだと思います。
佐藤正午さんも本当に文章が素晴らしい。『永遠の二分の一』からリアルタイムで全作読んでいますが、どの作品ももうずっと読んでいたくなる。至福の時ですね。最近の作家でいえば、早瀬耕さんの『未必のマクベス』を読んだ時に、自分がこれまで読んできて敬愛している作家たちと同じような性質を持った人が出てきたなと思いました。最初は淡い恋の話かと思ったら、すぐにぶっ飛んだ展開になっていく。あれもすごいセンスだなと思って。伊坂幸太郎さんもそうですけれど、文体や文章がちょっと特異な、他にいない作家だなと感じます。
新井千裕さんも文章が好きなんですよね。デビュー作の『復活祭のためのレクイエム』の時からリアルタイムで読んできた作家のひとりです。特に『忘れ蝶のメモリー』が好きですね。とにかく文章にセンスがある。
佐藤亜紀さんはまたちょっと違って、スケールの大きさに圧倒されます。『バルタザールの遍歴』とか。『ミノタウロス』、『吸血鬼』あたりから新刊をリアタイで読んでいます。日本で世界に通用する作家をひとり挙げよと言われたら、私は佐藤さんを挙げますね。世界的な作家だと思う。