コラム / 高橋良平
ポケミス狩り その17
「クロフツの巻」

何年か前のこと----消閑の気散じにと、隣室を埋めつくす本の山脈の一角をなすポケミス地帯から、気まぐれに『スターベル事件』(井上良夫訳・57年7月4版)を抜く。首をかしげながら読み終えて間もなく、なにかの会合の折り、東京創元社の戸川編集長(社長になってたかも)と顔をあわせたのをもっけの幸いと、もやもやした読後感を不平まじりに言い立てた。
すると戸川さん、迷惑顔もせずニコニコし、
「あれは抄訳ですからね」
と、一刀両断。こちらは、へへーっと平伏すばかり。ちなみに、創元推理文庫からは、『スターヴェルの悲劇』(大庭忠男訳)と原題直訳題で完訳版がでている。
そういえば、ポケミスにクロフツ初登場となった『スターベル事件』に、江戸川乱歩が寄せた解説「クロフツ小傳と諸家のクロフツ評」の終わりに、
〈この本は、故井上良夫君の訳筆になる昭和十二年、末広書房版の再出版〉
と断ってあったから、底本が戦前版ならばなおさら、抄訳なのは珍しくもない。気がつかなかったこっちが迂闊。抄訳、翻案も、わが国の翻訳文化だと考えているから、決してそれを否定するつもりはないが、にしても、この本はヘンだ。抄訳版の「スターベル事件」だけでは束不足と編集部が考えたのか、M・D・ポーストの短篇「アンクル・アブナー」を加えて(それでも、本文は160 頁に満たない)いるのに、乱歩さんの解説でまったく言及されていないのは、不思議。おまけに、『ハヤカワ・ミステリ総解説目録』の二度の増補版でも、この短篇はリストから漏れており、なぜかママコ扱いされている。
ともあれ、訳者の井上氏の名は、乱歩さんの『幻影城』の献辞----
〈この書を井上良夫君の霊前にささぐ
若し君が生きていたら、誰よりも熱心にこの本を読み、且つ
批判してくれるだろうと思う。十余年前、英米探偵小説の読
後感や探偵小説本質論について、非常識なほど長い手紙のや
りとりをつづけた、あの頃の楽しい思出から、私はそう信じ
ている。だから、私はこの書を先ず君に贈りたいのである。〉
で、つとに知られている。
関西の同人誌〈ぷろふいる〉の33(昭和8)年9月号にて、これまで原書で読破してきた数十作の長篇探偵小説を紹介する「英米探偵小説のプロフィル」の連載をもって探偵文壇に登場した、海外探偵小説通で名古屋に住む井上氏は、乱歩さんにとって、既訳・未訳を問わず、英米の探偵小説を俎上にあげて楽しく(文通で)本格論議のできる、無二の論敵でもあった。だが、評論・未訳作品紹介、翻訳に健筆をふるった井上氏は、戦争末期の45(昭和20)年4月25日、度重なる夜間の空襲で叩き起こされているうち、引いた風邪をこじらせ、肺炎で亡くなっている。享年36。
なお、交わした書簡は、乱歩さんが自分の分はカーボン紙を使った複写用箋で、井上氏の手紙と共にすべて保存しており、そこから中島河太郎氏が筆写した主な分は、中島氏の編集発行する探偵小説研究誌〈黄色い部屋〉の第5号(51年8月)から第12号(54年4月)まで掲載された。講談社文庫版[江戸川乱歩推理文庫]中にも収められているが、当該文庫を今は探し出すことができず、申し訳ないが書誌は不明。また、主な評論は、国書刊行会の叢書[探偵クラブ]の『探偵小説のプロフィル』で読むことができる。
乱歩さんが井上氏の逝去を知ったのは敗戦の翌年、未亡人に代わって氏の実姉からの死亡通知が届いたときだった。その手紙には、氏の蔵書を処分したい旨も書かれていた。
乱歩さんの『探偵小説四十年』の昭和21年度の章に、
〈[一月二十六日]一月二十六日夜出発、名古屋市に行き、井上ゆき子(良夫君未亡人)さんを訪ね、井上良夫君所蔵の英文探偵小説約百冊を譲り受ける。二十八日一番電車にて帰京す〉
と記しているが、同書の「井上良夫との文通」の項には、もう少し詳しく、
〈お悔みかたがた、リュックをしょって、私は名古屋へ出かけて行った。そのころは、汽車もボロボロで、その上非常に混雑していたし、荷物の運送なども心もとない時代だったので、リュックにはいるだけ詰めて、しょって帰るつもりだったのである。
井上君は英文の探偵小説を相当持っていた。それに、晩年には犯罪研究書に興味を持って、その方の珍本なども十数冊所蔵していたが、私はまだ読まない探偵本だけを譲り受け、残りの半分は、当時の「宝石」の岩谷書店の社長、岩谷満君に買ってもらうことにした。全部ほしかったのだが、そのころはまだ収入が少なく、私一人の力に及ばないので、岩谷君の助けを借りたわけである。今から思うと、あの中では犯罪史や犯罪研究書が最も値うちのあるもので、それらを入手しえなかったのを残念に思っている。譲り受けた本は、むろんリュックにはいりきらず、あとから送ってもらったのだが、当時私は西洋探偵小説に餓えていたので、一日も早く読みたいものだけをリュックに詰めたのである。岩谷君へも、あとからの文通で、鉄道便にして送ってもらった〉
"探偵小説の鬼"ぶりも窺える微笑ましいエピソードであるが、その3年後の49年5月に未亡人も亡くなり、独身で会社勤めの実姉は、井上家にはいって献身的に遺児ふたりの面倒をみたという。その井上家の金銭面の一助になればと、乱歩さんは抄訳と知りつつ、井上氏訳の末広書房版『スターベル事件』をポケミスで再出版したのだろう。

ポケミス解説中、クロフツの代表作『樽』の評価について、「亂注」として、
〈少くとも「樽」については、私はこれ(引用者注・読者に対して驚くほどフェアであること)と逆の考え方をしている。「樽」では一応データが示されるけれども、それが探偵の思い違いだつたりして、最後までデータの内容が確定せず、読者は安心して推理競走が出来ないような感じを受ける。犯人の方は独創のある天才型が多いが、探偵は平凡人で、よく間違いをやるので、その探偵の観察したデータは中途で変ることがあり、信用が出来ないのである。私は従来から屡々このことを書いている〉
ふ〜ん、と思ったぼくはさっそく、信頼できるテキストの完訳決定版と解説で都筑道夫さんが誇っているポケミス版『樽』(村上啓夫訳・67年10月4版)のページを開いた。
鉄道土木技師のクロフツが、長患いの療養中の慰みに書きはじめ、あげくデビュー作となった『樽』は、ご存じのように、イギリスの波止場に着いたブドウ酒の樽の中から女性の死体が発見され、樽の輸入経路を追っての犯人探しの物語。ただし、乱歩さんは平凡人の探偵としか書いていないが、探偵役はひとりでは、ない。ドーヴァー海峡をはさんだ英仏両国にわたる犯罪を、ロンドン警視庁の警部、パリ警視庁の警部、フランスの私立探偵らが着実に捜査してゆく、その経緯が語られるのだ。だから、たとえば"87分署"シリーズのご先祖さま的な警察小説に分類されるべきで、探偵vs犯人のミステリではないのだから、乱歩さんの指摘は、ないものねだりに思えてしまうのだが......。
だからか、都筑さんの『樽』解説中の、〈手法がリアルであり、内容が伝統的な大衆小説のロマンチシズムを持つているために、この『樽』はもちろん、クロフツの作品は、長い年月をへだてても、ほかのトリックの独創だけが生命の探偵小説にくらべて、読んで古さを感じさせないのである〉という言葉が、すんなり呑みこめる。
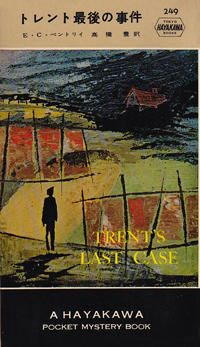
ものはついで、『スターベル事件』の解説中で触れられている、同時代の"長篇探偵小説中の輝かしい二つの明星"として、『樽』と並ぶE・C・ベントリイの『トレント最後の事件』(高橋豊訳・57年11月・重版表示なし)を手にとってみる。この作品、前記の文通中、
〈殊に二人の間に烈しい論争を起したものはメイスンの「矢の家」とベントリーの「トレント最後の事件」であった。井上君は「トレント」よりも「矢の家」を遙かに高く買い、私はその逆に考えていたので、各々一方の長所をあげ一方の欠点を列挙して何回となく論争の手紙をやりとりした〉(江戸川乱歩「名古屋・井上良夫・探偵小説」〈新探偵小説〉47年4月号=光文社文庫版『江戸川乱歩全集 第26巻 幻影城』所収)そうだ。
『トレント最後の事件』が書かれたのは、オクスフォードを卒業したベントリイが、法律家から〈デイリイ・テレグラフ〉紙のジャーナリストへと転身する時期で、執筆のきっかけは、名門セント・ポール・スクールのパブリック・スクール時代からの親友、G・K・チェスタートンが、『木曜日の男』を彼に捧げてくれたことだった。そのお返しに想を練って結実した本作は、「ギルバート・K・チェスタートン」に捧げられ、執筆の理由も目的もしっかり献辞に書かれている。
本書の探偵フィリップ・トレントは、足を使って地道に捜査するクロフツ警部とは異なり、本業は画家だが、探偵の才に恵まれているため、新聞社に依頼されて事件を捜査、その推理と突き止めた犯人を新聞記事で発表してきた。数々の難事件を解決し、名探偵の誉れ高いトレント。その名探偵"最後の事件"という設定がデビュー作とは、ちょいと人をくった感じだが、それよりも驚くのは、小説の中盤で、その名推理によって真犯人が判明してしまうことだ。では、後半には何が書かれているのかというと......。
本書の裏表紙に載った乱歩さん曰く、
〈トリックに極めて大胆な創意があり、犯人の意外性はルルウの『黄色い部屋』クリスティーの『アクロイド殺し』にも比すべく、本格物としても劃期的な名作であるばかりでなく、多くの本格物に欠けている感情的な要素がこれには豊富に取入れられ、恋愛探偵小説とも云うべき構成になっている。しかもその恋愛が謎と論理の邪魔になるどころか、却ってそれを一層面白くしている点、フィルボッツの『赤毛のレドメイン』などと共に稀有の作品ということが出来る〉
黄金期の長篇探偵小説への愛をこめつつ、探偵をロマンティックに"人間化"する批評的パロディ(ベントリイはナンセンス詩集もだしている)というのが、ぼくの読後感である。
蛇足。『トレント最後の事件』巻末解説の末尾に、[三一・四・二四・編集部 田中潤司]とあり、日付からして、〈EQMM〉創刊直前、田中氏が退社する間際に書かれた一文のようだ。
1959(昭和34)年・上半期[奥付準拠]
1月30日(HPB 463)『死者のノック』J・D・カー(村崎敏郎訳)
1月30日(HPB 466)『死刑執行人のセレナーデ』W・アイリッシュ(高橋豊訳)
1月30日(HPB 468)『水晶の栓』M・ルブラン(三輪秀彦訳)
2月15日(HPB 469)『緊急深夜版』W・P・マッギヴァーン(井上一夫訳)
2月28日(HPB 470)『ハイヒールの死』C・ブランド(恩地三保子訳)
2月28日(HPB 472)『猫とねずみ』C・ブランド(三戸森毅訳)
2月28日(HPB 473)『十日間の不思議』E・クイーン(青田勝訳)
3月15日(HPB 471)『ゴルフ場殺人事件』A・クリスティー(田村隆一訳)
3月15日(HPB 475)『ギャラウェイ事件』A・ガーヴ(福島正実訳)
3月25日(HPB 476)『死の序曲』N・マーシュ(瀬沼茂樹訳)
3月30日(HPB 474)『はなれわざ』C・ブランド(宇野利泰訳)
3月30日(HPB 477)『新聞社殺人事件』A・ガーヴ(中桐雅夫訳)
3月31日(HPB 478)『恐怖のはしけ』E・リード(加島祥造訳)
3月31日(HPB 479)『マローン御難』C・ライス(森郁夫訳)
4月15日(HPB 480)『七面鳥殺人事件』C・ライス(小笠原豊樹訳)
4月15日(HPB 481)『貴婦人として死す』C・ディクスン(小倉多加志訳)
4月25日(HPB 483)『赤い箱』R・スタウト(佐倉潤吾訳)
4月25日(HPB 485)『パンチとジュディ』C・ディクスン(村崎敏郎訳)
4月30日(HPB 467)『消された時間』B・S・バリンジャー(森郁夫訳)
4月30日(HPB 486)『検事踏みきる』E・S・ガードナー(宇野利泰訳)
4月30日(HPB 487)『検事卵を割る』E・S・ガードナー(平出禾訳)
5月15日(HPB 484)『青列車の秘密』A・クリスティー(田村隆一訳)
5月31日(HPB 303)『Zの悲劇』」E・クイーン(砧一郎訳)
5月31日(HPB 488)『傾いたローソク』E・S・ガードナー(尾坂力訳)
5月31日(HPB 489)『笑ってくたばる奴もいる』A・A・フェア(田中小昌実訳)
6月15日(HPB 490)『雲をつかむ死』A・クリスティー(加島祥造訳)
6月15日(HPB 491)『メッキの神像』C・ディクスン(村崎敏郎訳)
6月15日(HPB 492)『自宅にて急逝』C・ブランド(恩地三保子訳)
6月15日(HPB 493)『ビッグ4』A・クリスティー(田村隆一訳)
6月15日(HPB 494)『嘘から出た死体』A・A・フェア(田中小昌実訳)
6月30日(HPB 495)『カウント9』A・A・フェア(宇野利泰訳)
