『犬がいた季節』伊吹有喜
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
「伊吹さんが今度コーシローの話を書かれるんですよ」
と、担当の営業さんから聞いたとき「びえーっ!?」と叫んだ覚えがある。だって、コーシローですよ。高校に住んでた犬の話ですよ、あの伊吹さんがそんなマイナーな話題を書いちゃうんですか!?と。
三年前に『彼方の友へ』が本屋大賞にノミネートされなかったことに憤慨した名古屋の書店員仲間たちと「乙女の友大賞」という賞を勝手に作って勝手に表彰させていただいたときの、少し後のことだったと思う。
コーシローというのは四日市にある進学校に住みついていた雑種の犬の名前で、実際には昭和49年から60年までの12年間「在籍」していた。それを伊吹さんが平成から令和にかけての物語として紡いだのである。
「小説推理」(双葉社)に連載されていたこの小説をゲラ(原稿を本番のレイアウトに流し込んだ校正刷りの紙の束)で読んだとき、なんていうか、もういろんな思いがあふれ出てきて勢いに任せた無駄に熱い感想を担当営業氏に送りつけてしまった。無駄に熱くて無駄にプライバシーダダ洩れの感想を。
なぜかそこまで熱くなったのか。
それはこの小説のモデルになった高校が自分の母校であり、私自身もコーシローと共に三年間過ごした生徒だったからだ。
卒業して何年も何十年も経って忘れていたあの頃の思い出に溺れそうになってしまったのだ。
楽しい事ばかりじゃなかったあの三年間。友だちのこと、家族のこと、勉強のこと、進路のこと、恋のこと。そんなあれこれに悩んだり傷ついたり、それでも笑っていたあの頃のことが、ここにそのまま描かれていたから。
ここではないどこかへ行きたい、誰も知らない街で暮らしたい。そういう思いを、地方都市に住む多くの18歳が持っているだろう。
いまだ何者でもない自分が何者かになるために遠くへ行きたい、そんなあの頃の思いが心のどこかから飛び出してきた。
あの頃見ていた未来が過去になった今、私のあの青い思いはどこへ行ってしまったんだろう。
毎年四月に入学してきた生徒たちは三年後学校を去っていく。昭和63年度から平成11年度の5人の卒業生たちの、それぞれの日々と旅立ち。コーシローが見ているのは高校にいる姿だけ。けれど各章の最初と最後にコーシローの語りが入る。これがいいんだ。人の言葉がだんだんわかっていくコーシロー。匂いでわかる思い。伝えたいことがうまく伝わらなくてもどかしかったりもするけど、それでもなんとなく伝わる感じ。
最初に優しくしてくれた優花を待ち続けるコーシローの姿がいたいけでけなげで。子犬と成犬の間くらいだったコーシローが少しずつ年を取っていく姿。待ち続けた優花との再会、そして...というところはぜひハンカチを用意して読んでいただきたい。
それぞれの18歳。人生が大きく変わる時。
何かを選ぶために何かを捨てる。未来への一歩を踏み出す勇気はあきらめる強さも含んでいる。
あの時見ていた未来の自分が、笑顔の過去になるように。私たちはそれぞれの心の中のコーシローに問い続けながら歩いていくのだろう。
- 『自転しながら公転する』山本文緒 (2020年10月22日更新)
- 『星月夜』李琴峰 (2020年9月24日更新)
- 『アンダードッグス』長浦京 (2020年8月27日更新)
-
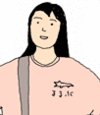
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

