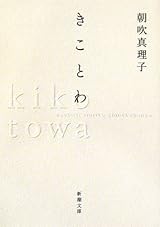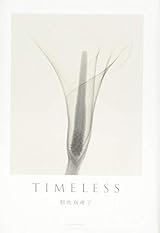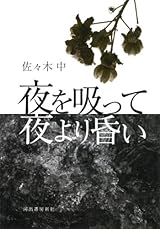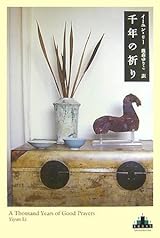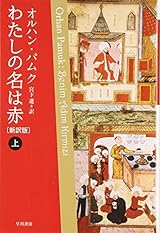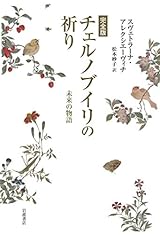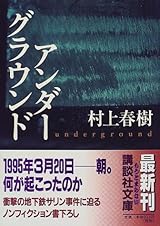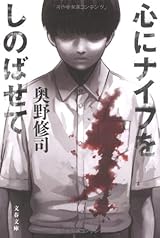作家の読書道 第230回:一穂ミチさん
短篇集『スモールワールズ』が大評判となり、直木賞にもノミネートされている一穂ミチさん。文体も形式も人物造形も自在に操って読者の心を揺さぶる一穂さん、同人誌での二次創作からBL小説でプロデビュー、そこから一般文芸へと活動の場を拡張中。漫画も小説もノンフィクションも幅広いジャンルを読むなかで惹かれた作品とは? さらにはアニメや動画のお話も。リモートでたっぷりおうかがいしました。
その6「「分からないけれど好き」が好き」 (6/8)

-
- 『お縫い子テルミー (集英社文庫)』
- 栗田有起
- 集英社
-
- 商品を購入する
- Amazon
――大学を卒業した後は就職されたのですか。
一穂:就職して働きながらオタクをしていました。その頃は何を読んでいたかな...。年代は定かではないんですが、栗田有起さんの『お縫子テルミー』がすごく好きでしたね。
大学時代から変わらず今も有栖川先生はずっと追いかけているし、高村先生も読んでいますが、大人になってからは一人の作家さんの作品を全部読むというより、あれもこれもつまみ食いしていますね。
――読書記録はつけていますか。
一穂:いや、全然つけていないですね。続かないんです。でも、一応、普段書いている日記に読んだ本のタイトルだけでも入れるようにはしています。読み返すことはないので、把握していないんですけれども。
――日記はずっとつけているんですか。
一穂:ここ15年くらいですかね。2、3日分をまとめて書くこともありますが、毎日つけています。もう習慣になっているので書かないと気持ち悪いんです。たいしたことは書いていないですよ。今日は何を食べたとか、どこに行った、くらいで。あとは、週刊占いみたいなものをコピペして貼っておいて、翌週に見返して「この週は当たっていたのか」って確認します。
――結構当たってます?
一穂:自分からこじつけにいっちゃうんですよね。「これってこういうことだよね」って。自分から当たりにいってます(笑)
――ずっと読んできている作家の作品以外、本はどのように選んでいましたか。
一穂:本屋でジャケ買いすることが多いですね。帯のあらすじ紹介とか。オタクなので、好きな紙を使っていたら買っちゃうっていうのはありますね。特殊紙を使っていたり、装幀に凝っていたりすると買いたくなります。
――装幀がすごく好きなのって、どんな本ですか。
一穂:蜂飼耳さんの詩集『食うものは食われる夜』とか。菊地信義さんの装幀です。菊地さんのドキュメンタリーが公開された時、観に行ったらサイン会があったのでサインももらったんです。「蜂飼耳さんの詩集持ってます」って言ったら、「ああ、あれね。凝りすぎちゃって重版かからないんだよね」みたいなことを言っていて。お金がかかりすぎて刷れないということですよね。蜂飼さんはエッセイもとても好きです。朝吹真理子さんもそうですが、ああいう静謐な感じのエッセイが好きです。
朝吹さんは小説も好きです。たとえば『きことわ』はなんともいえないふわふわした感じがある。プールの後にとろとろっと眠くなる時のような気持ちよさがあるんです。読んでいて眠たいという意味ではなく。ああいう、世界にたゆたう感じが好きですね。『TIMELESS』も素晴らしかったですし。
佐々木中さんの小説も好きでした。『しあわせだったころしたように』とか、『晰子の君の諸問題』とか『夜を吸って夜より昏い』とか。佐々木さんの本って、私にはかなり難易度が高いんですけれど、「よく分からないな」と思って読んでいると、どこか刺さるところがあるんです。私にとっては「分からないけれどもなんか好き、楽しい」というカテゴリーですね。
――海外小説は読みますか。
一穂:イーユン・リーの『千年の祈り』とかはすごく好きですね。文章が端正で美しい。新潮クレスト・ブックスはマットPPを使った装幀もすごくいいですね。他にはキャスリン・ハリソンの『キス』やベルンハルト・シュリンクの『朗読者』なども好きででした。
海外でいうと、毎年、ノーベル賞文学賞の人もちょっと気になったら読んだりしていて。そのなかではドリス・レッシングが結構好きです。とても読みやすい方だと思います。
その前年の2006年に受賞したオルハン・パムクの『わたしの名は赤』(※『わたしの名は「紅」(あか)』という邦題もある)は、語り手がどんどん変わっていくんですよ。イスラムのオスマン帝国の話で、近代化やキリスト教と衝突している状態で。イスラムの細密画は厳密にお手本が決まっていて、それをなぞるのが仕事みたいなことが書いてあって、ああ、オスマン帝国時代の芸術は自分の個性を出すものじゃないらしいんだなと思って。優れた絵師に対してアラーはご褒美に目を潰してくださる、みたいな描写があるんですよ。要するに、目を瞑っても描けるくらい熟練することが素晴らしいという。やっぱり、本を読んでいるとそういう、自分が考えたことのない概念に触れる喜びがありますね。ヤスミナ・カドラさんという方の『テロル』という小説もそうでした。イスラエルのテルアビブで妻が首謀者となって自爆テロをして、夫が「なぜだ」となって真相を探ろうとする話です。
小説ではないんですけれど、スヴェトラーナ・アレクシエービィチの『チェルノブイリの祈り』とかはすごくしんどい内容だけれど、すごく好きです。
――ノンフィクションもよく読まれるのですか。
一穂:そうですね。わりとノンフィクションやルポ系も好きです。忘れられないのは、村上春樹さんの『アンダーグラウンド』。それと、事件ものって読んでいて辛いんですけれど、奥野修司さんの『心にナイフをしのばせて』という本は、高校生の男の子が校内で刺殺されるという事件のその後を追ったノンフィクションです。被害者のご家族が突然お兄ちゃんが同級生に首を切られて殺されたと知らされるところから、家族がどういうふうに壊れていって、今はどういうふうにしているのかとか。加害者の少年がその後どうなったのかという話もあって。すごく辛い話なんですけれど、そういうノンフィクションやドキュメンタリーはよく読みます。
あと、ノンフィクションではないんですけれど、桐野夏生さんの『グロテスク』がすごく好きなんですよね。東電OL殺人事件を下敷きにして、昼は地味なOLで夜は売春をしていた女性の目から見た事件のフィクションを描いているんですよね。あれは「光り輝く、夜のあたしを見てくれ」って台詞が強烈に心に残っています。
――ああ、本の帯にもその言葉がありましたよね。
一穂:桐野さんは『柔らかな頬』もすごく好きなんです。あれは本当にきつい内容ですが、それでもぐいぐいと読ませてしまうからすごいなと思います。
――さきほどの『アンダーグラウンド』は1995年の地下鉄サリン事件の関係者に話を聞いたものですよね。それで連想してしまったのですが、同じ年に起こった阪神淡路大震災の時は大丈夫だったんですか。
一穂:自分に関しては、被害らしい被害はなかったです。大阪市内に住んでいて、体感的にはありえないくらい揺れたんですが、電気もすぐに通ったので「今日は学校に行かなくていいみたいだな」くらいの感じで。自転車で梅田を走り回ってみたら、地面がちょっとひび割れていたりしているんだけれど、バス乗り場にスキー板を持った人が並んでいて「ああ、スキーに行くのか」と思ったりして。まだネットがなかったので、その時点で神戸の状況を知らなかったんですよ。お昼になってニュースを見たら、神戸のほうからもくもくと黒煙が上がっていて、夜になっても全然消えずに、真っ暗な街の中に火の手が上がり続けている。それを見てようやく「とんでもないことになったんじゃないか」と思ったのを憶えています。
そういう意味では、ネットを通じてすべてがあからさまだった3・11のほうがインパクトは大きかったです。そういう災害の光景を直に見るようになったのって、スマトラ島沖地震くらいからのような気がします。報道の仕事ではない人が撮ったものが、当たり前のようにどんどんネットにあがってくる。その頃から、災害ってどんどん生々しくなっていった気がします。
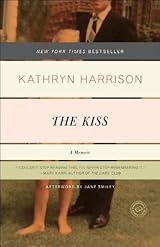
-
- 『The Kiss: A Memoir (English Edition)』
- Harrison, Kathryn,Smiley, Jane
- Random House
-
- 商品を購入する
- Amazon