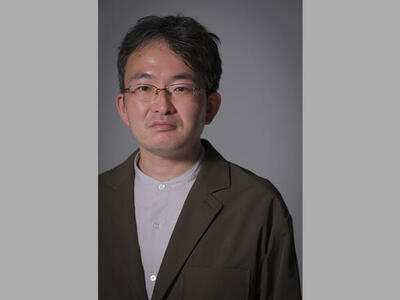
作家の読書道 第268回:潮谷験さん
2021年にメフィスト賞受賞作『スイッチ 悪意の実験』でデビューして以降、斬新な設定とフーダニットを組み合わせたミステリーで楽しませてくれている潮谷験さん。幼い頃からミステリー好きだったのかと思いきや、意外にも作家を志すきっかけは司馬遼太郎さんの『項羽と劉邦』で、歴史小説を書こうとしたのだとか。そんな潮谷さんの読書遍歴、デビューの経緯、最近の読書生活とは?
その2「歴史小説家を目指す」 (2/7)
――潮谷さんは京都ご出身ですよね。京都は新刊書店も古書店も多いイメージがあります。
潮谷:はい。ただ、私は京都の中心部ではなくて、中心部まで電車で10分くらいのところに住んでいたんです。なので、ベストセラーなら近所の本屋さんにあるけれど、そうではない本は電車に乗って買いに行くという環境でした。街の図書館を使うという発想はなかなか子供の頃ははなかったです。小中学生の頃は電車代もなく、気軽に中心部までは行けないので、なにかのついでに行った時にちょっと本屋さんに寄るとか、古本屋さんで立ち読みするくらいでした。やっぱりでも、当時に比べると本屋さんの数はすごく減っている印象です。
――高校時代の読書はいかがですか。
潮谷:純文学が面白いかな、と思った時期がありました。吉行淳之介の「童謡」が高校の教科書に載っていたんです。吉行さんの作品は全部そうだと思いますけれど、すごく文章のリズム感がいいですよね。それで吉行さんの短篇集を読んだりしました。自分も書く時は常にああいうリズム感がベストなんじゃないかと思って書いているところがあります。
高校にはわりと大きめの図書室があったんです。そこに横山光輝さんの『三国志』が全60巻並んでいたんですよ。『ドラゴンボール』のような漫画は置いていないけれど、そうしたちょっと学べそうな漫画は置いてあったんです。それで横山さんの『三国志』を読破した後で、関連作品の紹介で横山さんの『項羽と劉邦』という漫画もあると知ったんですね。図書室に横山さんの『項羽と劉邦』はなかったんですけれど、家の本棚を見ていたら、司馬遼太郎さんの『項羽と劉邦』の上巻だけがあって。親が買ってきて読まずにそのままになっていたようです。横山さんの漫画の原作というわけではないけれど同じ話だろうなと思って、せっかく家にあるんだから読んでみることにしたんです。ここではじめて歴史小説を読みました。上巻を読み、残りは中古屋さんで揃えました。
――『項羽と劉邦』を読んでみて、いかがでしたか。
潮谷:やっぱり司馬遼太郎さんなので当然なんですけれど、流れに圧倒されたといいますか。2000年以上前の出来事なのに、今の情景のように生き生きと描かれている。反乱が起きて、項羽と劉邦が台頭して、だんだん軍勢が出来上がっていくんですけれど、個人の努力だけではないんですよね。飢餓の時代だったので、人々が食べさせてくれる人を求め、勢力のある人のもとに集まってくる。そういうところに歴史のダイナミズムみたいなものを感じました。特に司馬遼太郎さんは歴史の中の人物に関して、ところどころ感情移入したかと思ったらすごく突き放した目線で見たりしていて、全体で見ればフラットな視線であるところが格好いいなと思いました。
――司馬さんを読んで、ご自身にも変化があったそうですね。
潮谷:はい。自分でも歴史小説を書いてみたいと思いました。中国史は『三国志』関係だと小説も結構出ているんですけれど、他の時代の小説はあまり出ていなかったので、図書館などに行ってどの時代だったら書けるんだろうと調べていきました。ここから歴史書に入って、春秋戦国時代を書いた『史記』とか、歴史書のほうの『三国志』を読んだりしました。それで、歴史小説を書きたいとは思ったけれども、なかなか取材が大変だということが分かったので、もうちょっと勉強しようと思って。この時点で歴史小説家になりたいという気持ちがはっきりして、大学受験でも東洋史学があるところを選びました。
――潮谷さんといえばメフィスト賞出身のミステリー作家というイメージなのに、まさか司馬さんきっかけで歴史小説を目指されたのが出発点だったとは。ちなみに書きたいのはやはり、日本史ではなく中国史だったのですか。
潮谷:そうです。中国は国の興亡が激しいので、歴史を書くならやっぱり日本史よりも中国史のほうが面白いんじゃないかな、と思っていました。それに日本史だと戦国時代の武将も有名なので、その人物がどういう末路を迎えるか読者もある程度知っていますが、中国史となると幅が広いので、その中から誰かピックアップして書くと面白いんじゃないかとも思いました。
司馬さんはあまり中国史は書かれていないので、宮城谷昌光さんの中国史小説をいろいろ読むようになりました。その頃は春秋戦国時代を主に書かれている時期でした。特に面白かったのが『晏子』。それは書き方が他とは違うというか。晏子は春秋時代の君主の臣下で、聖人君子として立派な生き方をした人。その人の清廉潔白な生き方が描かれるんですけれど、宮城谷さんの作品って、その時々で脇役が活躍して、それが主人公が埋もれるくらい面白いんです。晏子がわりとちゃんとした生き方をする一方で、その国で同じ人物が三回くらいクーデターを起こすんですが、そっちのキャラクターの掘り下げ方もものすごく面白かった。
――大学の授業は面白かったですか。
潮谷:「ここは小説に活かせるんじゃないかな」などと思いながら授業に出ていたんですけれど、やっぱり実際の研究とエンタメは違うなと思いました。あまりに深く掘り下げると小説として書けなくなっちゃう、みたいなところもありましたし。
今は日本語訳された中国の歴史書も増えましたが、当時はそれほどでもなかったんです。劉邦が前漢王朝を開いて、その400年くらい後に三国志の時代になりますが、当時私が考えていたのが、その間の時代の、後漢王朝を開いた光武帝の話だったんですね。日本に「漢委奴国王」の金印をくれた人で、その人を主人公にした小説がなかったので自分で書いてみようかなと思って。でも当時はその時代について翻訳された歴史書が見当たらず、断念しました。
本当は在学中に研究をしつくして、歴史小説を1冊書いてデビューしようという甘い見通しを立てていたんです。でも無理っぽいなと思い始め、いったん夢を封印して就職活動をしました。そのあたりで、歴史小説から目を離して、推理小説や一般の小説を読みはじめました。
――学生時代はサークル活動などもされず、小説を書くことに力を注いでいたのですか。
潮谷:バイトとかもしつつ歴史書などを読んでいたんですけれど、途中で情熱が落ちていったので...。当時の学生っぽい、そんなに頑張っていない学生という感じでした(笑)。
――学生時代に読んで印象に残った小説はありましたか。
潮谷:一人の作家を集中して読んだりはしなかったのですが、その頃読んで面白かったものでいうと、ゴールディングの『蠅の王』とか、ロートレアモンの『マルドロールの歌』とか。『マルドロールの歌』は散文っぽい詩と小説の中間くらいの内容で、空から追放された悪の化身が悪の限りをつくす話で、シュルレアリストの人からバイブルのように見なされている作品です。あまりにシュルレアリスム的な作品だと意味が分からなくなりますが、これはギリギリのところでエンタメとして成り立っていて、その感じがすごく面白いと思っていました。
歴史の本を読むうちに、世界史の出来事を一年ずつ新聞記事のように紹介していく「歴史新聞」というムックみたいな本を見つけたんですが、そこで『マルドロールの歌』が紹介されていたので読んだんです。
――中国史だけでなく、世界史に目を向けてらしたんですね。
潮谷:中国史を追究していくと、たとえば中国と国境が接しているロシアに目を向けたりするようになって、広がっていきました。
――新作の『伯爵と三つの棺』もフランス革命直後のヨーロッパの架空の国が舞台ですよね。なので世界史がお好きだったんだろうなとは思っていました。
潮谷:それは大学を卒業してからの話になるんですけれど、『ナポレオン ―獅子の時代-』という長篇漫画を読んだことが大きいです。20年くらい連載して、つい最近完結しました。少年画報社から出ていたんだったかな。長谷川哲也さんの作品で、タイトル通りナポレオンやフランス革命を中心とした話ですが、ナポレオンと対決するオーストリアの外交官のメッテルニヒやイギリスの軍人もピックアップされているんです。ナポレオンってある意味勝ち続ける天才なんですけど、そのナポレオンをどうにかしようと苦心する他国の人の話もすごく面白かった。それでフランスの周りの国のほうに興味がわき、メッテルニヒの伝記を読んだりしました。ひょっとしたらフランスよりもフランス革命に影響を受ける周りの国のほうが面白いんじゃないかと思い始め、それが今回の『伯爵と三つの棺』に繋がっている感じです。
――大学時代、ご自身で小説は書いていたのですか。
潮谷:純文学みたいなものを時々書いていたんです。でも、純文学は落としどころが見つけづらくて、全体像が作り上げられなくて。書き始めてもこれをどうしたらいいのか分からなくて、断念しました。
――純文学的な作品はいろいろ読んでいたのですか。
潮谷:有名どころでいうと堀辰雄さんの『風立ちぬ』とか。海外でいうとヘルマン・ヘッセの『デミアン』や、ジャン・コクトーの『恐るべき子供たち』とか。どちらかというと、海外文学はスケールが広いものよりも、わりと人間関係の狭いところで完結している小説のほうが好みだった気がします。
それと自分で書いていたものでいうと、酒見賢一さんの日本ファンタジーノベル大賞受賞作の『後宮小説』を読んだら面白かったんです。あれは中国のような架空の国の話ですよね。ああいう感じでいろんな要素を入れたものが面白いと思い、中国風の世界で、ガンダムみたいなロボットが活躍する話を書き、一回酒見さんと同じ日本ファンタジーノベル大賞に送ったことがあります。それが大学卒業ギリギリの時期でした。
――中国風の世界でガンダムみたいなロボットが出てくるって、いったいどんな話なんですか。
潮谷:アニメの「ガンダム」がずっと好きだったんですね。あれはいろんなシリーズが出ていますが、確かその頃の最新作が「∀ガンダム」だったんですよ。地球の文明が衰退して、ほとんど中世くらいの文明に戻った世界が舞台で、衰退する前に月に逃れた人たちが戻ってきて悶着が起き、そこで地球に隠されていたガンダムが見つかる、という話でした。中世風の風景の中にガンダムがいて、牧畜の牛などを運んだりするシーンがあったりして、それが面白かったんです。その影響を受けました。やっぱり自分は結構、読んだ小説やエンタメに影響を受けていると思います。












