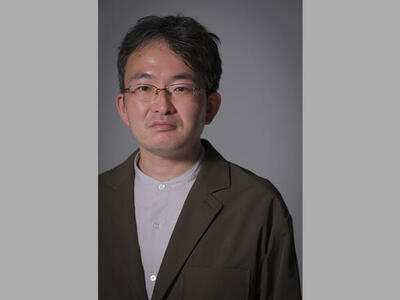
作家の読書道 第268回:潮谷験さん
2021年にメフィスト賞受賞作『スイッチ 悪意の実験』でデビューして以降、斬新な設定とフーダニットを組み合わせたミステリーで楽しませてくれている潮谷験さん。幼い頃からミステリー好きだったのかと思いきや、意外にも作家を志すきっかけは司馬遼太郎さんの『項羽と劉邦』で、歴史小説を書こうとしたのだとか。そんな潮谷さんの読書遍歴、デビューの経緯、最近の読書生活とは?
その4「SFからも影響を受ける」 (4/7)

-
- 『ブギーポップは笑わない (電撃文庫)』
- 上遠野 浩平,緒方 剛志
- KADOKAWA
-
- 商品を購入する
- Amazon
――やはりSFもお好きだったんですね。潮谷さんの『時空犯』はタイムリープものですし。
潮谷:SFでいちばん影響を受けたのは『星界の紋章』ですね。宇宙で戦争をする王道中の王道のSFです。そこから、たとえばジェイムズ・P・ホーガンの『星を継ぐもの』を読んだりもしました。
他に影響を受けているのは、やっぱり森博嗣先生。現代の科学でできないことは書いていないけれど、発想がSFといいますか。たとえば『すべてがFになる』は20年近く前の作品なのに、VR空間が出てくるんですよね。ロボットとかも出てきて、ああいう地に足のついたSFも面白いなと感じます。
定番でいうと、小松左京さんの『果しなき流れの果に』も好きです。あれはタイムスリップしますね。
タイムリープでいうと、すごく影響を受けた作品が1冊あります。富士見ミステリー文庫のライトノベルなんですけれど、田代裕彦さんの『シナオシ』です。20年くらい前の作品なのかな。これがタイムリープものなんです。わりとページ数は短いんですけれど、ものすごく斬新なことをやっているんです。ある人物が人を殺してしまうんですけれど、そのことを後悔してもう1回やり直したいと思う。それで超常的な存在にやり直す機会をもらい時間を遡るんですが、遡った先で、本人ではなく別の人物の心の中に入ってしまう。しかもそのせいで、自分が誰だったのか、自分がどういう事情で誰を殺してしまったのか分からなくなってしまう。とにかく殺してしまうことだけは憶えていて、乏しい材料の中でなんとかもとの自分が誰かを殺すのを止めようとするんです。というものすごく面白い発端の話が、300ページくらいでまとまっている。構成もすごく美しくて、こういうのを自分でも1回書いてみたいと思ったことが、『時空犯』に繋がっています。
――面白そう。
潮谷:それとSFでいうと、はずせないのが上遠野浩平さんの『ブギーポップは笑わない』。これも一世を風靡した作品で、ミステリーを読み始めた頃に知りました。
怪物みたいなものが出てきて事件が起きる話ですが、それを一気に書かずに、関わった人たちの群像劇になっているんですよね。第一話はほとんど関わっていない人の目から見た話で、第二話は変なことが起きているとちょっとだけ理解している人の視点で、また同じ時間軸から話が始まる。第三話あたりでわりと深く関わっている人を出して、最終話で事件を解決したの人の視点になり、全体を通してこういう話だったのかと分かる。ああいうミステリーの手法をライトノベルでやったのって、上遠野さんが初めてなんじゃないかと思って。だから私以外にもいろんな人に影響を与えていると思います。少なくともこれを読んだら、自分も一回は群像劇を書きたいと思うんじゃないかな、と。
それと、『翼ある闇』をきっかけに講談社ノベルスをいろいろ読むようになり、メフィスト賞という存在も知りました。講談社ノベルスで書いておられた西澤保彦さんは特殊設定の元祖なんじゃないかと思いますね。西澤さんが書かれているもので影響を受けたのは、「チョーモンイン」シリーズ。『実況中死 神麻嗣子の超能力事件簿』などがあります。これは超能力者の犯罪を取り締まっている組織みたいなものがある話なんですけれど、どういう超能力があるのかがリストになっていて、どれかの能力が使われた時点でセンサーみたいなものが作動して、「今この能力が使われました」と分かるんですね。この範囲内にこの能力が使われたから容疑者を捜しに行きます、みたいな感じなんです。あらかじめ特殊設定のルールみたいなものを読者にフェアに提示して推理をしている点は、他の作品にも影響を与えているんじゃないかなと思います。
なので講談社ノベルスからは多様な影響を受けていて、自分も講談社から本を出したいなと思っていた頃に、西尾維新さんがデビューされまして。
――西尾さんは2002年に『クビキリサイクル 青色サヴァンと戯言遣い』でメフィスト賞を受賞されてますよね。
潮谷:衝撃を受けました。森さんを読んだ時もすごく新しいと思ったんですけれど、西尾さんも新しいと思って、でも何が新しいのか自分では分析できなかったんです。この新しさが分からないとデビューできないんじゃないかと、いろいろ悩みました。
――当時、読書記録をつけて、この作品のすごいところはここだ、みたいな分析をノートに書いたりしていたのですか。
潮谷:わりと書いていたんですけれど、中断したりもして...。今回、このインタビューのお話を受けて部屋の中をさらったら、ある程度書いていたものが見つかったんですよ(と、ノートを見せる)。吉村昭さんの『仮釈放』を読んだ、などと書いてありますね。
――めちゃくちゃ細かく書かれてありますね...!!
潮谷:思えば、結構ノンフィクションも読んでいます。社会問題を取り扱っているものや、科学技術を取り扱っているノンフィクションが多いですね。
――科学技術といいますと、たとえば。
潮谷:わりと最近読んだものでいえば、渡辺正峰さんの『意識の脳科学 「デジタル不老不死」の扉を開く』とか。人間が死んでからも精神が保存されるという話はSFでも書かれているし私も書いているんですけれど、この作者の方はそれを絵空事ではなく、ご自身が死ぬまでにその技術が実現して、永遠に電子の世界で生きられないかを真剣に考え、そのための方策をいくつも挙げて、どれが一番実現可能性があるかと検証しているんです。ちなみに講談社現代新書です。
――それって、潮谷さんの『あらゆる薔薇のために』に影響を与えたのでしょうか。あれは記憶にかかわるミステリーでしたよね。
潮谷:いや、この本を読んだのはあれを書いた後だったんですよ。書く前にこれを読んでいたら、『あらゆる薔薇のために』の内容がまったく変わっちゃったんじゃないかと思うレベルで斬新なことを書いておられます。









