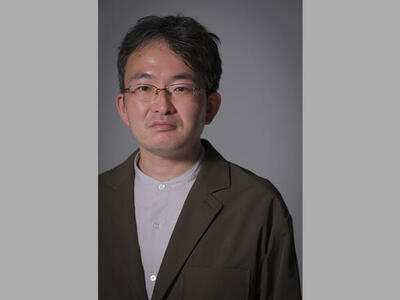
作家の読書道 第268回:潮谷験さん
2021年にメフィスト賞受賞作『スイッチ 悪意の実験』でデビューして以降、斬新な設定とフーダニットを組み合わせたミステリーで楽しませてくれている潮谷験さん。幼い頃からミステリー好きだったのかと思いきや、意外にも作家を志すきっかけは司馬遼太郎さんの『項羽と劉邦』で、歴史小説を書こうとしたのだとか。そんな潮谷さんの読書遍歴、デビューの経緯、最近の読書生活とは?
その6「デビュー後の読書生活」 (6/7)
――執筆時間など、一日のタイムテーブルは決まっていますか。
潮谷:一応、執筆用に自習室みたいなところと契約しているんですけれど、そこが利用できるのが最大で1日8時間なんですね。なのでその中で収めています。でも正直、いちばん集中できる時間って3、4時間くらいが限界なので、その時間以外は細かい調べものとか、読書に当てたりしています。
――デビュー後の読書生活に変化はありましたか。
潮谷:ある程度自分が書くものに有益というか、参考になるものを意識して読むので、半分仕事になっちゃうところがありますね。やっぱりミステリーが増えたかな。
でも、ミステリージャンルで後からデビューした人間は、これまでにない題材や切り口を取り入れたほうがいいと思うので、自分もミステリーに活用するためにあえて全然ミステリーとは関係のない分野の本も読むようにしています。なるべく本屋さんでぱっと見て興味を引いたものを選んでいますね。それと、やっぱりトレンドも知りたいので、最近発売されたミステリーや、あるいはまだ手を出していなかった古典ミステリーを探したりもします。
――そういうなかで、これが面白かったというものってありますか。
潮谷:そうですね。最近、実録物を小説にしたようなミステリーが立て続けに出ていまして。去年出たジョセフ・ノックスの『トゥルー・クライム・ストーリー』は、行方不明になった女子大学生に関して、周りの人に少しずつインタビューしたものを1冊にまとめている体の作品で、地の文がまったくないんですね。読んでいくとだんだん事実が明らかになっていくんですけれど、その臨場感がすごかった。こういうやり方があるんだなとびっくりしました。
一昨年出たジャニス・ハレットの『ポピーのためにできること』は、裁判の記録やメールの文章や新聞記事だけで事件を読み解いていく話で、これも地の文がなくて、登場人物たちの生のやりとりだけで真相を当てていく構成が面白かった。
そうしたら、今年また同じような趣向の小説が出たんです。ダニエル・スウェレン=ベッカーの『キル・ショー』。女子高校生の失踪事件が起きて、周囲の人たちへのインタビューで構成されるのは『トゥルー・クライム・ストーリー』と同じなんですが、ちょっと違うのは、ここにドキュメンタリー番組のスタッフが関わってくるんです。その番組のスタッフが女の子の家族に取材して、彼らが困っている様子をテレビで放送する展開になるんですね。テレビ局の意向が入ってきて、リアルな話の中に作り物が入り込んでくるという、さらにひとひねりある内容になっています。
この3冊がすごく面白くて、自分でもこういうものを書いてみたいなと思ったくらいでした。ただ、これらはアメリカやイギリスが舞台なんですけれど、日本を舞台にすると、ちょっとなにかニュアンスを変えるべきなのかなというのがあります。
――海外のミステリーもいろいろ読まれているんですね。
潮谷:ひょっとしたら海外から入ってくる時点でフィルターがかかっているのかもしれないけれど、海外ミステリーのほうが実験的なものが多いような気がするんですよね。ロジックを重視するのは国内ミステリーのほうが多い印象で、それはまあ新本格というムードがあったからかもしれないんですけれど。推理する楽しさという点では国内ミステリーの方が強いんじゃないかと思います。
――そうした本は、書店で見つけることが多いのですか。それとも書評や新刊情報をチェックしていますか。
潮谷:書評や雑誌の新刊情報に頼りっきりです。ネットの「翻訳ミステリー大賞シンジケート」とか、「道玄坂上ミステリ監視塔」といったサイトや、YouTubeなら杉江松恋さんと若林踏さんの「ミステリちゃん」やその派生型の「翻訳マッハ!」、ヨビノリたくみさんと齋藤明里さんの「ほんタメ」とか。他にも読書専門のVTuberの方もいろいろいらっしゃるので、時々検索して見ています。
――国内作品で印象に残っているものはありますか。
潮谷:去年文庫化された古泉迦十さんのメフィスト賞受賞作『火蛾』が印象に残っています。受賞された時に「メフィスト」本誌の選考委員の座談会を見て、この作品は今読むと影響されそうで怖いなと思い、十数年後にデビューしてからやっと読んだんですけれど、やっぱり想像以上の話だったというか。12世紀のイスラム教社会を舞台にした、語り手が変わっていく話なんです。現実の歴史にプラスアルファしてフィクションが加わっているとは分かるんですけれど、それがどこまでかが混然としていて分からないんですよね。そういう意味では、実際の歴史の中に架空の国を入れた『伯爵と三つの棺』と通じるところがあるんですけれど、それを私の作品よりもさらに巧みにされていて、本当に現実と空想が溶け合うような話になっていて。いつまでも頭の中に残っている作品です。
――ミステリー以外の小説では。
潮谷:何かの書評で見かけて気になって乗代雄介さんの『旅する練習』を手にとったんです。これは最後の数行で意外なことが書かれているんですが、読み返すと、地の文を書いている主人公の文章と、旅の途中で練習として書いている文章に微妙にテンションの違いがあるんですよね。何かが起こったのかな、と思わせる感じにはなっている。ミステリー的な読み方もしようと思えばできるんですよね。あれはある種の手記文学の新しい手法というか。手記の中に、もうひとつ別の時期の手記が入っているというのは斬新だと思います。
私の作品は『スイッチ 悪意の実験』と『伯爵と三つの棺』だけが一人称なんですが、もし『スイッチ』を書く前に『旅する練習』を読んでいたら、書き方もずいぶん違っただろうと思うくらい、『旅する練習』にはびっくりしました。
――小説以外で影響を受けたエンタメってありますか。映画とか。
潮谷:映画はあまり観ていないんですけれど、小学生の頃にテレビで放送されていた、ジョン・カーペンターの「遊星からの物体X」にはたぶん、いちばん衝撃を受けているんじゃないかと思っていて。南極の基地に怪物の乗ったUFOが落ちてきて、みんなその怪物に少しずつ同化されていく。同化された人間と、それに立ち向かおうとする人間がいるわけですが、誰が怪物に同化されているのか分からないんですね。ある意味、クローズドサークルの犯人当てみたいなところがある。ちょっとずつ、怪物特有の性質など、手がかりを見つけていくんですよね。今思うとかなりミステリー的な要素がありました。
それ以外では、わりと正統派のエンタメ映画が好きですね。最近だと「マッドマックス 怒りのデス・ロード」とか。正統派かは分からないですけれどアリ・アスターの「ミッドサマー」も面白かった。あの映画はある意味、因習村もののミステリー的な要素があって、不安にさせていく過程がすごく上手いなと思いました。
それと、DVDで観た映画ですが、「ワーテルロー」という作品があります。「戦争と平和」などのセルゲイ・ボンダルチュク監督の作品で、ナポレオンの最後の戦いであるワーテルローの戦いが舞台です。これがものすごくお金をかけている。全篇合戦シーンなんですけれど、CGもない時代なので全部本物なんですよ。私が生まれる前の作品なので映画館では観ていないんですけれど、あれこそ映画館で観るにふさわしいと思えるダイナミックな作品でした。
――これまでに「ガンダム」や「けいおん!」も挙がっていますが、アニメはいかがですか。
潮谷:アニメを真剣に見るようになったのはどちらかというと、創作というものを意識するようになってからです。展開を追いかけながら「自分ならこうするな」と思ったことが作品のアイデアに繋がったりします。
「ガンダム」シリーズは今でも好きで、最近映画化された「ガンダムSEED」シリーズとかも観ているんですけれど、あのシリーズってやっぱり、台詞のぶつかり合いが面白いですよね。ロボット同士で戦いながらも意見のぶつけ合いみたいなことをやっていて、ビジュアルの面白さだけでなく台詞の面白さがあるのが、長年愛されている理由のひとつじゃないかなと感じます。
日曜の朝の子供向けのアニメや特撮も見ます。子供向けのものって、常にいろんな制限があるじゃないですか。なのに毎回、違う内容の作品が出てくる。形式を守りつつ新しいことにチャレンジしているのを見ると、ミステリーに通じるところがあると感じます。
――これは画期的だったと思う作品などありますか。
潮谷:そうですね、結構あるんですけれど...。去年放送された特撮ものの「王様戦隊キングオージャー」というのは、そもそも現代が舞台ではないんですよ。戦隊ものですが舞台は地球とよく似た別の星で、そこに五つの国があって、それぞれの王様が変身して敵と戦うんです。子供向けの番組なのに、王様はどうあるべきかという君主論的なものも出てきたりする。なぜそういう設定になったのかというと、たぶんコロナの時期でロケができなかったからですよね。全篇セットとCGで作らなくていけなくなったんでしょうね。そういう大変な制限があるところからでも、斬新なものを生み出せるんだなと思いました。







