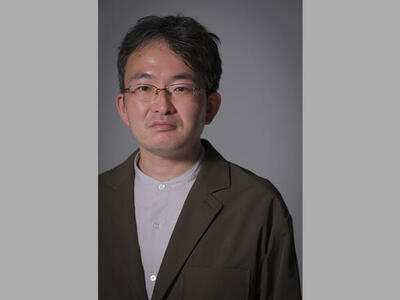
作家の読書道 第268回:潮谷験さん
2021年にメフィスト賞受賞作『スイッチ 悪意の実験』でデビューして以降、斬新な設定とフーダニットを組み合わせたミステリーで楽しませてくれている潮谷験さん。幼い頃からミステリー好きだったのかと思いきや、意外にも作家を志すきっかけは司馬遼太郎さんの『項羽と劉邦』で、歴史小説を書こうとしたのだとか。そんな潮谷さんの読書遍歴、デビューの経緯、最近の読書生活とは?
その7「最近の自作について」 (7/7)
――ギリシャ神話などはお好きだったんですか。『ミノタウロス現象』では、ミノタウロスのような怪物が世界のあちこちに現れます。
潮谷:ギリシャ神話も昔ムックなどでいろいろ読んでいました。あと、インド神話も結構好きだったりします。
でも『ミノタウロス現象』は、どちらかというと後から神話を当てはめたんです。最初は怪物のイメージも漠然としていました。設定上、世界に足跡が残っている怪物がいいなと考えているうちに、ミノタウロスと、ミノタウロスを閉じ込めた迷宮の構造などがこの話に取り入れやすいと気づいたので採用しました。ミノタウロス関係の図柄みたいなものは世界中に残っていて、そのほうが説得力もありますし。
――京都にある街にも怪物が現れて、史上最年少の女性市長が対応せねばならなくなるんですよね。彼女がちょっとコミカルなキャラクターで楽しくて。これまでの作品とはまた違った読み味も面白かったです。
潮谷:ありがとうございます。この作品のみ、KADOKAWAさんから出ている長篇なんです。最初にお話をいただいた時に、可能なら出版社ごとに微妙に作風を変えたら面白いんじゃないかと思いまして。そんなことを言いつつ、次が思いつかなかったら、他の出版社と同じ作風になるかもしれませんが。
それと、編集者さんが「わりとうちは出版時点から映像化を意識している会社です」とおっしゃっていて、だったら怪物が出てくると面白いかなって。CGの怪物って、あんまり気合を入れていないと、ちょっとしょぼく見えるじゃないですか(笑)。
――ああ、この作品に登場するミノタウロスも、あっさりやっつけられて、ちょっとしょぼいですよね。最初のうちは。
潮谷:この話のミノタウロスの設定なら、しょぼいビジュアルでも面白いと思うんです。それで、映像化を意識して適度にいい感じのアクションシーンも入れたりしました。まあでも、現時点で特に映像化の話があるわけではないです。
――『ミノタウロス現象』に限らず、京都が舞台のものが多いのは、ご自身が知っている土地だからですか。
潮谷:そうですね。いわゆる京都の中心部でなく周辺地域で育ったので、せっかくなら、あまりミステリーの舞台にはされていない、地味な京都を出してみたいというのがあります。
それと、書く時に距離感覚が想像しやすいというのがあります。たとえば作中で、ちょっと時間があるからどこどこに行って食事しよう、という場面を書く時、知らない土地だと普通なら行かないであろう距離の場所を出してしまいそうになるんです。そのへんが書きにくいので、基本的に舞台は京都にしています。3作目の『エンドロール』は東京の話ですが、実在の地名を全然書いていないのは、そうしたあたりが怖かったからです。
――なるほど。そして京都以外の舞台といえば、新作の『伯爵と三つの棺』ですよね。フランス革命直後のヨーロッパの架空の小国が舞台という。
潮谷:これは実在の土地を参考にして、だいたいここからはこれくらいの距離、と念頭に置いて書きました。
これは、さきほどお話ししました、最初に書いたヨーロッパの長篇と同じ舞台を使っていますが、登場人物はまったく違います。編集者に「好きなものを書いていいよ」と言われた時に、あの設定で何か書けないかなと考えたのが『伯爵と三つの棺』でした。
以前に書いたものは戦争が出てきますけれど、今回はそうした戦争の裏で、こんなことがありましたという感じの話になっています。
デビューしてからいろいろな人の本を読んでいるうちに、設定や世界観を全部出さなくても話は成り立つなと分かってきたんです。最小限のことだけ書き、小さい区域だけの話にすれば、逆にすっきりまとまったミステリーにするのも可能ではないかと。それで、同じ土地でまるっきり違う登場人物を使って、面白いロジックのフーダニットを書こうとして組み上げていきました。
――なおかつ、今回は手記というか、回顧録という形式が大きな試みでしたよね。この形式にした意味もちゃんとあるという。
潮谷:ミステリー好きだとやっぱり、手記ミステリーは絶対一度は読みますし、書きたくなりますよね。自分も挑戦したかったんです。
――ある古城で殺人事件が発生。目撃された容疑者は、城の改修を手掛けていた男。といっても彼は三つ子で、三人は性格はまったく違うけれども顔がそっくり。指紋やDNAの鑑定が出来ない時代に、誰が犯人かどうすれば特定できるのか、という。その謎解きも面白いのですが、その国の風俗や、事件の捜査方法、近隣諸国との関わりなどがしっかり作られていて、かつ説明的ではなくて面白かったです。他の作品を読んでいても、細部を丁寧に設定されているなと。
潮谷:やっぱり、そこは『星界の紋章』や『マヴァール年代記』の影響ですね。特に田中芳樹先生は設定を細かく決めていても、作中であまり説明しないんですね。説明しないけれど、読んでいくうちになんとなく分かってくる。そのさじ加減がすごいなと思っていたので、それを意識しました。
本作でも、たとえば描写を細かくしようと思ったら、この時使った食器は何々様式であるというところまで書けるんですけれど、あまり本筋とは関係ないので書きませんでした。
――当時の洋服のミニチュア版の写真が掲載されていますが、ご自身で作ったのですか。
潮谷:そうです。フェルトや、百均とかで買ったレースで作りました。といっても平面的でぺらぺらな作りなので、実際に人形に着せることはできないんです。写真にとってコピーして年代感を出せば、立体感のなさもあまり気づかれないと思ったので。
――地図の原案もご自身で作ったそうですよね。そういえば『ミノタウロス現象』も迷宮の図版が載っていましたが、あれもご自身で書いたのですか。
潮谷:ミノタウロス関係の文献に迷宮の図は載っているんですけれど、そのまま転載すると問題があるので、参考にしながら書きました。あの迷路の存在自体は実際にあるので、著作権上は問題がないはずなので。
『伯爵と三つの棺』も『ミノタウロス現象』も現実から乖離した要素が強いので、何か具体的なイメージがわく小道具があったほうがいいかな、というのがありました。それっぽい地図とか、それっぽい写真とか、絵とかがあると説得力が出てくるように思います。
――『伯爵と三つの棺』では、伯爵の家臣が公偵という探偵的な役職についているといったことなども面白かったです。
潮谷:公偵制度などに関しては完全にオリジナルです。当時の実際の捜査方法を書くとなると、フランスやドイツでは別々の制度があるんですけれど、どっちにしろいわゆる警察というものがなかったので、そこを埋めるものを設定したほうがいいかなと思いまして。
――歴史小説を書きたいと思ったことが作家を志すスタートでしたが、こうして歴史ものを書いてみて、やはり楽しかったですか。
潮谷:面白かったですね。今回は架空の国の話でしたが、また同じ世界観で、全然違う場所で書いても面白いだろうなと思いました。逆に大学生の時に書けなかった、本当の歴史を題材にしたミステリーも書いてみたいですね。それこそ米澤穂信さんの『黒牢城』みたいなものを書いてみたいと思いますし。歴史ミステリーって有名な人でないと駄目なのかなと思っていたし実際にそう言われていたんですけれど、『黒牢城』で、主人公がそれほどメジャーではない人物でも、優れたものが書けるし評価されると分かりましたよね。米澤さんの筆がすごいというのはもちろんですけれど、でも自分でやってみたいです。
ただ、日本史のほうが難しいんじゃないかという気はしますね。資料が残りすぎているので、下手なことを書くと「ここはおかしい」と指摘されそうです。中国史は一応自分の専門分野でもあったので、まだ書けるかなと思います。
――犯人当てミステリーになるんでしょうか。
潮谷:そうですね。犯人当てでもいいし、最初に犯人が分かっていて、その人を追い詰めていく形でもいいと思うんですけれど...。ただ、あまり大きな話になりすぎると、その中で一人の犯人を当てる、というのはバランスが悪そうなので気をつけないといけないですね。
――今後の刊行予定等を教えてください。
潮谷:「メフィスト」に連載していた『誘拐劇場』という新作が2025年の夏くらいに単行本になる予定です。ちなみにちょっとだけAIが出てきます。最近、AIが注目されているので、今のうちに登場させておきたいなと思いまして。特にAIに文章を考えてもらったわけではないんですが、作中でちょっと面白い役割をしています。
(了)




