『水を縫う』寺地はるな
●今回の書評担当者●精文館書店中島新町店 久田かおり
これはアタクシ的ド直球の好きが詰まった一冊だ。出てくる誰も彼もが好きだし、語られるエピソード一つ一つが好きだし、表紙も好きだしタイトルも好きだし。とにかく何から何まで大好きだ。
登場人物は祖母と母と姉と弟、そして離婚した父とその友人。6章のうち最初と最後は表紙に描かれている高校生の弟の語り。残りの4章が姉、母親、祖母、父の友人による語り。おや? 父親はどうした? 出番はないのか?
そう。父親である全さん(全くもってダメな父親の名前が「全」だなんてすごいよね)の語りはない。自らが語らないことでこそその人の存在がくっきりと浮かび上がるというか、語っちゃったら逆に何か大切なことが見えなくなってしまうというか......。
この「家族」の6人は6人とも(父親の友人は家族じゃないよね? でもそこ大事なところなので読むときのお楽しみにしてください)、不器用でこだわるものがあって、とても生きにくそうに世界のちょっと隅っこで肩をすぼめている。彼らはみんな、「らしくあること」に押しのけられているようだ。
女だから、女らしく。男だから、男らしく。母だから、母らしく。父だから、父らしく、と。そもそもなんなんだよ、「らしく」って。誰だ決めたことなんだ、「らしさ」って、と腹が立ってくる。
でも、自分も知らず知らずに「らしさ」にからめとられてはいやしないか。自分自身を、相手を、家族を、いろんな「らしく」に押し込めようとしていないだろうか、とふと不安になる。
誰もがそれぞれに、自分の中に多かれ少なかれ違和感を持っているんじゃないか。外から求められる自分と、自分が感じている自分と。いわゆる「自分らしさ」に。
生きたいように生きていけないもどかしさ、息苦しさを飼いならそうとしている。そうそう、息苦しさの極致にいる母親の突然の病がまさにその象徴でもあるのだろう。
なかでも結婚間近の姉、水青の「かわいい」や「女の子らしさ」への拒絶が一番悲しく一番つらかった。その原因となった出来事、許しがたい。まじで許すまじ。
そんな姉が結婚式で着るドレスを弟が作ると言い出す。この弟、清澄くんがとてもいいんだな。彼が高校生になってできた二人の友だちとのやりとりや、父親への屈託のなさを作ってくれた父の友人黒田の存在が彼の成長には必要不可欠であった。いやぁ、黒田がこの家族に及ぼした影響の大きさたるや! 友人である父親に、その子どもたちに何物にも代えがたい贈り物をしている黒田。いい味出してるよね黒田。彼にはどうにかして幸せになって欲しい。黒田のサイコーさについてだけでも一晩語り合えそうだ。
というわけで、ここにはいろんな「成長」がある。不器用な家族+αたちの、生きにくさからのほんの一歩の成長の物語なのだ。
ぼきぼきと折れながらもなんとかまっすぐに生きようとする彼らが迎えた、とある朝。彼らの笑顔が目に浮かぶような、その朝の場面。このすがすがしさを一緒に体感して欲しい。身も心も洗われ思わず深く息を吐く。
寺地はるなは裏切らない。
心地よい涙がにじむラストを楽しみに読むべし。
- 『赤ちゃんをわが子として育てる方を求む』石井光太 (2020年5月28日更新)
- 『ザリガニの鳴くところ』ディーリア・オーエンズ (2020年4月23日更新)
- 『文身』岩井圭也 (2020年3月26日更新)
-
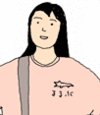
- 精文館書店中島新町店 久田かおり
- 「活字に関わる仕事がしたいっ」という情熱だけで採用されて17年目の、現在、妻母兼業の時間的書店員。経験の薄さと商品知識の少なさは気合でフォロー。小学生の時、読書感想文コンテストで「面白い本がない」と自作の童話に感想を付けて提出。先生に褒められ有頂天に。作家を夢見るが2作目でネタが尽き早々に夢破れる。次なる夢は老後の「ちっちゃな超個人的図書館あるいは売れない古本屋のオババ」。これならイケルかも、と自店で買った本がテーブルの下に塔を成す。自称「沈着冷静な頼れるお姉さま」、他称「いるだけで騒がしく見ているだけで笑える伝説製作人」。

