『はじめての沖縄』岸政彦
●今回の書評担当者●梅田蔦屋書店 三砂慶明
本書は二十代のころ観光客としてはじめて沖縄と出会い、「そうとう気持ち悪いぐらい」沖縄に惚れ、なぜ熱病のように沖縄に恋い焦がれるのか「理由」を探究するうちに、それが一生の仕事になった社会学者の岸政彦氏が、「沖縄についてずっと書きたかったことを書いた」本です。
社会学は、「社会学とは何か」と問うだけで一冊の本ができるほど無数の定義が存在しますが、中でも岸政彦氏は、ある歴史的なできごとを体験した当事者個人の生活史の語りを一人ずつ聞き取るスタイルで調査し、その語りを記録する社会学者です。
たまたま乗ったタクシーの運転手のおじいさんと話しはじめ、
「お客さんはどこからですか? あ、ぼくは大阪からです。こんな感じで、たわいもない会話が始まる。」
最初の質問から、それに答える形で語りがはじまり、その語りが次の質問を生み出す。一人の若い沖縄の男性が、単身大阪へ渡り、さまざまな苦労を重ねて再び、沖縄に戻ってくる。一見ありふれた生い立ちや人生の物語のあとに立ち上がってくるのは、「複雑なサンゴ礁のような、巨大な迷路のような、全体を見渡すことができないほど大きなもの」(『断片的なものの社会学』)。
「沖縄の人々の生活史は、個人の語りでありながらも、同時に、戦後の沖縄史そのものでもある。個人の人生のことを聞き取ることは、実は経済や歴史、あるいは国家や民族について聞き取ることでもあるのだ。」と著者はいいます。
沖縄は、時事問題、歴史や政治、文化や環境だけではなく、沖縄とはどういう場所なのかについて考えるだけでも何冊もの本になるような場所です。
沖縄を見て、沖縄で聞き、寄り添うように側にいて、沖縄について書くこととは一体どういうことなのかと問い続け、日本と沖縄の間に今なお存在する「北緯二十七度線」に何度も立ち返りながら迫っていきます。北緯二十七度線は、1972年まで存在した日本と琉球の境界線です。著者は、沖縄に広がる米軍基地の鉄条網、はてしなく続くシャッターの壁、無人の商店街、停滞しつづける沖縄の経済のなかに、沖縄が背負わされ抱え続ける「歴史と構造」がいまなお横たわっていると指摘します。
『はじめての沖縄』は、沖縄がどういう場所で、誰が何を見、どう語るのか、きめ細かくすみずみまで神経がいきとどいた沖縄への愛がしみこんだ本ですが、何より感動したのは、最初の一頁を開いて読みはじめたときから、目の前に岸政彦氏がいるような気がすることです。
頁をめくる度に、著者と一緒に沖縄の町を歩きながら、居酒屋でお酒をくみかわし、著者が耳を傾けつづけた果てしない人びとの物語がどこまでも広がっていくのは、まるで『遠野物語』のようです。人間が、人間にむかって語る人生の物語から、差別とはなにか、マイノリティとはなにか、良い社会とはなにか、という問いが等身大の問題として立ち上がってくるのは感動的です。「言葉というものは、単なる道具ではなく、切れば血が出る。(中略)人の語りを聞くということは、ある人生のなかに入っていくということである。」(『断片的なものの社会学』)。私は岸政彦氏の本を読んではじめて他人事ではなく、ただ淡々と事実として目の前にある沖縄の姿を知ることができました。
- 『火星で生きる』スティーブン・ペトラネック (2018年6月7日更新)
- 『4歳の僕はこうしてアウシュヴィッツから生還した』マイケル・ボーンスタイン&デビー・ボーンスタイン・ホリンスタート (2018年5月10日更新)
-
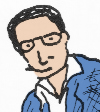
- 梅田蔦屋書店 三砂慶明
- 1982年西宮生まれの宝塚育ち。学生時代、担当教官に頼まれてコラムニスト・山本夏彦の絶版本を古書店で蒐集するも、肝心の先生が在外研究でロシアに。待っている間に読みはじめた『恋に似たもの』で中毒し、山本夏彦が創業した工作社『室内』編集部に就職。同誌休刊後は、本とその周辺をうろうろしながら、同社で念願の書籍担当になりました。愛読書は椎名誠さんの『蚊』「日本読書公社」。探求書は、フランス出版会の王者、エルゼヴィル一族が手掛けたエルゼヴィル版。フランスに留学する知人友人に頼み込むも、次々と音信不通に。他、読書案内に「本がすき。」https://honsuki.jp/reviewer/misago-yoshiaki

