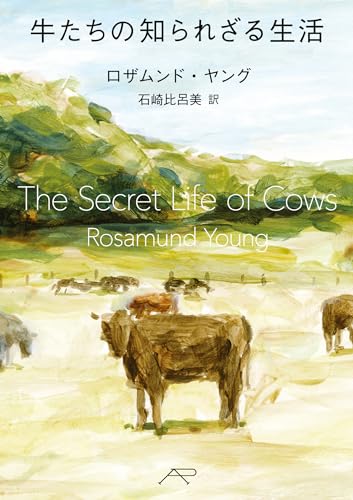『牛たちの知られざる生活』ロザムンド・ヤング
●今回の書評担当者●梅田蔦屋書店 三砂慶明
書店員の間でよく知られている良い本の見分け方の一つに、装丁があります。もちろん好みや相性もありますが、特に細部までこだわった本で面白くなかったということはほとんどありませんでした。その理由はおそらく、その本に心を動かされた編集者やデザイナーが何としても読者に届けたいと試行錯誤するからだと思います。本書をはじめて見たときに、間違いなくこの本はいい本だろうと直覚しました。定価も1600円と、2000円を切っているところに、この本を多くの読者に届けたいと願う営業担当の方の熱意も感じます。
しかしながら、帯の推薦文
「個性あふれる牛たちとの友情にみちた物語 イギリスのオーガニック農場「カイツ・ネスト・ファーム」で暮らす牛たちの日常(と事件)を、愛情豊かに描いたエッセイ。」
にはあまり引きこまれず(すみません)、序文だけ読んで棚に戻そうと思っていたら、『やんごとなき読者』(白水社)のアラン・ベネットの推薦文に、しっかりと鷲掴みにされてしまいました。
通常、棚に一冊しか在庫がない場合は、取り寄せてから買うことにしているのですが、お客様には心の中であやまりながら、早速購入して読みました。本文が165頁と短く、一気に読んでしまいましたが、読み終わるのがもったいなくて、なぜかあとがきを読む前に、頁をとじてしまいました。本来でしたら、最後の最後まで読んでから読書案内を書くべきでしょうが、読めませんでした。
まさか、農場で暮す牛について書かれたノンフィクションで、ここまで心を揺さぶられるとは思いませんでした。本書が読者をつかんではなさないのは、まったく経験したことも想像したこともない、牛や豚や羊や鶏の知られざる世界に連れて行ってくれるからです。牛や子牛が草を食む風景に、想像力がかきたてられるようなドラマが隠されているとは、本書を読むまで考えたこともありませんでした。
この本の著者であり、イギリスのオーガニック農場「カイツ・ネスト・ファーム」の経営者の一人でもあるロザムンド・ヤングは、集約管理型の大規模農場で動物に感情がなく、単に利益を生む食料として考える効率的な仕組みは、経営者の視点から見ても、間違っていると指摘します。
ヤングは牛を牛として描かず、ひとりの人間のように丁寧に綴っていきます。冒頭に家系図が載っているのでヤング一族のものかと思ったら、農場の牛の家系図でした。司馬遼太郎の群像劇のように、一頭一頭の牛の個性に光をあてて、農場を経営するというのは、考えただけで気が遠くなりそうですが、ヤングが営む農場では、農場のすべての牛に名前をつけ(さらにあだ名もつけ)、牛乳を飲めば、どの牛からしぼられた牛乳かを言い当てることができるといいます。
牛にはうわべの付合いはないと喝破し、「千ページ書いたところで、じっさいの彼女の姿の半分も伝えられないだろう」と愛惜の情をおしまない牝牛アメリアについての詩にも胸が熱くなりました。
テーブルマナーを身に着けた唯一の豚ピギーや、鶏がコッコッと鳴く意味など、タイトル通り、この本には動物たちの知られざる世界が愛情いっぱいに描かれています。
「牛は一頭一頭に個性がある。同じように羊や豚や鶏や、さらに言えばこの地球上に生きるすべてのものは、どんなにちっぽけでつまらないと思われているものにもそれぞれ違いがある。猫や犬に個性があることに異議を唱える人はあまりいないだろう。(中略)つまりは、どんな動物であれ、相手のことを知るにはそれなりの時間をともに過ごす必要があるということだろう。相手が人間でも同じことだ。」
『牛たちの知られざる生活』は、生まれてから毎日、牛を見続けてきたヤングにしか書けないノンフィクションです。その上で、ヤングが問うのは、人間が食べることについて、どう向き合っていくのかということです。
この本を読むまで、恥ずかしながら私が食卓で考えていたのは、おいしいか、おいしくないか、高いか安いかぐらいでした。私たちは、生きるために食べざるを得ません。しかし、何を食べて生きるのか?
ヤングが描いてくれたこの世界を知る前と、知った後とでは、私たちは変わらざるを得ないと思います。この本は読者に毎日当たり前のように生きている風景に大きな疑問をつきつけてくれる、そういう本だと思います。
- 『一日一文 英知のことば』木田元 (2019年1月3日更新)
- 『ストリートの精霊たち』川瀬慈 (2018年12月6日更新)
- 『これは水です』デヴィッド・フォスター・ウォレス (2018年11月1日更新)
-
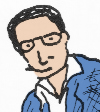
- 梅田蔦屋書店 三砂慶明
- 1982年西宮生まれの宝塚育ち。学生時代、担当教官に頼まれてコラムニスト・山本夏彦の絶版本を古書店で蒐集するも、肝心の先生が在外研究でロシアに。待っている間に読みはじめた『恋に似たもの』で中毒し、山本夏彦が創業した工作社『室内』編集部に就職。同誌休刊後は、本とその周辺をうろうろしながら、同社で念願の書籍担当になりました。愛読書は椎名誠さんの『蚊』「日本読書公社」。探求書は、フランス出版会の王者、エルゼヴィル一族が手掛けたエルゼヴィル版。フランスに留学する知人友人に頼み込むも、次々と音信不通に。他、読書案内に「本がすき。」https://honsuki.jp/reviewer/misago-yoshiaki