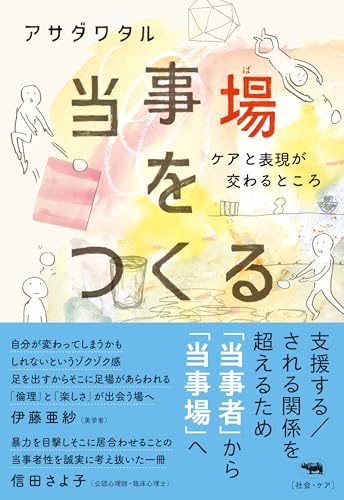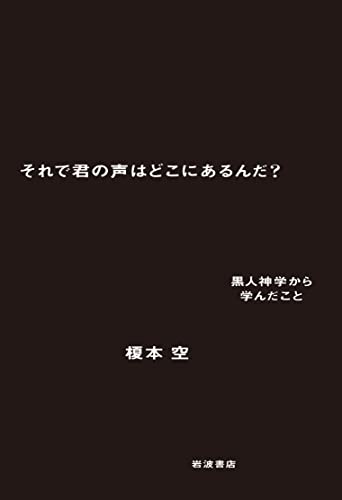『当事場をつくる』アサダワタル
●今回の書評担当者●駿河屋梅田茶屋町店 中川皐貴
災害に遭った人、犯罪に巻き込まれた人。そういった方の話を聞いたり、読んだりしたときに、自分は当事者ではないんだということを思い知る。
当事者たりえない私はどうすればいいのだろう?という問いを、榎本空さんの『それで君の声はどこにあるんだ? 黒人神学から学んだこと』(岩波書店)を読んだ時からずっと抱えている。
「黒人以外の人間が、黒人の背負ってきた苦しみや痛みを理解することは難しい」と、どうしようもない寂しさと諦めを含んで言われたという文章を読んだとき、正直「じゃあどう頑張ったって当事者になれない私はどうしたらいいんだよ」と思っていた。
『当事場をつくる』(晶文社)は、そんな問いの答えのひとつになるのではないかと、読み終えたときに感じた一冊。
本書は、ケアや支援の現場で表現活動を行ってきた著者による、支援とは何か、当事者とは誰か、を思索したエッセイであり論考である。
この本で重要なキーワードは、やはりタイトルにもなっている「当事場」という言葉だと思う。
「当事者性」を、〈個人〉に押し付けるのではなく〈場〉に持ち込むということ。
「当事者になり得なさ」を深く受け止めたうえで、「当事者性」を感受し、熟考し、他者と対話するための〈場〉を創る。その〈場〉を著者のアサダさんは「当事場」と名づける。
元々、人はいろんな一面を持っている。障害当事者は、「障害」だけを持っているのではない。たとえば音楽が好きだったり、穏やかな気質を持っていたり、なんなら背が高いというのも「当事者性」と言えるだろうし、一つしか持っていないなんてありえないのだ。
「当事場」では障害当事者が、「障害」だけではなく、様々な「当事者性」を持ち込んでいく。支援スタッフなどの「非当事者」は、それを受けて「支援者という当事者性」とは別の一面を引き出される。そうして、障害当事者と支援者という関係ではない、たとえば音楽好き仲間といった別の関係性、共通の視点を得て、徐々に分かち合っていくことができるのではないだろうか。
本書は福祉の場で書かれているが、この話は冒頭の黒人差別の問題や他の問題でも言えることだと思う。
「当事者」たりえない私はどうすればいいのか?
大前提として、私は「当事者」になれないことを理解するべきだろう。他人の気持ちを完全に理解することができないように、「当事者」の気持ちを理解し、「当事者」になるなんて土台無理な話だろう。
そのうえで、「当事者」を変えるのではなく、「当事者」も「非当事者」も巻き込んで、両者にはたらきかけることのできる「当事場」をつくるべきなのだろう。「当事場」にいる人たちは「当事者」も「非当事者」も関係なく、みんなが「当事場」を構成する一員になる。
分かち合える人が多ければ多いほど、その場で起こるままならなさを笑い飛ばし、楽しみながら生きていくことができる。
「当事場」を構成する人が多ければ多いほど、その場は豊かに、予測不能に、面白いものになるのだろうと思う。
- 『now loading』阿部大樹 (2025年9月25日更新)
- 『作文』小山田浩子 (2025年8月28日更新)
- 『こうの史代 鳥がとび、ウサギもはねて、花ゆれて、走ってこけて、長い道のり』こうの史代 (2025年7月24日更新)
-
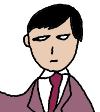
- 駿河屋梅田茶屋町店 中川皐貴
- 滋賀県生まれ。2019年に丸善ジュンク堂書店に入社。文芸文庫担当。コミックから小説、エッセイにノンフィクションまで関心の赴くまま、浅く広く読みます。最近の嬉しかったことは『成瀬は天下を取りにいく』の成瀬と母校(中学校)が同じだったこと。書名と著者名はすぐ覚えられるのに、人の顔と名前がすぐには覚えられないのが悩みです。