『つみびと』山田詠美
●今回の書評担当者●宮脇書店青森店 大竹真奈美
夏の猛暑の中で、ふと思い起こすことがある。
過去に起こった、子どもの車内放置や育児放棄などの放置事件だ。炎天下の車内に乗り込む時や、息苦しいほど暑い部屋に居る時、「あぁ、あの子たちは一体どれ程苦しかっただろう」と胸が痛む。
特に強く記憶に残っているのは、2010年、3歳女児と1歳9ヶ月男児を自宅に閉じ込めて約50日間放置し、餓死させた「大阪2児餓死事件」。事件当初は、居間の扉には粘着テープまで貼られていたことや、からしのチューブなども含め冷蔵庫は空っぽだったことなど、衝撃的でむごい話ばかり。やり切れない思いが燻り、未だ灼熱と共に記憶が炙り出されるのだ。
本作は、その「大阪二児餓死事件」をモチーフに描かれた小説だ。
タイトルの「つみびと」とは誰か。それは読む前からわかりきっている。「鬼母」と呼ばれた彼女こそ「罪人」に違いない、と。
しかし、読後その確信が揺らぐ。むごたらしい事件を引き起こした怒りの矛先に迷いが生じるのだ。
この育児放棄をした母親は、自らもネグレクトの母親に育てられている。壮絶な生い立ちの母を追うように自らも過酷な人生を歩む。ネグレクトがネグレクトを生む。負の連鎖である。
灼熱の中、幼い子どもを部屋に閉じ込め、充分な食事も与えず、家にも帰らない。とてもまともな人のすることじゃない。そう、「まとも」じゃないのだ。しかし、そもそもまともな家に育たず、まともを教わることなく育った子が、一体どうやってまともな大人になるのか。それは想像以上に困難なことなのではないだろうか。
子ども二人を死に至らしめたことは、何がどうあれ絶対に許されないことだ。しかし読み進めるうちに、自分はそれを責めることが本当にできるのだろうか?という疑問が生まれてくる。
今の自分の人格は、なにで形成されているのだろう。生まれ持った人格は何パーセントくらいで、育った環境や経験は、今の自分にどのくらい影響を与えているのだろう。彼女と私は、たまたま人生で積まれたピースが違っただけなのではないか。そんな可能性の恐ろしさを感じずにはいられない。
タイトルである「つみびと」=「罪人」。
脳内でふと変換された、もう一つの「つみびと」。それは、その罪に至るまで、沢山の苦しみや悲しみ、幾多の不幸が積み重なってしまった=「積み人」だ。
我が身に全く同じものが積み重なり「積み人」となった時、同じような「罪人」にならないという確証などどこにもない。それと同時に、いつどのようにして、積む側の人間に加担することになるかもわからない。「つみびと」は思いのほか、ありふれているのではないだろうか。
小説だからこそ読み解ける闇が本作にはある。闇の中で浮き彫りになる母子家庭の貧困問題、誰にも助けを求めることができない社会からの孤立感。彼女は、幸せになりたい、良い母親になりたい、きっとただそれだけだったのではないだろうか。その結果があまりにもかけ離れていてやり切れない。
二度とこのような悲劇をくり返さないために、自分に何ができるのか。読み切るには正直しんどい本作をここで紹介したのは、私なりのひとつの答えだ。
- 『アタラクシア』金原ひとみ (2019年7月18日更新)
- 『むらさきのスカートの女』今村夏子 (2019年6月20日更新)
- 『架空の犬と嘘をつく猫』寺地はるな (2019年5月23日更新)
-
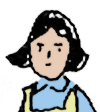
- 宮脇書店青森店 大竹真奈美
- 1979年青森生まれ。絵本と猫にまみれ育ち、文系まっしぐらに。司書への夢叶わず、豆本講師や製作販売を経て、書店員に。現在は、学校図書ボランティアで読み聞かせ活動、図書整備等、図書館員もどきを体感しつつ、書店で働くという結果オーライな日々を送っている。本のある空間、本と人が出会える場所が好き。来世に持って行けそうなものを手探りで収集中。本の中は宝庫な気がして、時間を見つけてはページをひらく日々。そのまにまに、本と人との架け橋になれたら心嬉しい。

