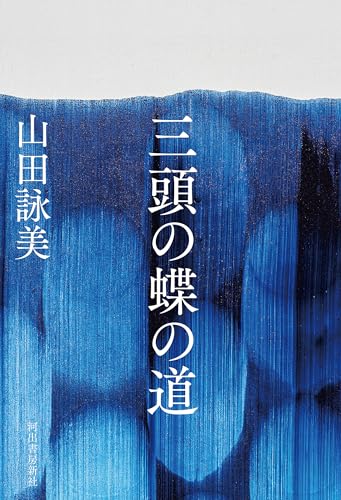【今週はこれを読め! エンタメ編】三人の女流作家の人生〜山田詠美『三頭の蝶の道』
文=高頭佐和子
女流作家。
その言葉を初めて聞いた時のことを覚えている。小学生の頃熱心に本を読んでいたところ、父が「ジョリュウサッカになったらいいんじゃないか」と言ったのだ。「ジョリュウ」って何だろう? 父の言葉に悪意は全くなく、女の人で本を書いている人をそう呼ぶんだね、くらいのことしかその時には思わなかったのだが、次第に「女流」という二文字がつけられる意味を考えるようになった。大学生になる頃にはベストセラーとなっていた『男流文学論』(筑摩書房)を何度も読んだりする感じに成長して今に至るわけなので、2025年の現在に女性の作家をわざわざ「女流」と呼ぶ人がいたら、さぞ残念な気持ちになるだろうと思う。だけど「女流」という言葉を嫌っているのかと言われると、それもちょっと違う。女性が自分の力で生きていくことが困難な時代に、才能や努力で道を切り開いてきた作家たちには感謝と尊敬と憧れの気持ちがある。十代の頃から読み続けてきた作家である山田詠美氏が、デビュー40周年を迎えて「女流作家」を書いたと聞けば、読まないわけにはいかないのだ。
女性で初めて「夏目賞」の選考委員となり、若い才能を見つけ出すことに尽力してきた河合理智子。同じく女性初の「夏目賞」選考委員で、周囲を翻弄する性格の高柳るり子。華やかな人柄と波瀾万丈の人生で、世間の注目を集めてきた森羅万里。強い個性を持った三人の女流作家の人生が、それぞれの葬式から始まる三つの章で描かれていく。同年代で親しく付き合ってきたように見える彼女たちだが、その関係は一筋縄ではいかないものだった。作家、編集者、秘書、親族などさまざまな立場の人々(こちらもすごい迫力)が、自分の目に映っていた彼女たちのことを回想し、思い出を語り合う。いくつもの角度から語られる彼女たちの姿と複雑な関係から、書くことと真摯に向き合ってきたそれぞれの生き方と、文学を巡る時代の変化が鮮やかに描かれていく。
山田詠美氏の作品にはいつもハッと目が覚めるような言葉がいくつも出てくるのだけれど、この小説にも冒頭から鋭く刺さる言葉が次々に登場する。まずは「作家とは嘘八百を文字にして生きる糧を得ている人種」という言葉にビクッとした。そう、今私が読んでいるのはフィクションだ。実在する作家名も出てくるのだけれど、物語の中心にいる一癖も二癖もある三人の女流作家も彼女たちを語る人々も、皆この世に存在しない。嘘の人々のはずなのに、笑ったり眉を顰めたりする表情の変化や、原稿用紙に向かう凛とした背中が目の前に現れてくるようだ。尊敬と嫉妬が入り混じった関係。ライバルや後進に対する愛情や牽制。強靭な精神力と自尊心。子供染みた振る舞い。文学に対する強い思い。その全てはフィクションであっても、著者が見てきた真実が入っているのだろう。だからこそ、きれいごとだけでは語れないその関係や、登場人物たちが発する言葉のひとつひとつに心を掴まれてしまうのだということを、読み進めていくほどに実感する小説だった。
作家たちが身を削って生み出した「嘘八百」に支えられて、今まで生きてきた。「女流」という呼ばれ方を当たり前のように背負って書き続けてきた作家たちの小説を読んでこられたこと、遺されたものをこれからも読めるのだということを、改めて幸福に思う。
(高頭佐和子)