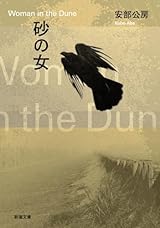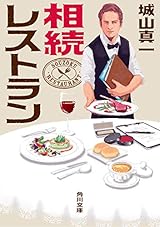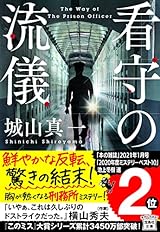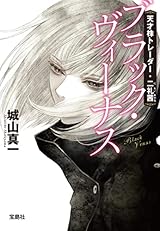作家の読書道 第280回:城山真一さん
2015年に『ブラック・ヴィーナス 投資の女神』で第14回このミステリーがすごい!』大賞を受賞、その後ドラマ化もされた『看守の流儀』などで、ミステリーと人間ドラマを融合させてきた城山真一さん。小学生の頃はあまり小説を読まなかったという城山さんが、その後どんな作品と出会い、小説家を志すことになったのか。小説以外の好きなものも含めて、たっぷりおうかがいしました。
その4「大学時代の背伸びした読書」 (4/9)
――大学は地元の大学に行こうと思われていたのですか。
城山:当時、'80年代から'90年代って子供がすごく多い時期で、うちの高校も半分以上は県外の大学に進学していましたけれど、自分はそこまでこだわりがなくて。むしろ小中学校の時にバス旅行で七尾から金沢に行くだけでも都会に行ったと感じていましたから、金沢に行けるだけで充分だったという。金沢の街の雰囲気も好きだったし、金沢大学に行ければいいなと思っていました。一人暮らしする予定でしたし。
――金沢での一人暮らしは楽しかったですか。
城山:もう、すごく楽しかったです。大学に入ると漫画はほとんど読まなくなりました。相変わらずプロレス雑誌は読み続けていましたが、「ビッグレスラー」が休刊になったので、「週刊ゴング」を読むようになって、これは40歳くらいまで読んでいました。あとは、大学に入ると女の子にモテたいなという思いもあって、「ホットドッグ・プレス」を読むようになりました。お気に入りの連載は北方謙三さんの人生相談コーナーでした。
――「試みの地平線」ですね。
城山:北方さんの回答がどれも斜め上からドカンとくるようなものばかりで、それを読むのが面白くて。
小説は、大学に入ると格好つけていたこともあって、純文学に傾倒していた時期があります。興味があったからというよりも、大学生はこういうのを読まないといけないなと、少し背伸びをしていたというか。村上龍さんの『限りなく透明に近いブルー』とか、村上春樹さんの『ノルウェイの森』とか。安部公房さんの『砂の女』なんかは、読んでいるだけでまわりが砂っぽくなってくる感じがしましたね。遠藤周作さんの『沈黙』は、クライマックスに外国人が和装で登場するシーンがあって、それが衝撃的だった記憶があります。あとは、宮本輝さんの『錦繍』とか。古いものでいうと、谷崎潤一郎さんの『痴人の愛』『春琴抄』が印象深かったです。『痴人の愛』は主人公に変質的なところがあるんですけれど、読んでいるうちに「自分もこんな感じになるかもしれない」と思わせるところがすごいなと。『春琴抄』は主人公が自分で目を潰す描写がすごくリアルで。今ふと思いましたが、五感にすごく訴えてきた小説が記憶に残っている気はしますね。
ただ、大学では勉強に力を入れていたので、そこまで小説はたくさん読んでいないと思います。
それから20年後くらいになるんですけれど、角川文庫で『相続レストラン』という小説を出した時に、大学の民法の授業で得た知識が役立ちました。
――サークルは何か入ったのですか。
城山:大学の時は文科系サークルのESSという、英会話研究会に所属しまして。わりと真剣に活動していて、2年生の後期に部長も務めました。ESSにはディスカッションとかスピーチとかディベートとかドラマとかいろんなジャンルがあって、僕は一通りやったあと、ディベート一本に力を注ぎました。2年生の秋に大学対抗のディベート選手権で北信越地区の代表になって、全日本選手権にも出ました。
英語といえば、大学3年生の夏休みに友達3人とロサンゼルスに行きました。2週間の滞在中、ずっとレンタカーを借りてモーテルを転々とする貧乏旅行でした。そのときは現地のアメリカ人と普通に話せましたけど、今は話す機会がないので、もう全く話せなくなりました。
――ディベートでは、どんなことがテーマになるのですか。
城山:脳死は人の死なのか、とか。ジャーナリストの立花隆さんの『脳死』や医療の専門書を自分で英訳して、英語で喋る訓練をしたりしていました。だからディベートをやっていると、変に偏ったカテゴリーだけ英語で話せる、みたいな感じになるんです。
――他にはまったものなどはありましたか。
城山:大学の頃、想像力をかき立てられて楽しみにしていたのは、小説よりもテレビドラマだったかなと思います。当時好きだったテレビドラマは、「もう誰も愛さない」「愛という名のもとに」「逢いたい時にあなたはいない」「素顔のままで」「パ★テ★オ」「高校教師」「若者のすべて」。映画は、洋画では「レインマン」「ゴースト/ニューヨークの幻」「ブラック・レイン」。ただ僕はわりと邦画も好きで、なかでも山田洋次監督がお気に入りです。山田洋次監督で西田敏行さんと裕木奈江さんが出ていた「学校」は映画館に観に行きました。この作品は今でも深く心に刻まれています。
大学生の頃といえば、「月刊カドカワ」の1991年4月号が「総力特集 氷室京介」で、これも今も宝物として持っています。氷室京介さんのインタビューのなかに、BOØWY時代の4作目の「JUST A HERO」でやっとやりたいことができて、いろんな人が自分たちの音楽に興味を持ってくれて人生が変わった、ということが書いてあって。実は僕も、4作目の『看守の流儀』でやっと自分の書きたいものがちょっとずつ見えてきて、周りの人も僕のことを見てくれるようになったなと思っているので、このアルバムの隣に『看守の流儀』を置いています。ほかにも、そのインタビューの中で、氷室さんが『Higher Self』10曲目の「MOON」というバラードを録音した時に、何百回も歌い直したっていうようなことが書いてあって、びっくりして。あとから、小説も同じだなと思いましたね。自分もやっぱり納得いくまで推敲しないといけないなと思っています。それと、本では『BOØWY STORY 大きなビートの木の下で』も宝物として置いてあります。
――金沢でも書店に通っていたのですか。
城山:書店は大好きでした。金沢には、うつのみや書店という大きな書店がありまして、毎日のように通っていました。『ブラック・ヴィーナス』が出た時に、自分が通っていたその書店でサイン会をさせてもらえて、本当に嬉しかったです。
――大学生の頃は、小説家になりたいとはまだ思っていなかったのですか。
城山:先のことはわからないけれど、とりあえずは普通のサラリーマンになれればいいかなと思っていました。小説を書いて、それを生業にするなんて、そんな大それたことは考えていなかったです。